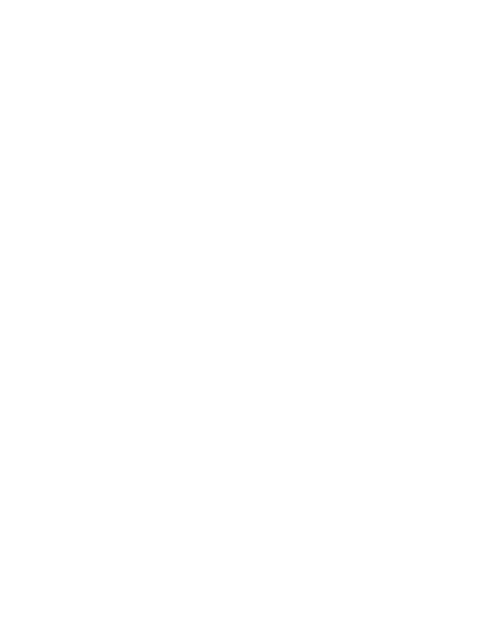今、 私は宣教部長として中部教区にとって非常に重要な役割を担わせていただいています。 その働きの一つとして、 ここ1年間程、 「中部教区宣教方針」 (仮) の作成に向けての協議を様々な場で繰り返しています。 その協議の場の一つで、 ある聖職の方が私に、 このようなアドバイスをくださいました。 「下原司祭の考えておられる宣教方針も良いものですが、 教会による癒しの業 の重要性について触れられている部分が少ないので、 是非、 その辺りを補強してください」 と。 私は、 その方の一言で、 これまでの自らの聖職としての働きで、 いつの間にか後回しにしてきてしまった大切な事柄に気付かされました。 それは病床訪問であり、 信徒訪問です。 私を含め、 多くの聖職の方々が様々な働きの中で、 いつの間にか後回しにしてしまいがちであり、 しかし、 信徒の方々が最も聖職に求める働きの一つ。 それが病床訪問であり、 信徒訪問ではないでしょうか。
聖体と聖血、 そして、 聖油を携え、 病室に向かいます。 病室に入る瞬間が一番、 緊張します。 「病状が深刻だったら、 大変だ」、 「回復の兆しがなかったら、 どうしよう」 などと考えると病室のドアノブを握るのを少し躊躇してしまう程です。 その緊張を何とか隠しながら、 病室に入ると実に様々な表情を持った方々と出逢います。 苦しみに耐え、 不安と向き合い、 必死にこの時を過ごしている方、 快方に向かい、 一安心し、 静かな時を過ごしている方、 そして、 何にも反応できない程の状況に陥っている方など。
私は、 そのような人々の前で 「平安がこの病室にありますように」 と祈り始めます。 すると、 病室に入った時には実に様々な表情を持っていた方々が、 必ずと言っていい程、 同じ表情を見せてくれます。 それは、 目を閉じ、 聖堂の中で唱えているかのような、 静かで、 真剣な、 心から 「アーメン」 と祈る姿です。 苦しみの中でも、 不安に呑み込まれそうでも、 昏迷状態とも思える中でも、 私の耳には、 心には、 その方の 「アーメン」 という祈りが鮮明に聴こえるのです。 私は、 この時、 「アーメン」 という最も短い祈りが持つ癒しの力、 信仰の力、 神への愛を、 直接、 肌で感じ、 身が震えます。 私は、 この時、 「アーメン」 (そのようになりますように) という祈りの本質に触れることができます。
そして、 帰り道で、 いつも実感します、 「僕は聖職として、 このような働きをしたかったのだ」 と。 その満ち足りた気持ちの中で、 同時に、 こうも思います、 「その働きを後回しにしてしまっている自分自身が情けない」 と。
聖職とは、 人々の 「アーメン」 という祈りをひとつ一つ集め、 神に届ける使命を持っていると思います。 聖職は、 人々が聖堂で唱える 「アーメン」 という祈りだけを集めるのではなく、 それぞれの家で、 病室で、 職場で、 施設で唱えられる 「アーメン」 という祈り、 ひとつ一つに立会い、 また、 その祈りが絶えないように導かなければならないのです。 人々が心の底から 「アーメン」 と祈る時、 聖職は、 共にいて、 その 「アーメン」 を見過ごしてはならないのです。
司祭 ヨセフ 下原 太介
(岐阜聖パウロ教会牧師)