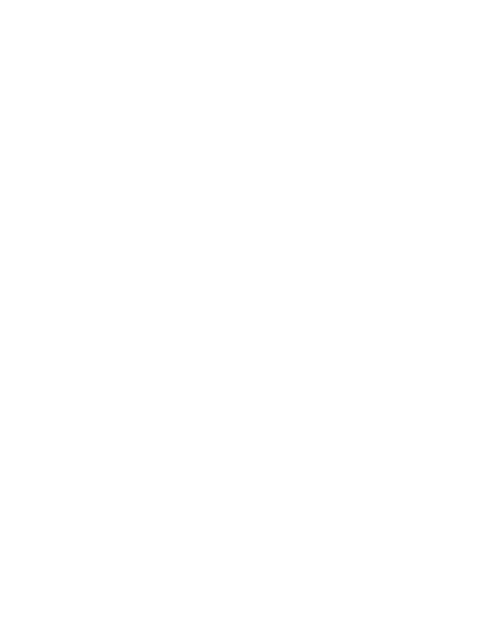去る2月11日の主教按手式・就任式に際しましては皆様方のご臨席、 お祈り、 ご協力、 本当にありがとうございました。 主教按手式はわたしの個人的な出来事ではなく、 極めて教区的な事柄であると思いますので、 個人的にありがとうございますとお礼を申し上げることではないのかもしれませんが、 按手式のために様々な準備をしてくださいましたことにつきまして改めて教区主教として皆様に御礼申し上げたいと思います。 また、 これまで管理主教をお引き受けくださった大西修主教様に、 そして11年余りに渡ります森紀旦主教様のお働きにそれぞれ感謝申し上げます。 森主教様には健康に留意され、 これからもお元気にお過ごしいただきたいと願っています。
わたしが按手を受けるについて、 皆様から 「おめでとうございます」 と言っていただきましたが、 わたし個人が主教に按手されることなど極めて小さな取るに足らないことで、 決しておめでたいことではないのですが、 問題はこれからいかにその主教職を遂行していけるのかだと思っています。 マリアさんは受胎告知の時、 天使から 「おめでとう、 恵まれた方」 と言われました。 その 「おめでとう」 の意味は、 これからマリアさんがイエス様と共にイエス様の負われた苦難を共に担うという意味でもありました。 わたしも皆様からの 「おめでとうございます」 をそのように理解したいと思います。
主教按手式の試問で、 わたしは「神の助けによって」 「聖霊の力によって」 「キリストのみ名によって」 「神の愛に基づいて」 「神の恵みによって」、 この務めを行いますと答えました。 主教職は自分が自分の力で行うものではなく、 常に神様の御助けによって行われるものなのです。 同時に、 信徒と教役者の方々が共に担ってくださるものでもあります。 そのように考えますと少し肩の力が抜けます。 神様の助けによって、 中部教区のすべての皆様と共に宣教のみ業に邁進してまいりたいと思います。
イエス様はご自分の受難の前に、 ペテロがイエス様を裏切ることをご承知の上で、 「わたしはあなたのために、 信仰がなくならないように祈った。」 と言われました。 ペテロはいつもイエス様を誤解したり、 失敗をしてイエス様に叱られています。 (もっともそれは彼が弟子を代表してという意味でしょうが。) それでもイエス様はペテロ (弟子たち) を最後まで愛し抜かれました。 最後の最後までペテロのために祈られました。 わたしがペテロという教名をいただいたのは、 自分自身が人間的には欠けたところだらけですが、 それでもイエス様は愛していてくださることの素晴らしさをペテロの姿に見たからでした。
イエス様はいつもわたしたちのために祈っていてくださいます。 いつもわたしたちを愛していてくださいます。 そのイエス様を見つめながらこれからご一緒にイエス様に従ってまいりましょう。
主教 ペテロ 渋澤 一郎