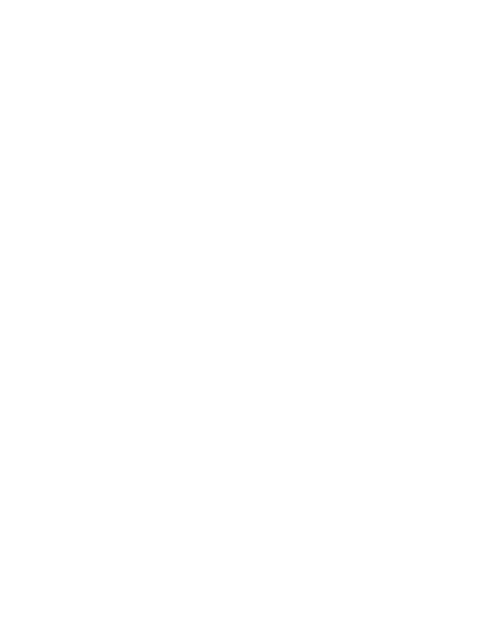「わたしはあなたのために、 信仰が無くならないように祈った。」 (ルカ22・32)
福音書を見ますとイエス様は非常にしばしば祈っておられることがわかります。 洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時も祈っておられました。 大勢の群衆が押し寄せてきた時にも、 イエス様は人里離れたところに退いて祈っておられました。 十二使徒を選ばれる時にも夜を徹して祈られました。 5つのパンと2匹の魚で5000人以上もの人々を満腹させられた時も神様に賛美の祈りを唱えてからそうされました。
ご自分の受難予告を最初にされる直前にもイエス様は一人で祈っておられました。
イエス様のお姿が変わったのは祈るために山に登った時でした。 主の祈りを弟子たちに教える前にもイエス様は祈っておられました。 また、 気を落とさず絶えず祈ることも教えておられます。
そして、 最後の晩餐の時には感謝の祈りを唱えてからパンとぶどう酒を弟子たちに与えられました。 そして、 いよいよご自分が逮捕される直前には汗が地に滴り落ちるほど祈られました。
このように見てきますとイエス様のご生涯は祈りによって導かれていることがよく分かります。 神様のご意志を生きるためには祈ることによって絶えず神様との交わりを保ち続けることが不可欠だったのです。
そのような祈りの中にあって冒頭に挙げたみ言葉はイエス様がペトロのために祈ったという内容のみ言葉です。 イエス様が特定の誰かのために祈ったというのはこの箇所だけではないでしょうか。 時間的には最後の晩餐とイエス様の逮捕の間であり、 ペトロがイエス様を否認する前のことです。 ペトロという人物は福音書においては人間としての弱さや欠点、 過ちが何の覆いもなく表されている存在として描かれています。 実際そういう人物でもあったのでしょう。 あるいは弟子たちの代表という意味でそのように描かれているのかもしれません。
いずれにしても、 イエス様は、 強がりは言っているが、 間もなくイエス様を知らないと言って逃げ出してしまうペトロのために、 彼の信仰が無くならないように祈られたと言われるのです。 ご自分が間もなく捕らえられ十字架に付けられようという緊迫した状況の中で、 このどうしようもないが、 しかし愛すべき弟子のために祈ったと言われる時、 そこにペトロも含めた弟子たちへのイエス様の限りない愛を見る思いがします。
イエス様のご復活の後、 ペトロを中心とした弟子たちが大胆にイエス様を宣べ伝えて行くことが出来たのも、 このイエス様の愛と祈りに支えられたからに他なりません。
イエス様はわたしたちの信仰が無くならないように祈っていてくださいます。 イエス様の祈りがあるからわたしたちは信仰生活が続けられることを覚えましょう。 イエス様の祈りがペトロが逃げ出さないようにという祈りではなかったことに注意しましょう。 イエス様は 「逃げ出す」 という人間の弱さを良くご存知です。 それでも信仰が無くならないようにと祈ってくださるのがイエス様の祈りであり愛なのです。 その祈りにわたしたちは生かされているのです。
司祭 ペテロ 渋澤 一郎
(名古屋聖マルコ教会牧師)
メッセージ
教区報「ともしび」に毎号掲載されている、巻頭メッセージをご覧ください。
『復活のイエスの招き』
主イエス様のご復活を心からお祝い申し上げます。
「弟子たちはだれも、『あなたはどなたですか』と問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである」
ヨハネによる福音書21章の冒頭にある物語中の一節である。
ヨハネ福音書は20章できれいに終了している。「本書の目的」をもってきちんと閉じられている。その後何らかの理由で編集者により21章が付け加えられたのである。わたしはこの21章が好きである。お好きな方も多いと思う。21章の中の1節-14節も好きである(目を通していただきたい)。この物語に流れる雰囲気がとてもいい。20章までにペトロにイエスが現れたと言う物語が無いので21章が付加されたのかどうかわからないが、21章全体がシモン・ペトロに関する物語となっている。
まだ復活に出会っていないペトロを初めとする数名の弟子たちが十字架の大騒乱のあとふるさとに戻り、少々疲労気味の中で、慣れた「漁」に夜行くのも自然である。「何もとれなかった」(3節)と記されている。4節の夜明けも象徴的だ。その時刻にイエスは岸に立っておられ、静かに彼らの言動を見ておられたとある。イエスの言葉に従って綱を打つと、引き上げることが出来ないほどの大漁という仰天すべき出来事が起こる―ルカ福音書5章1節以下に関係があるか? イエスの愛しておられた弟子が、主であることを告げると、裸同然だったペトロが上着をまとって湖に飛び込んだという描写、彼の人物、性急で、ユーモラスな性格を見、わたしたちは思わず微笑む。
わたしはこの物語の弟子たち全体の言動の静けさと、心の中のしみじみとしたはちきれるほどの喜びを感じ、描写のうまさに感心する。黙っていても成り立っているイエスと弟子たちとの以前からの関係、しかもあの十字架事件による狼狽と何と復活されたイエス。そこにはイエスに「あなたはどなたですか」と問う必要もなく、弟子たちに「十字架の時は大変だったね」と裏切りを口にする必要もない両者。すべてイエスに見通されており、しかもイエスの赦しが感じられ、責められることもない。焼いた魚を真中に、イエスと気恥ずかしい弟子たち。謝ることも無く以前の関係と同様の関係に甘えられるうれしい気持ち。
暖かい目で見通されている弟子たち。これはイエスとわたしたちの今の状況であろう。わたしたちは分かられている。知られている。個人的に、また社会の中で、世界の中で、わたしたちはみ心にかなう生き方をしようとしながら、主イエスをしばしば裏切ってしまう。40日間の大斎節をともに歩みながら、そのことを切実に感じてきた。しかし大斎節は復活日で終わりとなる。いかなる、み心にかなわない状況にあろうとも、イエスは変わることなく、咎めることなく、「さあ、来て、朝の食事をしなさい」(12節)と手を広げて招いてくださる。わたしたちは分かられている。うれしいことである。
聖餐式は復活のイエスが弟子たちとなさった食事の記念でもある。心から復活日の聖餐式をささげよう。
主教 フランシス 森 紀旦
『マリア・ワルトルタ』
わたくしは、マリア・ワルトルタが書いたイエス様についての書物を知ると、人生は3倍豊かに成る、と勝手に思っています。
『マグダラのマリア』 あかし書房からの抜粋で、マリア・ワルトルタをご紹介します。
1896年、南イタリアのカゼタで、愛情あふれる父と、きびしく変わった気質の母親のもとに生まれる。母の干渉で結婚話が2回とも実らず、愛することなしに生きることが考えられなかった彼女は人間の愛情のはかなさを知って、最大の愛である神に至ることになる。
1917年、第一次世界大戦時にボランティアで看護婦になり、フィレンツェの軍病院で 「下級」 兵士の世話をして献身的に働いた。
1920年、突然、後からついてきた子供に、ベッドからとった鉄棒で力いっぱい背中を打たれるという事件に遭い、それから心身ともに苦しむこととなる。1934年からはもうベッドから起きることはなく、死ぬまでの28年間、病人生活を送る。
病床の間、「神と人なるキリストのポエム」 という、ノート1万5千ページにもわたる原稿を何の推敲もなく、わずか数年の間にしたためる。
この著作について、彼女は 「天から与えられたヴィジョン」 によるものであって、自分は神の手の 「ペン」 または 「道具」 と言い続けた。
1961年、65歳でこの世を去る。
彼女の著作では、イエス様の生涯、すなわち聖書の福音書が映像のようにあざやかによみがえり、人物が語り、現代人に改めて生き生きとした福音を聞かせてくれる。その仕事は自然的に説明できないものであるともいわれる。
「素晴しい本」、「最高の輝き」、「美しい奇跡の本」、「全人類が読むべき本」 とあらゆる賛辞が寄せられる10冊の本はわたくしの宝です。
マリア・ワルトルタ描くイエス様は長身、ブロンド、空色と言うか、サファイア色の瞳、声はバリトン…と詳しく、白や水色の着物などのファッションも細かいので、目の前3メートルにイエス様がいるかのようです。ペトロ、聖母マリアに詳しいだけでなく、イスカリオテのユダが生き生きと描かれます。
神様のお名前はヤーヴェと発音され、マグダラのマリアはマルタとマリアのマリアだとか。一部をご紹介しましょう。
「露の最も小さい一滴にも、その存在のよい理由がある。最も小さい、うるさい昆虫の一匹にも存在するよい理由がある…神経をいらだたせて衰弱させ、この世での一日を苦しくする様々の疑問に打ち勝つための秘訣は、神が知恵深く、または、あるよい理由のために全てを行うと信じ、神が行っていることすべて、人を苦しめるための愚かな目的のためではなく、愛のためであると信じることである」 読むだけで恵まれます。感謝
司祭 ビンセント 高澤 登
(飯田聖アンデレ教会協力牧師)
『新春に思う』
新しき年をお与えくださった神様に、 心から感謝するとともに、 皆様に新年のご挨拶を申し上げます。
しかし早いもので、 ついこの間世紀を迎えたばかりだというのに、 もう3年目を迎えたわけです。
思うに世紀の後半から世界のあらゆるもの、 すべての速度が速くなってきたように感じます。 歴史に加速度がついてきたのでしょうか。
そのため社会の動きも個人の動きも、 地球規模の同時代性をもつようになってきたといってもいいでしょうか。
毎日のテレビで、 刻々と世界中の出来事が伝えられるのを見ると、 私たちもいつの間にか世界的規模の観点で見るようになってきました。
航空技術や、 テレコミュニケーションによる通信の瞬時化によって、 私たちはときどき地理的距離という考えを忘れてしまうほどです。
こうした時代の大きな変化に教会はどう対応していけばいいのか。 そして、 私たちの信仰生活はどうあるべきなのかが、 今問われているように思われます。
教会は何となく平穏で安心感のある所、 神様に守られている方船、 その方船の中に安住する私たちというイメージがあります。
しかし現実はそんなに甘くはないのです。 教会もまた社会の大きな変化の中で危機的状況が見え隠れしているのを感じます。
「イエスは言われた。 『正しい答えだ。 それを実行しなさい。 そうすれば命が得られる』 しかし、 彼は自分を正当化しようとして、 『では、 わたしの隣人とはだれですか』」 (ルカ10・28―29)
今私たち聖職・信徒一人一人が、 イエス様から 「実行しなさい」 と言われたら、 同じように 「では、 わたしの隣人とはだれですか」 と問いかけるかも知れません。
新潟では昨年から 「拉致」 事件が大きな社会問題となっています。 国際的事件であるためにマスコミでも大きく取り上げられ、 各行政を中心に被害者への支援の輪が広がっています。 私たちも両国間での早期解決を強く望んでいます。 しかしこのように国際問題として取り上げられ、 政治的に社会的に支援されるのは特殊な事件だからです。
こと国内でしかも身近な所で、 日常頻繁に起きている 「犯罪被害者」 に対しては、 国も社会も、 支援が遅れているのが現状です。
私も数年前から被害者支援に携わっていますが、 今や教会内においても被害に苦しむ信徒や家族が少なくありません。 したがって教会もこれら被害者の支援活動を積極的に行う必要があります。 その被害者の支援には経済的、 法律的支援とともに大事な精神的支援があり、 しかも被害者が自立するまで、 専門家を中心に大勢の協力者が必要です。
今年も更に変化の激しいそして加速の度を増す社会になることでしょう。 その中で危険と隣り合わせで生きている私たちは、 日常生活の中で起きる様々な精神的身体的な悩みや苦しみを、 教会という共同体の中でこそ解決していけるように努力していきたいものです。 一人が苦しめばともに苦しむ共同体として、 私たち一人一人がもっと深く、 確かな交わりを築いていくならば、 危機的状況は必ず克服することが出来る。 ただ、 「実行しなさい」 と言われた主のみことばが心に響く新春です。
司祭 ヨシュア 鈴木 光信
(新潟聖パウロ教会牧師)
『受けるより与える方が幸い』
クリスマスはキリスト教の大切なお祝いですが、今では日本の子供たちに人気のある行事になり、季語としても定着しています。復活日は初代教会の時から守られていましたが、クリスマスが祝われる様になったのは、4世紀頃からと言われています。初代教会の人達は復活された主イエスと共に生きる喜びがあり、主イエスの誕生日を正確に知って、祝う必要性を感じなかったのだと思います。100年程前までは日本でも子供の誕生日を祝う習慣がなく、社会的地位の高い家庭の男の子だけの行事だったようです。日本のどこの家庭でも子供の誕生日を盛大に祝うようになったのは50年程前からで、戸籍制度や男女平等の意識が確立され、経済的余裕ができたこととも関係があります。
福音書はイエス様の誕生についてそれぞれ違った書き方をしています。マタイの福音書では 「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、『神は我々と共におられる』という意味である」(1・23)と旧約聖書との関連を記していますが、マルコの福音書は全く触れていません。ルカの福音書は 「マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで飼い葉桶に寝かせた」(2・6、7)と文学的に記し、ヨハネの福音書は「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」(1・14)と神学的に記しています。クリスマスは平和の主が私達の中に来られ、共におられることを感謝する、信仰的に大切な意味のある日であることが分かります。
20年程前、主イエスが生まれた町ベツレヘムを聖地旅行で訪れました。周辺の殆どの人達がイスラム教徒で、主イエスが生まれた家畜小屋の跡と言われる所は聖誕教会のドームの中央に保存されていました。現状では歴史を想起するのは難しく、むしろ主イエスはどこにでもおられるとの気持ちを強く持って帰りました。
私が生まれ育った新潟県の高田は雪が多く、クリスマス頃になると地面にも、木々にも雪が降り積もって、町全体が白く、音さえも飲み込んでしまう静かな町でした。私のクリスマスのイメージと言えば、カナダのクリスマスカードの絵そのままに、サンタさんがそりに乗ってプレゼントを運んで来ることを現実のこととして受け止めることができました。当時は衣食住が貧弱で除雪作業に苦労しましたが、サンタさんからプレゼントを貰うと、そのご苦労が良く分かり、心から感謝することができました。
現在は豊かになり過ぎて、サンタさんがプレゼントを選ぶのにも悩むようです。どんどん便利で面白くて新しい物がはんらんし、子供が家庭でお手伝いをすることもなくなり、余程のことがないと喜んだり、感謝することさえありません。以前、ある日曜学校のクリスマスでプレゼントをもらった子供が 「何だこんな物か」と、投げ捨てて帰ったのを見て心が痛みました。主イエスは「受けるより与える方が幸いです」と教えています。この言葉をサンタさんの姿の中に見出して、一人一人がサンタさんになって、今、一番プレゼントを必要とし、喜ぶ人のことを思い出して、受ける喜びを、与える喜びに変えて欲しいと思います。
司祭 パウロ 塚田 道生
(一宮聖光教会牧師)
『A・C・ショー宣教師の足跡に学ぶ ―ショー祭に事寄せて―』
私たちの長野伝道区には、明治時代に活躍された聖公会の宣教師を讃える祭りが二つもある、というのは珍しい思いがします。その一つは毎年6月に上高地で行われるウェストン祭であり、もう一つが、毎年8月1日に当礼拝堂と境内地で町民祭として行われるショー祭です。もっともこちらは最近に始まったばかりで今年で3回目ですが、これは10年前に軽井沢在住の有志が始めた別荘建築等の調査保存の運動から、それらを生み出す根元となったショー師の存在と精神こそ軽井沢町の精神であることが再確認され、感謝と将来への指標として行われるようになった祭典です。
アレクサンダー・クロフト・ショー司祭は1873(明治6)年にSPG(英国聖公会福音宣布協会)の宣教師として来日し、在日英国公使の助言もあって三田の大松寺という寺に居住して日本語を学びつつ日本の文化・伝統・宗教への理解を求めて行きました。それは当時のSPGの宣教方針でもあったようです。更に師はこの時期に福沢諭吉氏と出会い終生の深い交わりを持ったこと、慶應義塾で倫理(実は聖書)を教えつつ向学心に燃えた学生たちと親しく膝を交えたこと、更に英国公使館付牧師として在日欧米人のため、また当時海外列強から不当に扱われていた日本の地位確立のために大きな貢献をしたこと等、実に幅の広い優れた宣教者であったことを知るのです。
1879(明治12)年、ショー師は芝栄町に聖アンデレ教会を創立しその後の働きの拠点としました。ここでも師は、日本の伝道は日本人によって為されるべきだと、若く優れた聖職の育成に力を注ぎ、日本聖公会の指導者たちを生み出したのでした。また彼等と共に東日本地区の責任者として各地に伝道の足を伸ばし、現在の中部教区の基礎を築いたのです。師は高潔な性格の人で自分の業績を公にするような人ではなかったのですが、師の創り上げた基礎は非常に確固たるもので、その働きの結果は今日でも日本聖公会の伝統の一部となっています。
1885(明治18)年、ショー師は伝道の旅の途次に軽井沢を通り過ぎたことが避暑地軽井沢開発の発端となりました。その翌年から夏の休暇にはここで家族と共に過ごし、多くの人々にこの地の素晴らしさを伝えると共に村人達との交流を深め、自然と共に生きる喜び、人種階級を超えた自由で平等な交わりという今日の軽井沢の精神を遺されました。そのことが今日、ショー祭という祝典として今年も200名を越える人々が集まる祭りとなったのです。今年は師逝去100年記念の年、その遺徳は礼拝堂と共にいつまでも語り伝えられ、神の御業を讃美する声となることでしょう。青山霊園に眠る師の墓標には「主はわたしを光に導かれ、わたしは主の恵みの御業を見る」(ミカ7・9)と刻まれています。正に師の生涯にふさわしい聖句です。
司祭 ミカエル 村岡 明
(軽井沢ショー記念礼拝堂嘱託)
『カード訪問』
牧会の基本が「訪問」にあることは言うまでもない。イエス様がその人を訪ねている。聖職者(教会)はそれを目に見える形で表現しなければならない。
しかし訪問が得意な場合はよいが、人にはそれぞれ得て不得手があるものだから、教役者だからといって簡単にできるものではない。私もいわゆるマメな性格ではないので、神学生の境から、卒業後いかに訪問するべきか困っていた。
2年生のときの夏期勤務でそれが解消した。大宮聖愛教会の斎藤茂樹司祭(後の主教)のところで勤務となった。同司祭と朝夕、礼拝をささげ、様々な仕事をやったが、その中に同師の訪問のやり方があり、それが私のその後の牧会のあり方を決めたのである。
斎藤司祭は古ぼけた1冊のノートを見せ、説明してくれた。それは最初の頁が1月1日、次の貢が1月2日、というふうで、366日ある。各頁は誕生・洗礼・堅信・結婚・逝去に分かれていて、1月1日にいずれかの記念日がある人の名が書き込まれている。2日以降もそうなっている。これだけ作るのは教籍簿を見れば簡単なことだが、問題はこのノートの使い方である。
同教会では中部教区の諸教会と同様、主日聖餐式でその週に記念日を迎える人のためお祈りしていた。同師は、誕生.洗礼・堅信・結婚・逝去を迎える人―逝去者の場合は関係者―あての5種類のカードを予め1年分作っていた。
私も始めた。訪問する動機ができるし、手渡して記念日のことを中心に話もできる。そして次の家へ。不在の時は郵便受けへ。カードには簡潔に「洗礼記念[○月〇日]おめでとうございます。次の主日の礼拝(○月○日)でお祈りいたします。ご出席ください。19△△年前橋聖マッテア教会」と印刷。「年に3回必ずその人を訪問できるよ」と斎藤司祭に言われたことを思い出す。
この方法はどの教会に行っても本当に助かった。訪問する方は「会える」、される方は「礼拝に出るよう勧められる」(カードの言葉だけで)。大体一週間に10枚くらい。地図で家を調べ、自転車で一回りしてくる。前橋は県庁所在地で広かった。雨や雪のときは市街地の人だけで、後は郵送となる。「郵送ぐせ」がつくとこの方法は意味がない。市外の人たちの場合は主としてバスであった。
あるときバスに乗り、教会に来ていない一人の男性(60代?)を訪ねた。挨拶しても黙って盆栽に水をやっている。「○○記念、おめでとうございます」。振り向きもしない。「持ってきたカードをここにおいていきますね」。バスに乗って帰ってきた。10数年後その人が教会で活躍していることを、転勤先の教会で知った。
家が分からない人の場合は勤め先の会社に持参した。「イラッシャイマセ」 と言ってくれる受付の女性に告げる。あわてて降りてきたその人は必ず次の主日礼拝に出た。会社訪問はよくした。
人数は増え、皆で宣教について考えた。教会の感謝献金もものすごく上がった。ささげた人の名を月報に載せるから、多い人はわずかずつでも5回おささげしていた。
訪問できないことがはっきりしている場合、信徒さんが礼拝の帰りに寄って渡してくれるよう頼んだ。それだけでも人と人との触れ合いがある。
最近よく思い出すことを取りとめもなく書いてみた。
継続は力である。
主教 フランシス 森 紀旦
『8月に思うこと』
8月は、長崎、広島への原爆の投下、そして57回目の終戦記念日を迎え、平和への決意を新たにする月でもあります。
しかし、その決意に逆行する政治状況、あるいは日本国憲法の平和主義に挑戦する復古主義的軍事大国意識が見え隠れしています。そのことは、戦争への厳しい批判を曖昧にした戦争責任意識、独善と甘えの構造と無関係ではないと思う。
敗戦後57年間、四方を海に囲まれ、外敵の侵入機会の比較的少ない島国であるため、平和に経済的繁栄を謳歌する一方、憲法が国民に保障する財産権、平和的生存権などの基本的人権、地方自治が脅かされている沖縄の現実を直視しなければならないと思う。巨大な米軍基地からの出撃により、自らの意に反して他国民を死傷せしめる加害者となっている現状。あるいは、広大な基地と水域、空域が、米軍の管轄下におかれている結果、沖縄の自立的発展に必要な産業の育成を困難にし、県民一人当たりの所得は全国平均の約74%、東京都民の半分以下で全国最下位、さらに失業率は全国平均の2倍である。
日本国憲法の平和主義に関し、1948年2月7日、文部省発行の中学1年生向けの「あたらしい憲法のはなし」、特に「戦争の放棄」の項では、「兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのいっさいのものはもたない」ことを意味するとし、さらに以下のように明言しています。「しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの国よりさきに行なったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません」と書かれています。
憲法の平和主義、とりわけ第九条の条章が、日米安保条約と自衛隊が40年以上に及ぶ「既成事実」としてもはや動かし難い重い存在となったかに見える今日、これにどう対処すべきかば、我々にとってきわめて重要な問題である。それは単純な「否」、という対応だけでは、余りに抽象的・非現実的・非生産的だからである。とすれば、憲法の平和主義の原点に立ち返って、これを積極的、創造的に再構築する方途を検討すべきであると思う。
「彼らは剣を打ち直して鋤とし 槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず もはや戦うことを学ばない。」(イザ2・4、ミカ4・3) この言葉は、日本国憲法第九条、及び平和主義の思想と同じである。巨大な国家に挟まれたパレスチナで、イザヤとミカが語った深化するに足る価値を内在した高い理念である。我々は、預言者が神の啓示を受けて語ったこの理想が、この地上に実現するために祈り、労する「平和を実現する人々」(マタ5・9)となるようにと召されているのである。
「剣をさやに納めなさい。剣をとる者は皆、剣で滅びる」(マタ26・52) と主イエスは弟子達を諭して、自ら十字架の死の道を選ばれました。我々は、主イエスの自己犠牲と献身の御足をたどることによって平和を実現する道が開かれるのではないだろうか。
司祭 テモテ 島田公博
(飯山復活教会勤務)
『新たに生まれなければ…』
「どうすれば、古びた教会が、新しい生命に満ちあふれて生まれ変るのだろうか」。何とか手を打たなければ、このままでは教会は沈没してしまうとする危機感は今に始まったことではない。
3人寄れば、教会、伝道区、教区そして管区の現状を憂い、(文殊の知恵を合わせて)教会を活性化するための論議を重ね、色々な方策を(小泉総理の構造改革にも負けずに)次々に編み出してきているが、今もって決定的な処方箋を入手できたためしはない(独断と偏見によれば)。
そこで思いつくのが、主イエスを夜陰に乗じて訪ねた、ファリサイ派の論客の一人、ニコデモが発した「年をとった者が、どうして生まれることができましょうか」という質問だ(ヨハ3・4)。
ニコデモは開口一番、「あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています」と低姿勢で相手にせまり、色々な角度から議論をしかけて、何とか言質を取ろうとする。しかし、主イエスは、ただ、言葉少なに「人は、新たに生まれなければ、神の国を見ることばできない」と語られた。
そして「年をとった者が、どうして生まれることができましょうか」となお食い下がるニコデモに、主は「肉から生まれたものは肉、…霊から生まれたものは霊である」と答えられるのであった。
ニコデモは、当時の社会では指折りの論客だったし、色々な情報を手にすることができた人物に違いない。しかし、主イエスを表面的にしか理解しておらず、人格的にではなく、知的にしかとらえきれず、「あなたは…こんなことが分からないのか」(ヨハ3・10)とイエローカードをもらってしまう。
変革を求めて、話し合いに徹し、会議に会議を重ね、又、さまざまな情報や統計、資料などを持ち出してきている私たちだが、ニコデモがそうだったように、表面に現れた事象だけにとらわれ、その背後にあるもの、あるいはその対局にあるものを注視することをしないと、肝心なものを見失ってしまい、どうして、なぜという深い泥沼に落ち込んでしまう。
「なぜ、どうすれば」と今もなお教会の再生を求めて問い続ける私たちに、表面的な、自然の道理、人間的な考えだけに目を奪われることをしないで、それらを越えた反対側に勇気をもって立ち、今一度、見直してみてはと、主は今も語られているのではないか。
時には奇跡という形を用いてでも、自然の成り行きや常識を超えて働いておられる神をもっと素直に信じ、もっと謙虚に神に聞き、もっと大胆に、そのみ心に従って歩むことができれば、古びた教会の再生も意外なところから実現していくのではないだろうか。
司祭 ルカ 森田 日出吉
(高田降臨教会・直江津聖上智教会牧師)
『水がめをそこに置いて』
今年は例年にない暖かさで、桜が終わらぬうちに、桃の花も満開、濃いピンクの花が桃畑に色鮮やかです。
五月末には「レンガの聖堂チャリティーバザー」が、地域との交流と、信徒が力を合わせて一つになる場として行われます。でも、最近のフリーマーケットやデフレの影響でしょうか、バザー状況も変わってきて、中古衣料品など、商品として充分な評価をされなくなる傾向にあるようです。粗大ゴミの日など、色んなゴミ(?不用品)が運び出されてきます。充分お役目を果たした物、まだまだ使えるのにと思う物等が運び込まれてきます。不用品といえども使い古された物がリニューアルされてまた新たな道が与えられリサイクルしていきます。あるいは古い物であっても、アンティーク品として高く評価される物もあったりします。使う立場で物を見た時、不用品とレッテルを貼られるその中にも、なお生かされる物が有る事を見出しているのではないかと思います。
五月になり、主のご復活から四十日目は「昇天日」、そして五十日目「五旬祭」(ペンテコステ)の日は「大いなる主日」(マグナ・ドミニカ)として記念され、この日弟子達に聖霊降臨が起こり、聖霊の力をいただいた弟子達が宣教していく群れになっていきました。この日を「聖霊降臨日」として記念します。聖霊降臨日はご復活し、上げられた主イエス様が常に私達に聖霊を注ぎつづけ、働きつづけてくださることを記念する祝日です。
ヨハネによる福音書四章にはサマリアの女性との出会いが記されています。主イエスは、ガリラヤに行かれるためにシカルというサマリアの町に着き、疲れてヤコブの井戸に座っていました。聖書はそれは正午頃だと伝えます。主イエスとの出会いは、予期せぬ出会いで、唐突でした。まさかこんな時間に井戸に人がいるとは。普通の女性だったら、朝早くから水を汲み、一日の準備を済ませ、昼食をいただく頃、この女性は井戸に来ました。むしろこの時にしか来れなかった女性でした。五人の夫と結婚と別れを体験し、夫でもない者と同居と、身持ちの悪い女、ふしだらな女と、人にも言われ、ユダヤ人からの、サマリア人からの、女性からのさげすみに会い、人目を避けて、この時間にしか来れないと自分も感じていた女性でした。せっかく主と出会い、主イエスが与えようとする『生きた水』を理解できませんでした。彼女が求める水は、皆と顔を合わせ、さげすみの目に会わずにすむ『ここに汲みに来なくてすむ』水でした。
けれど主イエス様の言葉のうちに、自らをもさげすんでいる自分を、全て受け入れてくださった方がここに居てくださる事に気が付きました。今まで気ままに生きてきた代償に、さげすみを受け止めなければならない水がめをそこに置いたまま、過去のさげすみに縛られて生きる道でなく、主イエスの救いに生きる人となり、人々にメシアたる主イエスを伝えるため、町に出かける人に変えられていきました。
人間の貧しい力だけでは神様との生きた交わりを保つ事は出来ません。私達は聖霊によってキリストにつなぎとめられ、信仰の内に生かされています。聖霊の息吹をいただき、歩んでいきましょう。信仰の先輩達が、その働きの中に聖霊の恵みをいただき歩んだように。
司祭 マルコ 箭野 眞理
(長野聖救主教会牧師)