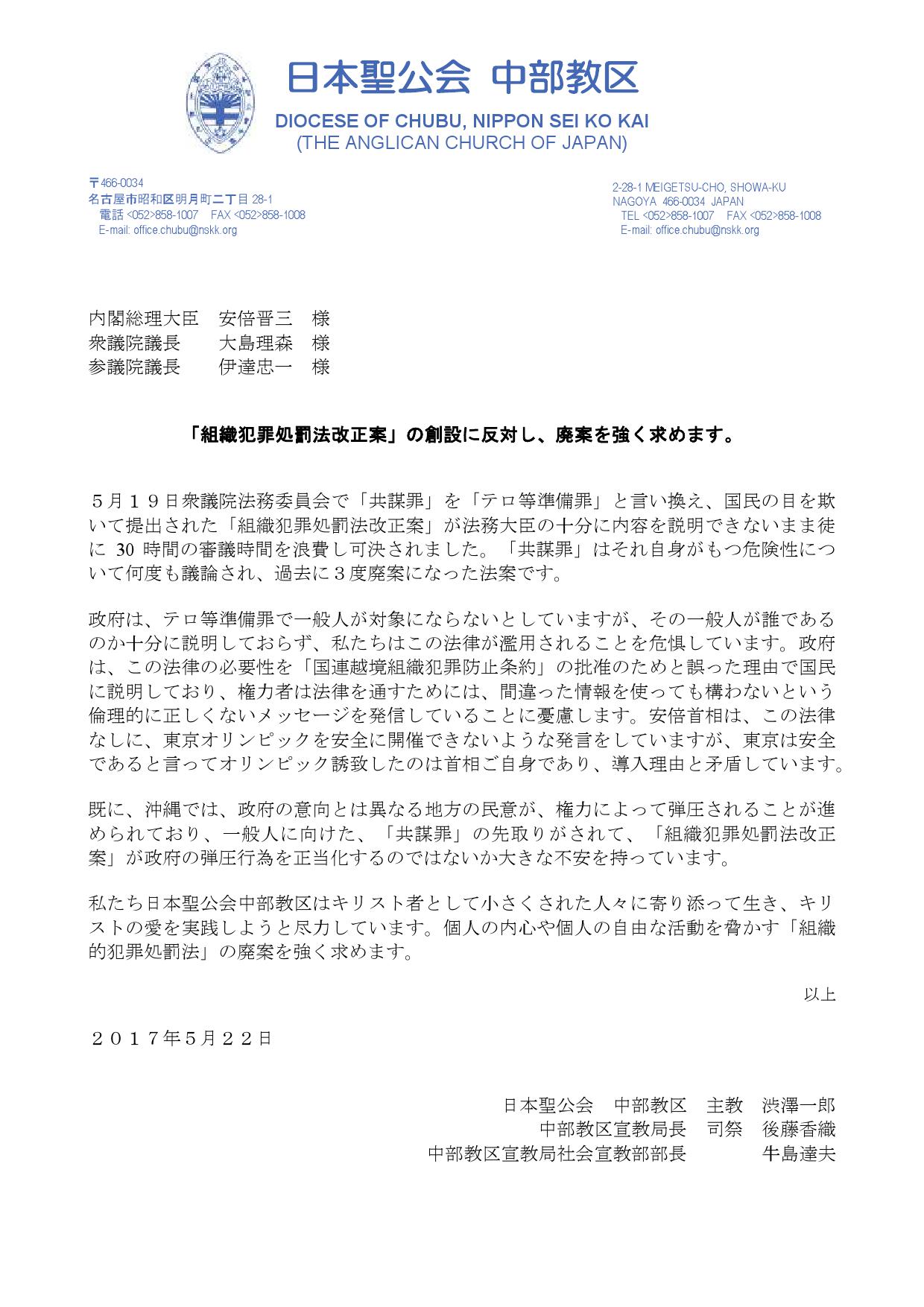「ひとみのようにわたしを守りみ翼の陰に隠してください」 『日本聖公会祈祷書』詩編第17編8節より
日々の祈りの中で、私が時折引用する詩編の一節です。とてもしなやかで、祈りに旋律と情景が生じる、本当に美しい一節です。
瑞々しく美しく澄み、柔らかく穏やかな輝きを湛え、深い慈愛と優しさをもって、常にそこに私たちを映し出してくださっている主の瞳。その主の瞳の一端にでも、主が見つめる景色の片隅にでも、自分自身が存在していると思うと、主の御守りを一層強く感じることができるのと同時に、様々な罪や悪を日々繰り返してしまう自分自身のその姿で、主の瞳を汚してはならないという自戒の念を強く抱くことができます。
美しい主の瞳は、私の信仰にとって主の象徴そのものであり、私自身の瞳も、それに似ることができれば、主の見つめる景色と同じ景色を私自身の瞳にも映すことができればという、信仰の目標そのものでもあります。
このような思いからなのか、私は聖餐式において陪餐の際、自然と信徒の方々の瞳に目がいくようになり、そこから様々なことを感じ、また学んできました。
深い黙想の中、平安と静寂を湛え、伏し目がちに頭を垂れる方。式中に聴いたみ言葉を噛み締めながら、新たなる信仰の気づきに喜び、感謝し、自分の掌にある御体を仰視する方。自らの罪を省み、悔い、贖罪と救いを求めているかのように意味深く、神妙に自らの組んだ手を静視している方。信仰者としての自らの成長の糧を求め、真摯に主と向き合いながらも、親鳥が雛を両翼で包み込むように、その両腕に幼子を擁き、常に優しい眼差しを向けながら、主による御加護と祝福、また命の糧がその子に与えられるようにと祈る方。そして、その方の両腕に擁かれながら、安らかに眠りについている幼子。
信徒の方々のこのような姿、そして、瞳、眼差しを陪餐の際、間近で見つめながら、折々に主がこれらの方々とどのような関わりを持たれているのかを知り、信徒の方々の瞳を通して御姿を顕される主を垣間見ることができています。
それらの瞳の中で、近年、最も印象的なものが子どもたちの瞳です。毎主日、約2~5歳の子どもたち数人が聖餐式に参列し、陪餐の際、至聖所まで来て、母親の隣で跪き、私から祝福を受けます。その際、子どもたちは前述の信徒の方々とは全く異なる瞳を、私に見せてくれます。それは、もしかしたら私たちが年齢的成熟、そして、信仰的成熟を積み重ねていく中で、失ってきたものかもしれません。
子どもたちは、至聖所で信徒の方々に分餐するために右へ左へ移動する私の姿を、いつも目で追い続け、祝福の際、自分の目の前に立ち、頭に手を置く私を、また、自分の母親が陪餐に与る際、その姿と御体と御血を、目を力強く見開いて見上げています。私は、いつも、その瞳に圧倒されてしまいます。
なぜなら、創造主が私たち人間に吹き込んでくださった純粋で、力漲る生命力本来の爛々とした輝きが、また、神の存在を決して疑うことなく、その存在により近づこうとする真っ直ぐな探求心が、そして、何よりも、神の神秘をその時、誰よりも知り、感じている証しが、そこにはあるからです。
私は、その瞳を見て、直感的に〝主に一番近い存在が持つ力〟、〝神の神秘の中を生きる存在の尊さ〟を感じ、威厳さえ覚え、主の臨在を感じます。
子どもたちの瞳には、主が宿っている。祝福の際、子どもたちの目の前に立つ私自身が、子どもたちの瞳に、そして、その中に宿る主の瞳に、どのように映っているのか…。いつも、私自身の在り方が問われているようです。
(上田聖ミカエル及諸天使教会牧師・福島教会管理牧師・聖ミカエル保育園園長)
未分類
くるみの木のこと
教区内の幼稚園・保育園がだんだんと認定こども園に移行しつつあります。既に三条、直江津がこども園化され、この4月からは松本、稲荷山も幼保連携型認定こども園に移行しました。それぞれの園が子どもたちへの教育と保育、そして子育て支援に今まで以上に努められますよう願っています。
先日、稲荷山で開園記念式典がありましたが、稲荷山幼稚園は幼保連携型認定こども園「稲荷山くるみこども園」という名称に変わりました。なぜ「くるみ」なのか平部延幸園長が説明しておられました。かつて稲荷山の教会にはたくさんのくるみの木があり、戦前戦後を通じて教会や幼稚園の財政を支えてきたそうです。今はなくなってしまいましたが、そのことを忘れないために「くるみこども園」と名付けたそうです。
そう言われてみますと、長野県の多くの教会には確かにかつて大きなくるみの木がたくさんあったように記憶しています。推測ですが、その背景には教区最初期の宣教師の一人であり、長野の教会で長く牧会されたウォーラー司祭がくるみの木を植えることを奨励したためではないかと思われます。
長野聖救主教会発行の「ウォーラー司祭―その生涯と家庭」にはウォーラー館の庭のくるみを盗みに入った子どもたちが同司祭からこっぴどく叱られたこと、また、くるみは大切に乾燥させ、売却代金は教会会計に入ったことが記されています。神学生のためにも使われたと聞いています。
ですから、単純に教会の庭にくるみの木がたくさんあったということではなく、一本の木にも教会の働きに奉仕するという存在意義があったのです。くるみの木にもそのような歴史があることを稲荷山の開園式典に出席して改めて感じました。
新生礼拝堂がFEBC(キリスト教放送局)の取材を受けました。
小布施の新生礼拝堂が、FEBC(キリスト教放送局)の関連ホームページ「続・ここに立つ教会」で取材されました。教会の写真や金司祭のインタビューなどが掲載されています。ぜひご一読ください。
共謀罪反対声明
新生病院80周年記念動画
日本聖公会中部教区関連団体・特定医療法人新生病院は
2012年に80周年を迎えました。
その記念誌をもとに作られた動画が届きましたので、どうぞご覧ください。
植松主教様を偲んでもう一言
わたしも主教様の「信徒は聖霊を与えられているので何でもできる」というお言葉を良く記憶しています。主教様の信仰の確かさを表しているお言葉であり、聖霊の働きへの確固とした信頼から来るお言葉です。そして、その信頼は―これも主教様の十年間の変わらない教えでしたが―「み言葉」と「祈り」から来るものでした。聖書を読み、お祈りをする。信仰者の基本中の基本を繰り返し教えられました。そして、「クリスチャンにとって最も大事なこの二つのことがもし欠けているとしたら…これはまさに致命的です」と言っておられます。主教様はそのことをご自身の生き方をもってわたしたちに教えてくださいました。
主教様が退職されて30年。この信仰の基本は永遠に変わるものではありません。むしろ、教会に少し元気がなくなってきている今だからこそ、その基本が本当に求められていると強く感じます。わたしたちが自覚的、創造的に信仰を実践するためには「み言葉」と「祈り」を決して欠かすことはできないのです。
”神に信頼をおく”
大斎節も残り少なくなりました。主イエス様の十字架、そして、ご復活を深く黙想しつつ残りの大斎節を過ごしてまいりましょう。
わたしたちの信仰生活はいつも平穏無事というわけには残念ながら行きません。些細なことでも信仰生活を脅かす困難さは必ずあるものです。そんな時、神様は必ず良い道を備えてくださると信じていても、時には神様に弱音を吐いたり、不安になったり、愚痴を言ったり、疑ったりしてしまうのです。それがわたしたちの信仰生活の現実です。
「コリントの信徒への手紙二」の中でパウロは、福音宣教のために被った苦難があまりにも激しかったので、「生きる望みさえ失い、死の宣告を受けた思いだった」と記し、「それで、自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました」(1・9)と書いています。
パウロがそれまで神様を頼りにしていなかったわけではないでしょうが、彼のような信仰の持ち主でも想像を超えた様々な苦難に遭遇したときには死の不安に駆られてしまうのです。しかし、彼は続けて言います。「神は、これほど大きな死の危険からわたしたちを救ってくださったし、…これからも救ってくださるにちがいないと、わたしたちは神に希望をかけています」。
パウロは自分たちがいかに大きな危険に晒されてきたか、しかしそんな時でも神様はいつも救ってくださったではないか、これからも救ってくださらないはずがない、と神様への信頼を確認し、福音宣教への思いを強くしているのです。
信仰が揺らぎそうになった時こそ神様に信頼をおいて信仰生活を送ってまいりましょう。神様はどんな時でもわたしたちに最も良い道を備えてくださるのです。
ご復活の祝福をお祈りいたします。