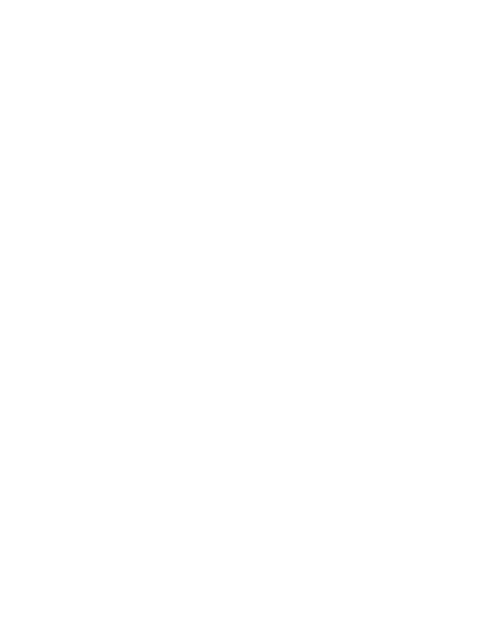イエス様は神の国のたとえで、「神の国は人が知らないうちに成長する」と言っておられます。蒔かれた種が地中でどのように成長するか人には分からないが、芽を出し、穂を実らせるように、神の国は目にも見えず、耳で聞くこともできないが間違いなく成長しているのだと言われます。神の国(神様の働き)は深く、静かに進行するということです。
先日、I教会で、あるご夫妻の洗礼・堅信がありました。奥様はそこの幼稚園出身でキリスト教には長い間、関心を持っておられましたが、ご自分の家が仏教ということもありなかなか入信にまでは踏み切れないでいました。しかし、この度、決心をされご夫妻で入信されたのです。
礼拝後の挨拶の時、「ここまで来るのに長い時間がかかりました」と言っておられました。そして人間的に見れば幼稚園の時から50年という長い時を経て洗礼へと導かれたわけですが、そこにはこのご夫婦に対して深く、長く、静かに関わってくださり、このお二人を洗礼・堅信へと導いてくださった神様の働き(神の国)があったのです。
また、最近、I司祭のお連れ合いであるSさんのお父様が洗礼を受けられました。Sさんがお父さんに、「お父さん、お父さんは洗礼を受けてクリスチャンになったんだよ」と言いましたら、お父さんが、「そうかい。でも、実感がないな」と言われたそうです。とても微笑ましい会話なのですが、実はそこにも神様の静かで確かな働きが隠されているのです。
洗礼を受けてクリスチャンにされたからといってその瞬間にそのことを実感する人はそう多くはないと思います。殊に、幼児洗礼の場合は実感も何もないでしょう。乳児には洗礼を受けているという意識すらないのですから。わたしも洗礼を受けた時、緊張したことは覚えていますが、その瞬間に人が変わり、わたしはクリスチャンになりましたという実感はありませんでした。多少の違いはあれ、皆さんそうでしょう。
では、実感がなければクリスチャンではないのかと言いましたらそんなことはないのです。神様の働きは深く、静かで確かなものです。人間の目にも見えず、耳にも聞こえず、感じることもないかもしれません。しかしわたしたちは洗礼によって間違いなく神様とイエス様に結び付けられるのです。確かにクリスチャンとされるのです。I司祭のお連れ合いのお父様は実感はないかもしれませんが間違いなくクリスチャンとされているのです。そこには人間の感覚を超えた神様の静かな働きがあります。
わたしたち人間は神様の御心をすべて知ることはできません。神様だけが知っておられて、人間に分からないことがたくさんあります。それでもいいのです。神様のことがすべて分からないということは、逆に恵みではないかとわたしは思います。もし、人間が神様のすべてを知ったらどうなるのでしょうか。考えてみると恐ろしいことです。神様が知っていてくださればそれで十分なのです。
神の国は静かに、しかし確かに成長しています。I教会のご夫妻の場合、神の国は50年間、静かに成長して来ました。I司祭のお連れ合いのお父さんはもっと長い時間がかかりました。それでも間違いなく神様の働きは深く静かに潜航し、今日の洗礼・堅信になっているのです。わたしたちはそこに神の国の成長を見るのです。
神の国は今もどこかで、いや、わたしたちのすぐ近くで静かに成長しているのです。神様は次にどんな素晴らしい神の国を見せてくださるのか、そんなことを期待しつつ送る信仰生活は何と楽しいものでしょう。
主教 ペテロ 渋澤一郎(日本聖公会中部教区主教)
メッセージ
教区報「ともしび」に毎号掲載されている、巻頭メッセージをご覧ください。
わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。
「父と子と聖霊」の三位一体の神様というのは、わかりにくいかもしれません。日本聖公会では、「聖三一」と呼ばれることもあり、中部教区では岐阜県にある可児聖三一教会はこれに由来しています。教会は、この「聖三一」の神様を教理の発展のなかで信じてきました。日本ハリストス正教会では、アンドレイ・ルブリョフが描いた、アブラハムを訪ねる三人の天使(『創世記』)に拠る聖画(下の絵)が、唯一正当な図像表現として公認されているそうです。また、聖公会神学院にもこの聖画があり、いまも黙想のときに用いられたりしていると思います。アウグスティヌスは、聖三一の関係を「言葉を出すもの」父、「言葉」子、「言葉によって伝えられる愛」聖霊という類比によって捉えました(『三位一体論』)。三者はそれぞれ独立の相をなしつつ、一体として働き、本質において同一であると考えています。これが、西方神学における三位一体理解の基礎となります。
しかし、神様が「三つであるが一つであり、一つであるが三つである」というのは、理解する対象ではなく、信じる対象としての神秘であるとも考えられています。これが現代まで守り続けているのは、「頭で理解できたこと」よりも、「体験によって感じたもの」であるからだとも思います。例えば、私たちは、よく「主の祈り」を唱えます。これは「聖三一」の神をよく表しています。「主の祈り」は、祈り方がわからない弟子たちに、イエス様が直接教えた唯一の祈りであり、イエス様も神様に向かって用いていた祈りです。子なるイエス様が、父なる神様に祈った祈り、これを、私たちのうちにある聖霊によってお祈りする、これが「主の祈り」の大切なところであると思います。
神様は私たちを無条件にまず愛していて、これがこの世界の根本だと思います。神様は私たちへの愛を示すために独り子であるイエス様をお遣わしになりました。そして、その神様から遣わされたイエス様の無条件の愛に対して私たちが「はい」と答えたとき、私たちは真に神様の子どもになれるのです。今まで眠っていた私たちのうちにある聖霊が活発に動き出していき、私たちは真に神様の子どもとなり「主の祈り」を唱えます。
確かに現実はつらい状況もありますし、試練を抱えてはいますが、イエス様から「神様はあなたのことが大好きだよ」「そのことを信じますか」と呼びかけられて、私たちのうちにある聖霊によって「はい」と答えるというのが、聖餐式の大きなよろこびであり、ここに、私たちは、「三つであるが一つであり、一つであるが三つである」神様を感じることができるのではないでしょうか。そして、私たちが、「主の祈り」を唱えるとき、私たちが一人ではないこと、「いつもあなたがたと共にいる」神様をも感じることができると思います。
石田雅嗣(松本聖十字教会牧師)
ただいま
4月より新潟聖パウロ教会へ赴任し、イースターに続いて牧師任命式が行われました。礼拝のはじめ、主教の前に信徒代表の方と共に立ち、信徒さんからの「支持します」との声に励まされました。新潟聖パウロ教会は、聖職志願をした後、神学院卒業と同時に旅立った場所です。
10年ぶりに帰ってきた夫と私を温かく迎えてくださる方々。その間に亡くなられた方々のご家族と故人を偲び語り合う思い出。10年前に教会に来られた方の中には高齢のため礼拝に出席することが困難である方々も増え、これから再会できるのが楽しみです。
教会の隅々に10年前、5年間働いた丁胤植司祭の様々な足跡が残っていて不思議な気持ちです。信徒訪問をする前に、丁司祭に聞くと10年前のノートを取り出し、信徒訪問をした時の記録を見ながら家族関係や共にしたお祈り、励ましの言葉を教えてくれます。
有志の信徒さんと話す時は、10年前の思い出話もたくさんあり、「神学院に行く前のこと」も思い出しながら話をする機会も多い中、故レア永井志保子さんが思い出されます。
新潟聖パウロ教会へ牧師として赴任した夫は、主日礼拝の準備や説教、牧会などで充実した日々を過ごしていました。「ソンちゃんは若いのに、ご両親と離れて友達も少ないから大変」といつも声を掛け気に留めてくださる方でした。名古屋にいる時は手話を学んでいたと話すと新潟の手話教室の情報を教えてくださり、教会へ訪ねて来る悩み多い若者のことで相談をすると、「夫が癌で亡くなってから病院でボランティアをしていた」時のことや「いのちの電話」相談員をしてきた時の経験を聞かせ、励ましてくださったのでした。
日本の美味しい食べ物や素敵な文化もたくさん教えてくださり、今も「麦とろご飯」、「赤カブの漬物」を食べる時は永井志保子さんを思い出します。ご自分は生まれながら片方の血管が細くて、塩分を控えて漬物を食べないのに、沢山作って教会に持ってきて分け与えてくださる姿に憧れていました。
10年間引きこもった一人の若者との出会いもあって、教会を訪ねる人々へ何か役立つことはないか探していた時、カウンセリングを学ぶことを考えていたら、夫は私が結婚前より神学を学んでみたいと語っていたこともあって、聖職志願の道を応援してくれました。
今までの10年間も色々知らないことがたくさんあり、悩む人の前で何もできず落ち込むこともたくさんありましたが、教会と病院での日々は永井志保子さんが見せてくださった姿を思いながら歩んだものでした。
夫を亡くし、母親の世話、離れて過ごす娘さんたちのこともありながら、ボランティア活動や教会の会計、教会の人々への世話など、血管が細くいつかは歩けなくなる日が来ると、書道や縫物など受けるより与えるが幸いとの生き方を教えてくださった永井志保子さんはじめ、多くの方々より頂いた愛情を心に留め、一緒に祈り、人々と交わり、共に生きる人々が神様の愛に結ばれている信仰共同体、その中の一人であることが本当にありがたいです。
永井志保子さんだけではなく、神様を愛し、愛され、結ばれている人々と共に集い、祈り、分け与えて来られた方々の仲間に入れさせて頂きたいと思います。主に感謝。
司祭 フィデス 金 善姫(新潟聖パウロ教会牧師)
「行っていらっしゃい」、「ただいま~、お帰り~」
3月末、長野県から新潟県に移りました。4月6日現在は新潟聖パウロ教会の司祭館に荷物を解き、片づけているところです。住まいは新潟で、管轄は三条聖母マリア教会・長岡聖ルカ教会、そして聖公会聖母こども園にチャプレンとして関わっています。
10年ぶりに入ってみた新潟の教会ですが、「あーそうだ。おもにこの部屋を事務室として使っていたし、ここにはあれそれが置いてあった」というような記憶がもどってきます。そして私の跡がそのまま残っているところがあって、一方では不思議感まで漂います。これから新潟の信徒さんに徐々にお会いできる機会があると思いますので、また楽しみにしています。
4月の最初の主日は三条で復活日礼拝を献げ、イエス様のお墓に向っていた婦人たちが「誰があの大きな石を転がしてくれるだろう」という話をしていたところについて説教をしました。それは単純なお喋りではなく「主よ、石の扉を開けてください。そして墓から出てきてあなたの教えていた通り自由を生きてください。そしてわたしたちもその自由を生きることができるようにしてください」という祈りではなかったのかな~という話をしました。そして普段日常の中で心を分かち合っていた信仰の仲間たちが一緒に祈ることによって力を合わせていたことを意味するということだろうとメッセージを伝えました。人間誰だって心に大きな石を抱えているはずだから、もし私が皆さんに「そこの誰か石を転がしてください」と叫ぶ時は是非耳を傾けて欲しいですし、皆さんも「そこのだれか石を転がしてください」と叫ぶ時には私も応えられる、そういう関係をつくっていけたら嬉しいと言いました。
長岡聖ルカ教会は今度の主日に行く予定ですが、樋口正昭さんと連絡を取りながら信徒さんの安否や牧師館の使用不可状況の話、そしてベストリーの屋根の修理について情報を得ています。皆さんと一緒に礼拝を献げて、長岡教会の方々が今まで手を合わせて祈ってきたことについてその悩みを分かち合うことから始まる長岡での主日を期待しています。
三条聖母マリア教会の集会室に信徒の西川愛子さんがお描きになった和画が掛けられています。広い草原に一人の少女が草場に座って、鳥かごの中から小鳥たちを出して自由に放ってあげている絵です。少女が座っている草場にはクローバーがいっぱい生えていてそのクローバーは白やピンク色のお花を咲かせて単純な緑ではなく他の種類の草も細かく描かれています。絵の中の少女の顔からは小鳥を自由に放ってあげることによる喜びの表情だけではなく、小鳥たちとの別れを寂しく思うような表情も感じられます。小鳥たちも少女から離れることに未練が残っているのか、少女の肩に座っている小鳥や少女の手のひらから離れない小鳥もいます。
しかし、もうすぐ小鳥たちは青い空に向けて飛んでいくでしょうし、少女とは別れなければなりません。長野を去る時に長野の方々が渡してくださった挨拶はサヨナラではなく、「行っていらっしゃい」でした。小鳥を放して飛ばそうとしている少女の心は、小鳥たちの旅立ちを応援するとともに名残惜しさも多くあったかと思います。その心を受けて新潟に着いた私は、主において兄弟姉妹となった新潟県の信徒の方々の心の扉の前に立って「ただいま~」と声を上げてみます。絵の中の上の部分に教会が見えますが、遠くから「お帰り~」という声が聞こえてくるような気がします。
司祭 イグナシオ 丁 胤植(三条聖母マリア教会・長岡聖ルカ教会牧師)
いのちのエネルギー
聖職に叙任されて以来、長く学校での勤務を経験してきました。一般の教会と異なり、周囲のほとんどの人がいわゆる「クリスチャン」ではない環境の中で、なるべく教会用語を用いずにキリスト教の内容を伝える、説明する、という訓練を知らず知らずに受けてきたような気がしています。これは私にとって「世界のあらゆるところに神を見出す」ということでもありました。
その中で、「復活」という概念は非常に誤解されやすいという印象を持っています。一言で言うなら、「死んだ人が生き返る」というところで終わってしまうことが多いのです。しかし、キリスト教が伝える「復活」や「復活の命」は、それと同じではありません。いろいろな方のご葬儀に際して思うことは、亡くなった方が「生き返る」ということが起こらないとしても、そこには確かに「復活の命」があるのだ、ということです。肉体に拘束される生物学的な「命」ではなく、神から与えられた「いのち」としてのわたしたちの受け止めが「復活の命」なのです。これを説明するよすがとして、「いのちのエネルギー」という言葉に、誤解を恐れずこのイメージを託してみたいと思います。
神学生時代、バングラデシュのテゼ共同体を訪問し、そこでいろいろな出会いを経験しました。特に今でも強い印象を持っているのは、ブラザー達が支援しており、現在もJOCS(日本キリスト教医療協力会)がワーカーを派遣している、障害者コミュニティセンターでのことです。
ある日、派遣ワーカーの岩本直美さんに同行して、センターに関係する子どもの家庭を訪問しました。ある男の子は重い知的障害を持っており、おそらくほとんど会話はできなかったと思います。しかし、たった一回彼の家を訪れただけの私でも、立ち去るのが悲しかったらしく、真っ裸で道に出てきてオイオイ泣いていました。今でもその姿を思い出すたびに、彼のうちに宿る「いのちのエネルギー」に励まされています。
センターでは、障害を持った女性のグループが立ち上げられたところでした。その一人の女性タフミナさんは、カレッジ在学中に婚約もしていたのですが、骨結核を発症して歩行が不自由になり、婚約も解消されて学校も中退し、引きこもりがちに過ごしていました。利用者としてセンターに関わりを持った彼女に、実はカウンセラー的な賜物があるとみた岩本さん達は、彼女をセンターのスタッフにして、この女性グループの担当者としました。先日、この女性グループを支援するための「井戸ばた基金」の案内に、グループのリーダーとしてタフミナさんのお名前を見た時、彼女の内なる「いのちのエネルギー」を認め、そして彼女をここまで支え励ましてきたスタッフの働きに、そして神さまに心から感謝しました。
「復活の命にあずかる」とは、神さまの「いのちのエネルギー」が世界のあらゆるところを満たしていること、そしてこのわたしのうちにも、神さまはその「いのちのエネルギー」を豊かに与えてくださっていることに気づき、それを信じることだ。この方々は、私にそのことを教えてくださいました。
※「井戸ばた基金」については、idobatakikin@gmail.comにお問い合わせください。
市原信太郎(東京教区出向)
父権制を再生産する共同体
この言葉は、ある洗礼堅信準備会の中で、女性差別などが教会の中に根深く横たわっていることを認識していながら、しっかりと向き合わず、「なかなか変わることが難しいんですよ」と、なあなあで済まそうとしたわたしの発言に対して投げかけられたものです。
全くその通りです。「イエスさまの語られた福音は、人々を解放するのです」と語りながら、父権制を始めとする様々なしがらみに絡め取られ、解放されずに再生産する共同体がわたしたちの教会のようです。そこから解放されている人が、わざわざ不自由な共同体に加わりたくないと感じるのは、当たり前のことです。
最初に引用したガラテヤの信徒への手紙3章28節は、初期の教会で使われていた「洗礼定式」です。初期の教会共同体がイエスさまが告げ知らせた福音を信じて生きることで、民族、身分、性別といった、人々を分け隔てる主な境界線を乗り越え、平等で包括的な信仰共同体を実現する決意がここに表現されています。
新共同訳聖書ではその違いが訳出されていないのですが、この洗礼定式の民族、身分、性別の組み合わせで、最初の2つは、「AもBもありません」という形ですが、3つめの性別は「男と女もありません」となっていて、性別に関しては単純な並列ではないことが分かります。
「男と女も」の箇所で使われているのは、「雄」「雌」というギリシャ語で、「男と女もありません」は「男・雄と女・雌」で「一対」という概念をも乗り越える姿勢を表しているのです。この洗礼定式は、様々な境界線を越えて平等な関係で共に生きようとする決意を表明し、特に性別による境界線だけでなく、「男と女で一対」という思い込みを放棄し、父権的な家庭形成から解放されることを目指していたのです。当時の父権社会の中で弱者だった女性たちにとって、結婚し、子どもを産まなければ価値がないという圧力からの解放が宣言されていたのです。
ところが、ガラテヤ書ではこの「洗礼定式」が引用されたにもかかわらず、コリントの信徒の手紙Ⅰ12章13節の引用では、「男と女も」の組み合わせは除かれてしまっています。さらに、1世紀末の擬似パウロ書簡である「テモテへの手紙一」2章15節では、
「しかし婦人は…子を産むことによって救われます」という父権制的な教えが記され、最初期の教会では解放されていた歩みが、後戻りをして再生産されて現在に至ってしまったのでしょう。
そろそろ、しがらみの再生産から抜け出し、イエスさまの宣べ伝えられた、平等で包括的な福音によって解放されないと、教会は誰も寄りつかない、中の人間は身動きのとれない不自由な共同体として閉じられてしまうのではないでしょうか。洗礼堅信の準備をしながらそんなことを考えさせられています。
後藤香織(名古屋聖マルコ教会牧師・愛知聖ルカ教会牧師・可児聖三一教会管理牧師)
フランシス江夏一彰師、司祭に叙任
「支持します」。会衆の力強い声が聖堂内に響き渡り、心が震えました。2017年12月16日、フランシス江夏一彰執事の司祭按手式が渋澤一郎主教の司式により長野聖救主教会において温かくも厳粛に執り行われ、中部教区内外より100名を超える参列者が集い、新司祭誕生の喜びを分かち合いました。江夏新司祭の勤務教会である軽井沢ショー記念礼拝堂とゆかりの深い聖路加国際大学聖ルカ礼拝堂聖歌隊メンバーによるアンセムと、中村勝・千恵子ご夫妻によるビオラとオルガンの演奏が按手式に花を添えました。説教者の中尾志朗司祭は「司祭職は自分の思いだけでは担えない。多くの人々、特に家族の理解と支えに感謝の気持ちを忘れないでほしい。また、今まで以上に苦労や誘惑も多くなると思うが、すべてを一人で抱え込もうとせず他の聖職に相談してほしい。」とユーモアを交えながら励ましの言葉を語られました。
私は推薦司祭として参列しましたが、改めて強く気付かされたことがあります。それは、聖職按手式で主教の問いかけに対して「支持します」と応答するとき、なぜいつも胸が熱くなるのかということです。10年以上にわたり軽井沢で共に歩んできた江夏執事の司祭按手式であったこともあり、特に強く感じたのかも知れません。私たちは何を根拠に聖職に按手される人を支持すると言えるのでしょうか。その人の持つ優れた才能でしょうか。豊かな学識でしょうか。あるいは温かな人柄でしょうか。それらのものはあるに越したことはありません。しかし、それらのものを根拠に支持するのであれば、当然支持しないという応答もあり得るでしょう。そうではなく、私たちが聖職按手式で「支持します」と確信を持って応答できるのは、それらのものを超えて神さまの御心が実現されることを信じるからに他なりません。神さまが今按手される人を用いてご自身を顕そうとされている、その恵みの場に立ち会っている私たちには「支持します」と言う以外の応答は考えられないのです。そこには圧倒的な神さまのご意志と導きがあります。
江夏新司祭は特任聖職(教区・教会から給与を受けないで職務を行う聖職)を志し、2012年9月に執事按手、以来平日は医療者として東奔西走し、日曜(多くの土曜も)は教会や地域において執事の務めを果たしてきました。その有能で誠実な人となりは改めて紹介するまでもないでしょう。何より江夏司祭がその豊かな賜物を用いて、神さまのご栄光をますますこの世界に現すことができますように、そして恵みに溢れた聖職按手に導かれる人が神さまの御心によって増し加えられますように祈り求めて参りたいと思います。
土井宏純(軽井沢ショー記念礼拝堂牧師、稲荷山諸聖徒教会管理牧師)
見えない光を求めて
今日、降誕劇は教会でもなかなか見られなくなってしまいましたが、クリスマスになると教会の幼稚園では、今でも降誕劇を行うところが多いと思います。年長児のクラスを中心にして主な役を振り分けて演じています。日頃の練習の成果により、見ごたえのある劇となっています。
それを見ていると色々なことを考えさせられます。この1年、社会で起こった様々な出来事、地震や豪雨のため引き起こされた、自然災害により困っている人々、地域紛争や内戦により避難せざるを得ない人、交通事故やその他人々によって起こされる様々な事故や事件による被害者など、世の中には不条理な出来事によって苦しむ人々が多くいることを考えさせられます。
そして原発の事故を考えると動物や植物といった自然そのものについても考えさせられます。そうした出来事は人間の努力で解決できそうなこともあれば、できないこともあります。お互いがもうちょっと協力して、譲り合えば何とかなりそうなこともあります。結局は一つ一つのことを当事者が丁寧に対応していくことになるのでしょうか。
日々伝えられる様々な情報の中で立ち止まってみて改めて考えてみると、「私たちの社会は一体何を目指しているのでしょうか」。目の前の出来事に何かと右往左往しているだけのような思いもします。右往左往する中でいつの間にか何を大事にしているかが見えなくなってしまっていないでしょうか。政治の世界では、好印象を与えるような方向に人が流れ肝心の政策がきちんとしないで人々に不安を与えるようなことになったり、産業社会では、日本を代表するといわれるような大きな会社で基準を満たしていないというようなことが起こったり、社会の基軸そのものが揺らいでいる印象があります。多くの人に、常と変わらないもの、灯台の光のようにあることが安心につながる、そうしたものを求める思いもあります。
私たちは何を目印にして生きようとしているのでしょうか。神様は、人々を救うために御子をこの世に遣わされました。そのことをヨハネは次のように書いています。「言の内に命があった。命は人間を照らす光であった。」(ヨハ1・4)しかし、「暗闇は光を理解しなかった。」(ヨハ1・5)とあります。私たちの混迷する現代社会は「暗闇」の例えそのものの様子とならないでしょうか。物質文明はどんどん発達していく中で、精神性がなおざりにされていて大切にされるべきことが共有されていないと思われます。そうした中で私たちは改めてヨハネがその先に書いた言葉と出会います。「言は、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。」(ヨハ1・12)
降誕劇を演じる子どもたちの真剣さは、見る人々を引き付けます。そこには世の救い主の降誕を真剣に待ち望み祝う姿があります。改めて私たちも心を澄まして、常に変わらずある光を見つめつつ新しい年の歩みを踏み出したいと思います。
日野原先生から教えられたこと ―「寄り添う」ことの意味―
去る7月18日、聖路加国際病院名誉院長、日野原重明先生が主のもとに召された。実に105歳のご生涯であった。青山葬儀所で営まれた葬送・告別式には、約4千人の人々が、日野原先生との、この地上での別れを惜しんだ。日野原先生には、個人的にも、さまざまなことを教えていただいた。4年ほど前、聖路加の理事会終了後に懇親会があり、たまたまお隣の席が日野原先生だった。日野原先生は、私に、「ところで西原さんはおいくつですか」と尋ねられた。私は、「ちょうど50歳になりました」と答えたところ、日野原先生から、「ああそうですか。あと50年がんばってね」と返されたのも愉快な思い出である。
忘れもしないのは、2013年8月に、聖公会関係学校教職員研修会の主幹校を立教大学が務め、私は、副総長として、同研修会運営の実行委員長に任ぜられ、基調講演の講師を日野原先生にお願いしたことである。日野原先生には、「一人ひとりの存在と共にあること―聖公会学校の原点を確かめる―」という主題で、ご講演いただいた。日野原先生は、ご自身の立教大学との深い繋がりを話された後、このようなことを語ってくださった。
「世界で最初の近代的なホスピス、聖クリストファー・ホスピスが、ロンドンの郊外のシデナムというところにあります。その創立者シシリー・ソンダース先生に、ソンダース先生が長年やってきたホスピスのことを一言で言えば、どういうことかと聞きました。がんの患者で痛みがある患者にモルヒネを与えて、そうして苦しみをとり、死の不安をできるだけとってあげるという、命が制限された患者に何が必要であるかを一言で私に教えてくださいと言ったら、彼女が言ったことは、”Being with the patient”、『患者とともに』。患者がだんだん、だんだん亡くなる時に、
患者がいろいろなことを思い出して語ることを静かに聞いてあげ、ああそう、ああそうということをして、患者が語る言葉を静かに聞きながら、その腕を握ってあげて、そして患者と一緒に死ぬような態度。これがホスピスの中に必要であるということ。死ぬ人と治療する人ではなしに、一緒に死ぬのだ、ともに死ぬのだ。これが『寄り添う』という、”Being with the patient”の一番大切なことであるということだ、と。」
日野原先生のこの言葉は、これからの医学において重要な視点という文脈であったが、私たちの教会にとっての〈宣教・牧会〉の核心とは何かについても、大いに示唆されている。一人ひとりの教会につらなる者に、「寄り添う」こと。この社会、世界で、痛んでいる人々、泣いている者たち、重荷を背負って生きざるをえない一人ひとりに、ていねいに「寄り添う」こと。それは、確かに、主イエス・キリストが、この地上でなされた働きに、倣うことに他ならないのである。
(岡谷聖バルナバ教会牧師)
うしろ姿のしあわせ
「アっ~、今日も抜かれてしまったァ!!」
職場へは最寄りの駅から歩いて行くことが多いのだが、必ずと言って良いほど、途中で追い抜かれてしまう相手がいる。その相手とは、中学生の女の子である。体は小柄で、手足も細く、一生懸命にその手を振りながら、自分よりも大きなカバンを背負って走り去って行くのである。走らなくては間に合わないのかなぁ、と、お節介なことを思うのだが、その光景が微笑ましくもあるのである。
ある朝のこと、その女の子が歩いていた。と、思ったら走り出し、また、歩いていたのだ。何となく、その走り方も歩き方もぎこちなく、いっぽうの肩も下がっているのに気が付いた。よくよく見ると、膝の辺りに繃帯が巻かれていた。おそらく、何処かで転んだかして怪我をしたのだろうが、その理由を知る由もない。そういえば、この女の子の顔を見たことはなく、辛く悲しくなっていないかと慮ってもしまうのだが、推察でしかない。
こう思うと、自分は沢山の人のうしろ姿を見て歩んできた、また、歩んでいることをあらためて感じた。そのうしろ姿は、若い時には沢山の先輩方である。しかし、そのうしろ姿は小さく、遥か彼方に見えるか見えないかであり、
早くそのうしろ姿が大きくならないかと、願ったものである。勿論、願ってばかりでは大きくはならず、大きくならないかと途切れ途切れに走ったりもした。しかし、そのうしろ姿に追いつくどころか、ちっとも大きくならないのである。また、小さくても見えれば良い方で、どうしても、うしろ姿が見えない方もおられる。
うしろ姿を見て歩いてきたとばかり思っていたが、年を経るとともに見られる側になってもいる。「江夏先生のいる教会へ行ってみたい」と声を掛けられることがある。その相手は、信徒ではない方が多く、また、実際に足を運んで下さる方もおられる。もし、自分のうしろ姿を通して教会への思いがつながるのであれば、身の引き締まる思いである。何故なら、自分が見えないうしろ姿の方が、自分のすぐ横を一緒に歩いて下さっているからである。その方が前を歩いているのではなく、その方が歩んだ道を自分が歩くとき、すぐ横で支えて下さっているからこそ、その方のうしろ姿が見えないことに気付いたのはいつのことだっただろうか。
年を経ると、歩みが遅くなる。必然的に、その横を若い人たちが、スゥっと追い抜いていく。そして、自分は再びうしろ姿を見ながら歩くことになる。この時に見るうしろ姿は、自分は支える側になってもいる。うしろ姿には、顔以上の表情が見える気がする。顔で笑って、背中で泣いている若い人たちを見てきた。顔だけではなく、うしろ姿にも笑顔でいられる世の中になって欲しいと祈り、また、働いていきたいと思う。
小さな女の子は、今日も一生懸命に前を向いて、腕を振りながら走っている。大きなカバンを背負いながら。この頃は、頼もしくさえもある。その小さなうしろ姿の力強さに、自分もしっかりと前を向いて、時には振り返りながら、歩んで行きたい。
(軽井沢ショー記念礼拝堂勤務)