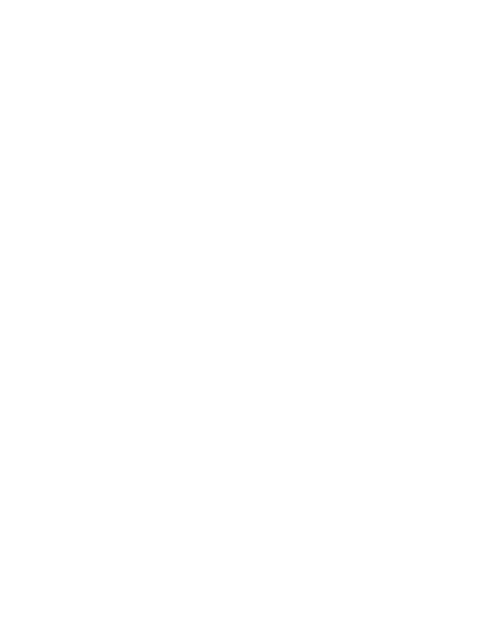「父と子と聖霊」の三位一体の神様というのは、わかりにくいかもしれません。日本聖公会では、「聖三一」と呼ばれることもあり、中部教区では岐阜県にある可児聖三一教会はこれに由来しています。教会は、この「聖三一」の神様を教理の発展のなかで信じてきました。日本ハリストス正教会では、アンドレイ・ルブリョフが描いた、アブラハムを訪ねる三人の天使(『創世記』)に拠る聖画(下の絵)が、唯一正当な図像表現として公認されているそうです。また、聖公会神学院にもこの聖画があり、いまも黙想のときに用いられたりしていると思います。アウグスティヌスは、聖三一の関係を「言葉を出すもの」父、「言葉」子、「言葉によって伝えられる愛」聖霊という類比によって捉えました(『三位一体論』)。三者はそれぞれ独立の相をなしつつ、一体として働き、本質において同一であると考えています。これが、西方神学における三位一体理解の基礎となります。
しかし、神様が「三つであるが一つであり、一つであるが三つである」というのは、理解する対象ではなく、信じる対象としての神秘であるとも考えられています。これが現代まで守り続けているのは、「頭で理解できたこと」よりも、「体験によって感じたもの」であるからだとも思います。例えば、私たちは、よく「主の祈り」を唱えます。これは「聖三一」の神をよく表しています。「主の祈り」は、祈り方がわからない弟子たちに、イエス様が直接教えた唯一の祈りであり、イエス様も神様に向かって用いていた祈りです。子なるイエス様が、父なる神様に祈った祈り、これを、私たちのうちにある聖霊によってお祈りする、これが「主の祈り」の大切なところであると思います。
神様は私たちを無条件にまず愛していて、これがこの世界の根本だと思います。神様は私たちへの愛を示すために独り子であるイエス様をお遣わしになりました。そして、その神様から遣わされたイエス様の無条件の愛に対して私たちが「はい」と答えたとき、私たちは真に神様の子どもになれるのです。今まで眠っていた私たちのうちにある聖霊が活発に動き出していき、私たちは真に神様の子どもとなり「主の祈り」を唱えます。
確かに現実はつらい状況もありますし、試練を抱えてはいますが、イエス様から「神様はあなたのことが大好きだよ」「そのことを信じますか」と呼びかけられて、私たちのうちにある聖霊によって「はい」と答えるというのが、聖餐式の大きなよろこびであり、ここに、私たちは、「三つであるが一つであり、一つであるが三つである」神様を感じることができるのではないでしょうか。そして、私たちが、「主の祈り」を唱えるとき、私たちが一人ではないこと、「いつもあなたがたと共にいる」神様をも感じることができると思います。
石田雅嗣(松本聖十字教会牧師)