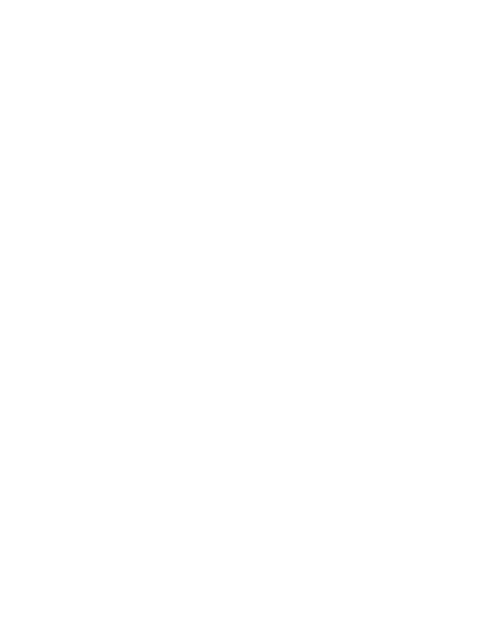8月下旬、プレ宣教協議会に参加してきました。2012年に開かれる「日本聖公会宣教協議会」の準備のための集まりです。「宣教する共同体のありようを求めて」というテーマでした。参加者は全員で80名でした。全教区からほぼ均等に参加者があり、女性の参加も約30名と多く、久しぶりの管区の集まりへの参加でしたが、何となく力強い思いがしました。植松誠首座主教はこの協議会を「お祭り」と表現しておられましたが、うまい表現だなと思いました。参加者がしかめ面をし、角付き合わせて議論しているばかりでは宣教への意欲は生まれてきません。そこに参加する人が大いに楽しんでわいわいするところから宣教への意欲が生まれてくるのです。そういう意味では今回の協議会はまだ本当にはお祭りにはなっていなかったかもしれませんが、本番の宣教協議会は大いに楽しめる協議会にしたいものです。
今回はいろいろな課題について話し合いましたが、各種の統計的な数字だけを見ますと日本聖公会の前途は悲観的です。どうしたらいいのでしょうか。ふと、岡谷聖バルナバ教会聖堂聖別記念誌の中にあった、聖堂建築当時の牧師であったコーリー司祭の文章が思い起こされました。コーリー司祭はこう書いておられます。「画期的な宣教方法などない。また、焦ると良い結果は出ないということを経験上わかっている。わたしたちは洗礼志願者と一年間祈りを共にし、そして洗礼へと導く。こうすることで、数は少なくても信仰深く陪餐を欠かすことのない信仰共同体を創り上げることができる。」
そっくりそのまま現代の教会にあてはめることはできないかもしれません。しかし、ここには大切な宣教・牧会の基本が示されているように思えるのです。