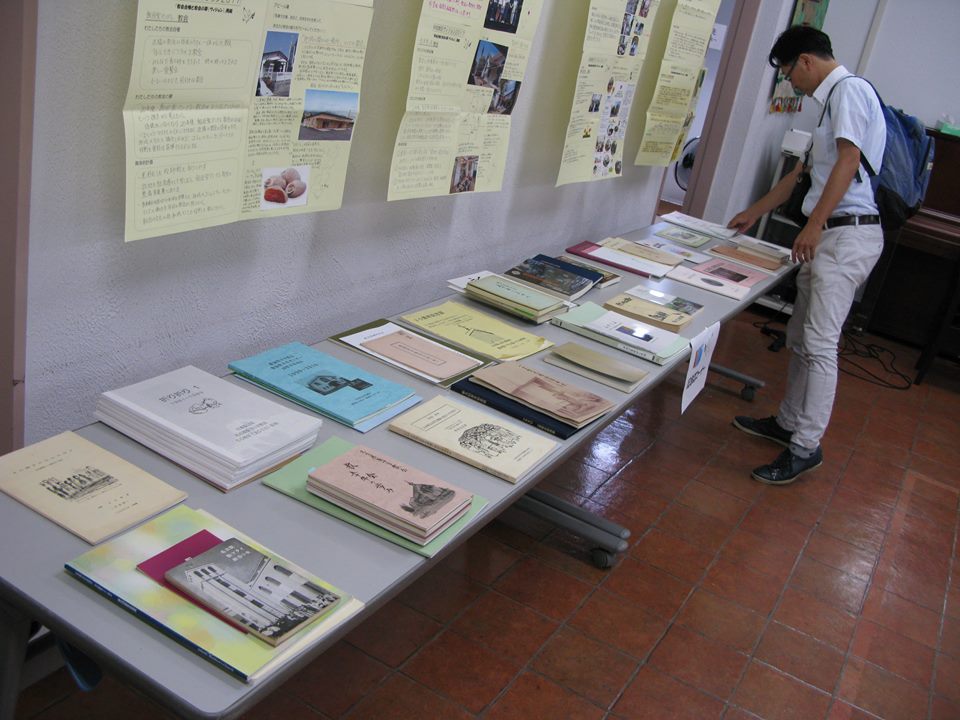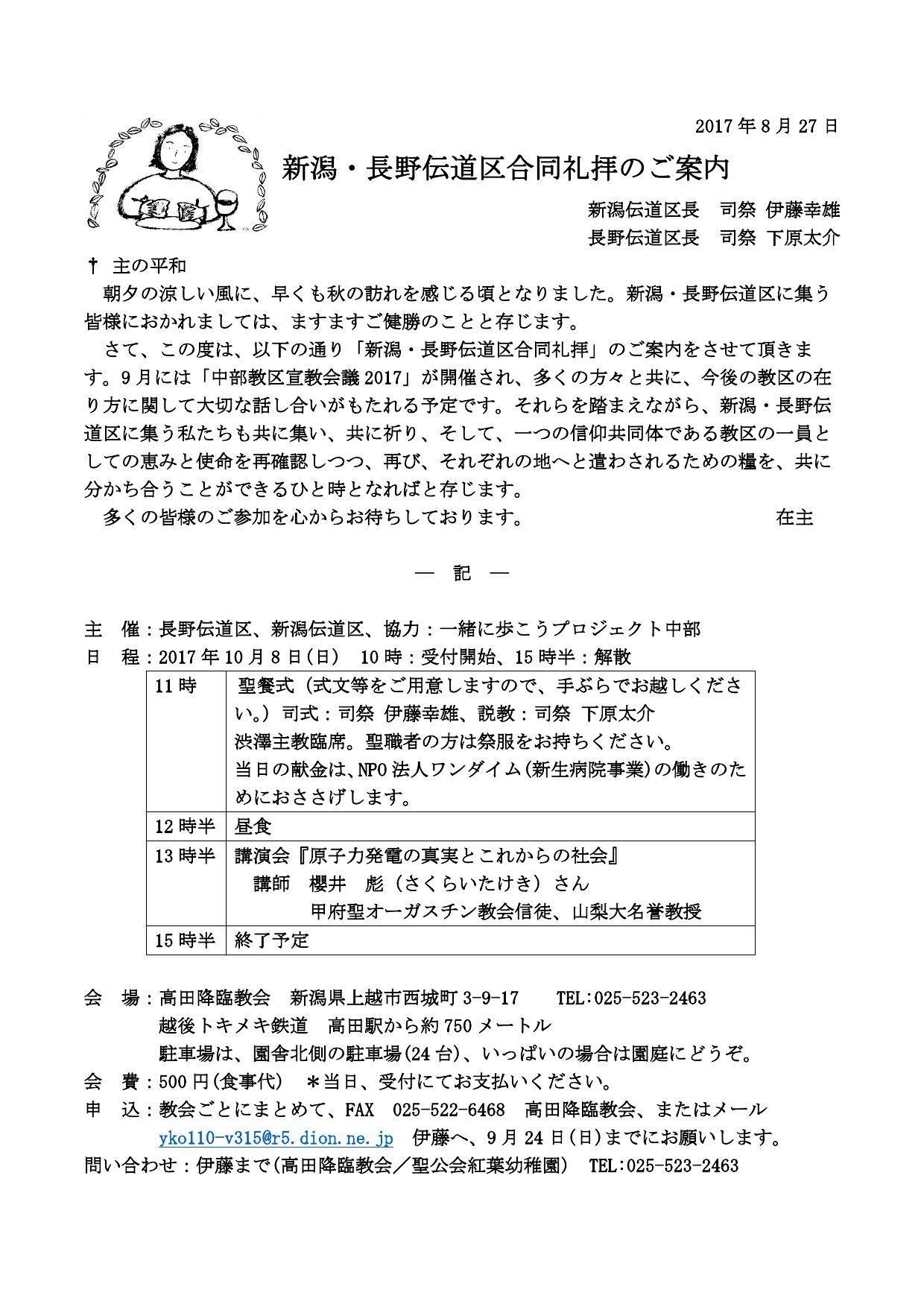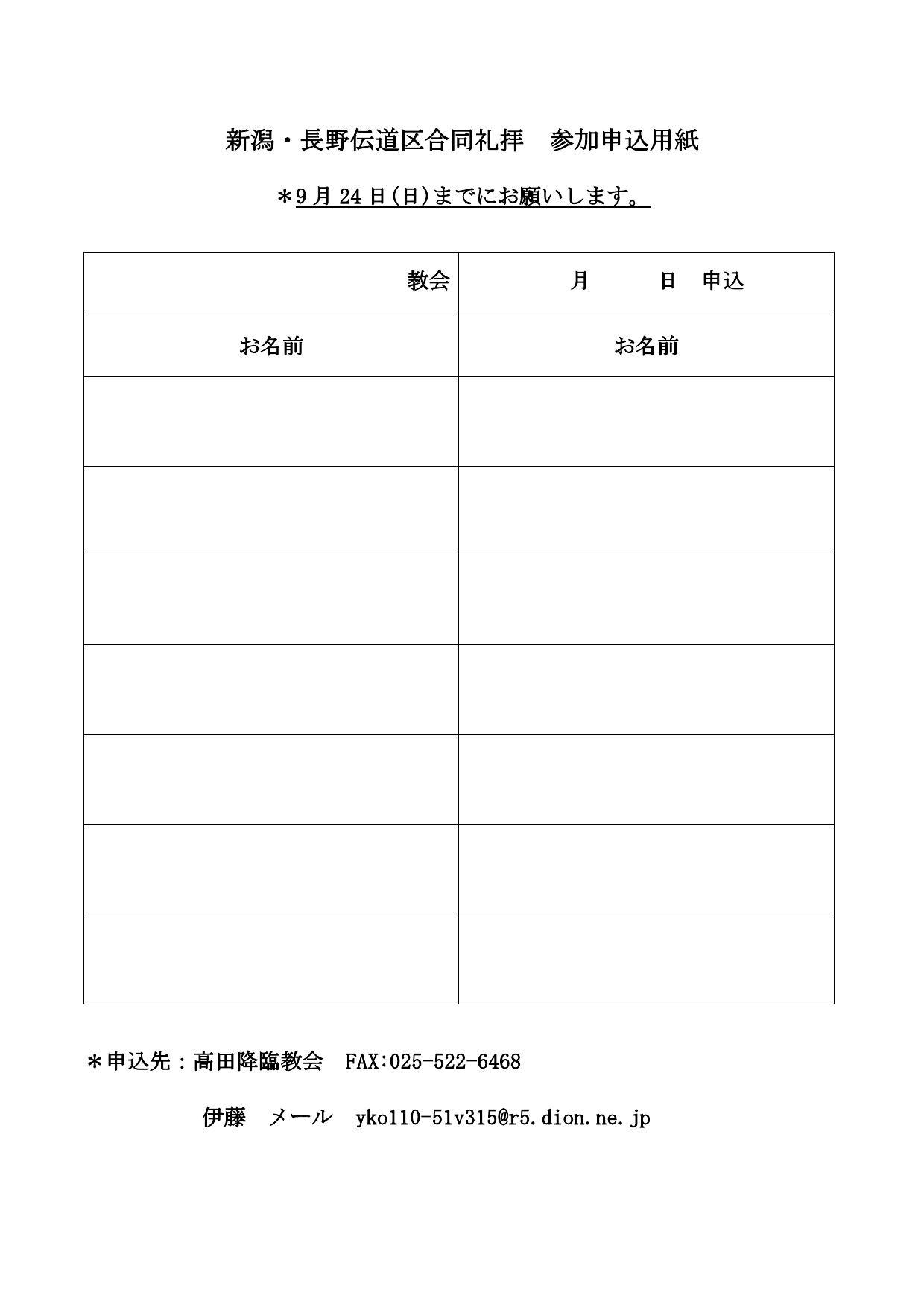先日の主日、大変恥ずかしいことをしてしまいました。午前にG教会で聖餐式・堅信式があり、午後はO教会で聖餐式でした。いずれも管理牧師と夏期実習中の聖職候補生が一緒でした。G教会での礼拝が終わり、食事を皆さんとご一緒し、O教会に向いました。教会に着き、さて、式服などの入った荷物を車から取り出そうと思ったところトランクに荷物がありません。何とG教会に忘れてきてしまったのです。しまったと思いましたが後の祭りです。片道4~50分の距離ですので取りに帰ることもできません。O教会では主に説教が役割でしたが、式服、祈祷書等はもちろん、説教の原稿も荷物の中に入れたままでした。
原稿がなくても説教ができないことはなかったのですが、この際、管理牧師におすがり(?)しようと思い、「説教も含めて聖餐式全部、お願いしてもいい?」と尋ねたところ、二つ返事で「いいですよ!」と言ってくれました。お陰様で助かりました。式服もありませんので、わたしは会衆席で聖餐式をお献げしました。主教になってからはもちろんですが、特別な場合を除いて主日に会衆席で聖餐式を献げたことはありませんでしたので思わぬ体験でした。
自分の注意不足で教会の皆さんに迷惑をかけ、しかも、これから聖職を目指す聖職候補生の前でこういう失態を犯すのは大変恥ずかしいことで大いに反省しなければと思ったことです。ちなみに、管理牧師さんは突然にもかかわらず大変良い説教をしてくれました。もちろん、説教原稿なしでです。感謝です。
蛇足ですが、わたしは時々、〝聖餐式が始まるというのに説教の原稿がなくてうろたえる〟という夢を見ることがあるのですが、それが正夢になってしまったように感じたのでした。
未分類
宣教会議2017
そこにいるということ
長く信仰生活を続けておられる方がいつも礼拝に出席しておられるということは何かホッとするものです。そこにおられるというだけで信仰を醸し出してくださるように感じます。
その少し前には別の教会を巡回しました。聖餐式の途中で小さい子供がむずかるためお母さんが気を遣って礼拝堂の外に連れていかれました。わたしは個人的には子供が多少むずかっても聖餐式という空間の中にいるということは大切なことだと思っています(泣き叫んでいる子を放置しておきなさいということではありません)。
小さな子供や赤ちゃんは聖餐式の意味や内容、説教も理解できないでしょう。しかし、理解できなくてもみんなが礼拝している空間にいるということが大切なのです。その場にいて礼拝の空気を全身で感じることにより、神様を知り、イエス様を知り、信仰の成長へとつながっていくのです。
殊に、選者としてご奉仕くださいました黒田淑子さんは歌人としてのお忙しい身にもかかわらず、また、途中体調を崩されたにもかかわらず長い間ご奉仕くださいましたこと本当に感謝です。これからもご健康に留意されご活躍されますよう心よりお祈りしています。
新潟・長野伝道区合同礼拝
平和を想う時
先日、岐阜市で開催されていた「子どもたちに伝える平和のための資料展」を見てきました。岐阜市は1945年(昭和20)7月9日深夜から10日にかけて米軍の空襲を受け、市の中心部のほとんどが焼かれ、約900人の犠牲者が出ました。
岐阜市は7月9日を「平和の鐘の日」とし、空襲での犠牲者を追悼し、戦争の悲惨さ残酷さを後世に語り継ぎ、平和への祈りを込めて鐘を鳴らします。この資料展もその一環として開催されています。主催は岐阜市ですが、企画・制作は「岐阜空襲を記録する会」が行っており、会の事務局長は岐阜の教会のメンバーが務めておられます。
資料展の規模は小さなものですが、畑を耕している小学生の様子や空襲前と空襲後の市内を写した写真、実際の焼夷弾などが展示されています。アメリカ軍が空襲1ヶ月前に撮影した岐阜市の航空写真は実に鮮明です。
当時の岐阜市中心街は空襲による火災の延焼を防ぐため道路が拡張されましたが―岐阜の教会もその時に強制的に撤去させられました。(戦後、現在の場所に移りました)―いざ空襲になりますと焼夷弾の威力の前には道路の拡張など何の意味もありませんでした。市内は焼け野原と化したのです。
8月は平和を想う(願う)時です。戦争は国と国、人と人とが争い、殺し合うことであり―しかも、無垢な非戦闘員が一番の犠牲になります―、平和な生活がすべて灰燼に帰すことを意味しています。
旧約のイザヤは「剣を打ち直して鍬とし 槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず もはや戦うことを学ばない」(2・4)と預言していますが、戦争の気配を感じさせるような昨今、武力では決して平和な世界は生まれないということをわたしたちは過去の戦争の経験から学ぶのです。
「共謀罪」の恐ろしさ
去る5月23日、十分な論議がし尽くされたとは思われない状況の中で、衆議院本会議において「共謀罪」法案が政府与党によって強行採決されました。この法律の怖さは何と言っても一般の国民がテロの調査・捜査対象にされ得るということにあります。もちろんテロは絶対に許されるべきではなく、その防止のためには十分な取り締まりが必要であることは言うまでもありません。
政府は、一般市民はテロ捜査の対象にはならないと言っていますが、テロを画策する人(々)は一般の市民と区別のつかない状況の中で、しかも極めて秘密裡にそれを行います。と言うことは一般市民であっても少しでも疑わしいと思われれば―捜査する側がそう判断すれば―いくらでも、誰にでも捜査が及ぶということを意味しているのです。
戦前、「治安維持法」という悪法がありました。当時の司法相は議会で「無辜の民にまで及ぼすことのないよう十分研究考慮した」と言ったそうです。ところが、実際に法律が施行されると全くそうではありませんでした。一般市民はもちろん、宗教団体もその対象とされたことは改めて申し上げるまでもありません。
中部教区主教であった佐々木鎮次主教は―戦争中には東京教区主教に転出しておられましたが―スパイ容疑で憲兵隊に拘禁され、寿命を縮めるほどの厳しい取り調べを受けました。南東京(横浜)教区の須貝止主教もそうでした。他の何人かの司祭たちも同様です。
恐ろしいことは官憲がある人(々)をスパイと特定すれば簡単に拘束することができてしまうということです。「共謀罪」はまさにそのような法律なのです。「治安維持法」の二の舞にならないと一体誰が保証できるでしょうか。