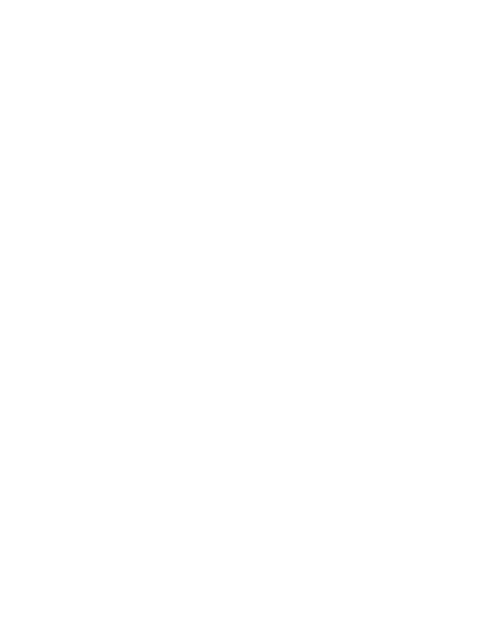立教小学校のチャプレンとして、日々、子どもたちの姿を見つめる中で、〝果たして、私は年を重ねながら、本当に成長してきたのだろうか?むしろ、退化してきたのではないだろうか…〟と思うことが多々あります。
純粋無垢な真の優しさ、何の恐れもなく両手を広げ、他者の全てをその身に受け止めることのできる心の広さと大胆さ、思ったこと、感じたことをありのままに表現し、それが正しいもの、優しさに満ちたものと賞賛されれば、全ての人々を幸せにすることができそうな程の笑顔を見せることができる、しかし、その逆に、それが正しくないもの、誰かを傷つけてしまうものと指摘されれば、それを真剣に受け留め、心から後悔し、時に涙を流しながら懺悔の祈りを唱えることができる。そして、何よりも、神の存在を常に身近に感じ、神の息吹の中を、いいや、まさに神の中で生きることができている。
私は、そのように生きる子どもたちの姿を見ながら、こう思います。〝昔、子どもであった私も、かつては、このように生きることができていたのだろうか。…きっと、できていた。でも、今は、もう…。なら、年を重ねた今の私は、成長したのではなく、それらを失った、退化した私なのでは?〟と。
主イエスは子どもたちを疎んじた弟子たちに対し、こう宣言し、子どもたちを高く抱き上げ、手を置いて祝福されます。
「子供たちをわたしのところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。」(マルコ10章14節~15節)と。
ここには、明確に、子どもたちの存在自体の尊さ、そして、神と神の国と子どもたちとの確固たる繋がりが語られているのと同時に、子どもの存在性を理解できず、子どもたちを疎んじ、
更には、かつて自分たちも持ち合わせていた「子供のように」
(子どものような存在性)を失ってしまった大人たちに対し、強い憤りを抱く主イエスの姿があります。
しかし、教会に集う大人たちは、今でも、子どもたちを一方的に〝小さく、弱い存在だから、主イエスの愛の名の下に、助け、導かなければならない〟と、無意識のうちに見下し、自分たちを、子どもたちの高みに置いてはいないでしょうか?
一匹の羽化できなかったヤゴの亡骸を本当に大事に抱え、校内の花壇に埋め、皆でアジサイを献花し、心を込めて祈り、黙祷する十数人の子どもたちの傍らに立ち、私は思いました…〝私には、こんな祈りはできない。私の祈りは、この子たちの祈りにはかなわない〟と。
そして、教えられました。これまで私は、ずっと、無意識のうちに大人の世界の価値基準の中で祈りの対象を選別し、存在に優劣をつけ、命の重さに差をつけ、祈り、また祈らずにいたのだと。
大人たちの教会は、常に悲しみや苦しみの中にある人々に心を留め、祈りを捧げ、愛を注ぎます。しかし、大人たちの教会は、自分自身が日々、踏みつけて歩く無数の蟻たちに心を留め、祈りを捧げ、愛を注ぐことはしません。できません。むしろ、その事実に気づいていない?気づかぬふり?
しかし、子どもたちは、その事実に気づき、真剣に向き合い、自分事として悲しみ、苦しみ、祈りを捧げ、愛を注ぐことができる。
存在に優劣をつけず、命の重さに差をつけず、存在価値を値踏みせず、祈りの対象を選別しない子どもたちは、まさに主イエスの似姿なのです。だからこそ、子どもたちは神の国に入ることができるのではないでしょうか?
かつて、主イエスの似姿であった大人たち。大人たちが「子供のように」(子どものような存在性)なれるのは、また、「新たに生まれ、神の国を見る」(参照、ヨハネ3章3節)ことができるのは、いつなのでしょうか。
司祭 ヨセフ 下原太介
(立教学院出向)