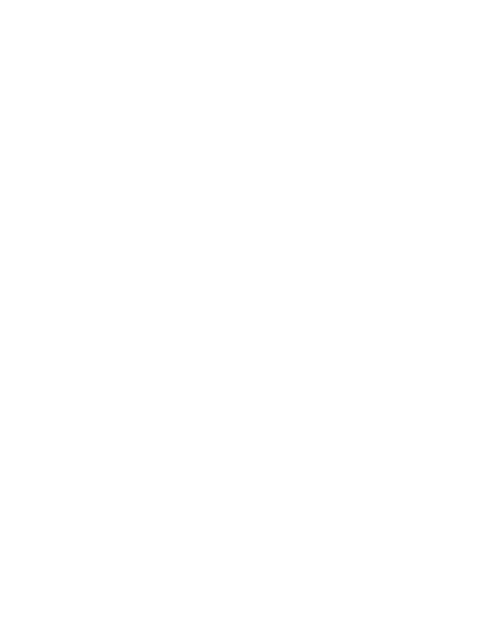「特祷」は、英語では「コレクト(collect)」と呼ばれ、カトリックでは「集会祈願」、ルーテル教会では「つどいの祈り」などと呼ばれており、広くキリスト教諸教派で用いられている短い祈りです。もともとは「祈りを一つに集める」という意味を持ち、司式者が会衆を祈りへと導くための祈りとして位置づけられています。とくに聖餐式では、式の最初の部分(「開式」)を締めくくる重要な祈りです。司式者は、「祈りましょう」という招きの言葉に続きその日に固有の特祷を唱え、会衆は最後に「アーメン」と唱えることで、これをともに祈ります。こうして、その日の礼拝に参加者皆が「集められる」のです。
第一祈祷書を編集したクランマーは、当時イングランドで用いられていたセーラム典礼からラテン語の特祷を英訳して採り入れたほか、いくつかの新しい祈りも加えました。その流れは今に続き、世界各地の聖公会で独自の特祷が用意されており、総数は千を超えると言われます。
かつての祈祷書には、特祷と共にその日の使徒書と福音書も記されており、これらのつながりが明確でした。しかし、現在世界の聖公会で主流となっており、日本聖公会でも90年祈祷書から採用されている3年周期の聖書日課では、各年の日課ごとのつながりが薄く、すべてを特祷と重ね合わせることは原理的に困難です。大韓聖公会など、各サイクルごとに毎主日3種類の特祷を用意している例もありますが、今回の祈祷書改正では、これは今後の課題とし、従来通り1主日1特祷を基本としています。
今回の改正案では、降臨節第1主日から三位一体主日までの特祷は、福音書の主題や期節の信仰的意味が反映されるよう配慮しました。一方で、聖霊降臨後の期節、いわゆる「特定」の期間は、日課が準継続朗読の原則で選択され、明確なテーマが設定しづらいため、聖餐式の導入部分を締めくくる祈りとしての機能に重きを置いています。
内容面では、長年親しまれてきた伝統的な祈りも残しつつ、一方では助けや危難からの救いを願う内容の祈りが多く見られたところに、現代社会に応答する視点から、宣教・創造・命・平和と和解といったテーマを取り入れた新しい祈りを、バランスに配慮しつつ加えています。たとえば、8月には平和に関する祈りを、11月には聖徒の交わりや逝去者を覚える祈りを置き、期節の流れと信仰生活とをつなぐ構成としています。
言葉の面では、堅い感じを与える漢語表現を可能な限り和語に改め、また神学用語を直接祈りの中で用いることも極力避けました。読みやすさを大切にする一方で、祈りとしての豊かさを損なわないよう慎重に言葉を選んだつもりですが、このあたりは試用してみてのフィードバックをお待ちしたいところです。
特祷ひとつ取っても、それが形となって新祈祷書に収録されるまでには厖大な労力が必要です。また、祈祷書に記された言葉は、それが私たちの口を通して祈られてこそ、「生きた祈り」となります。新しい祈祷書を形にする働きのためにお祈りをお願いしつつ、それを実際に試用してみることを通して、私たちの信仰と礼拝が豊かにされることを願っています。
司祭 ダビデ 市原信太郎
(松本聖十字教会管理牧師 東京教区主教座聖堂出向中)