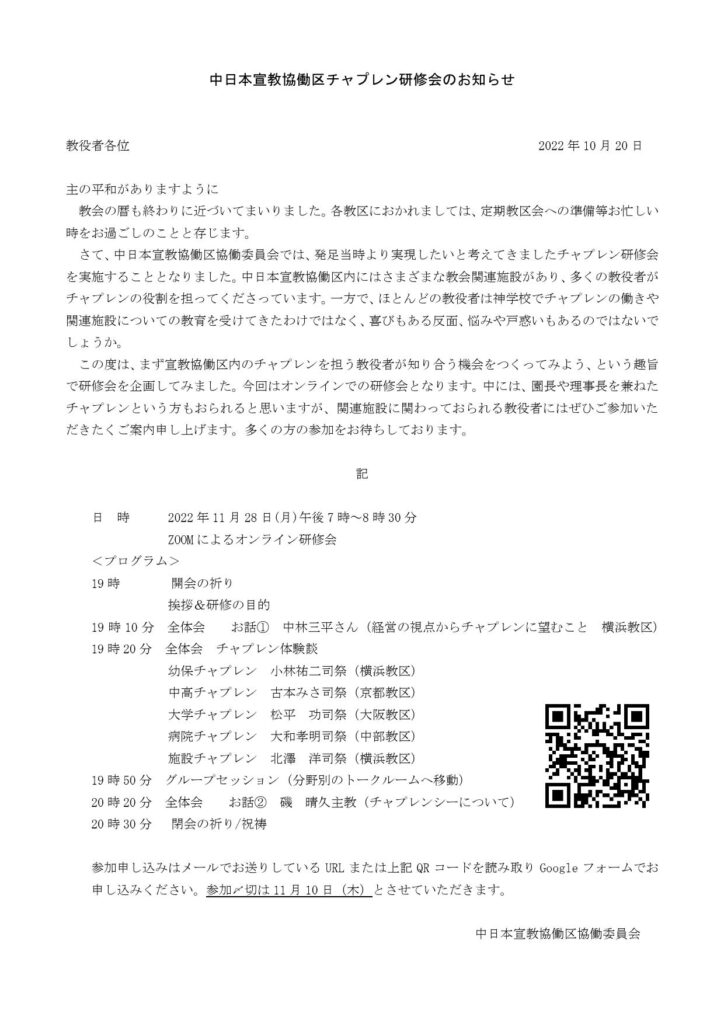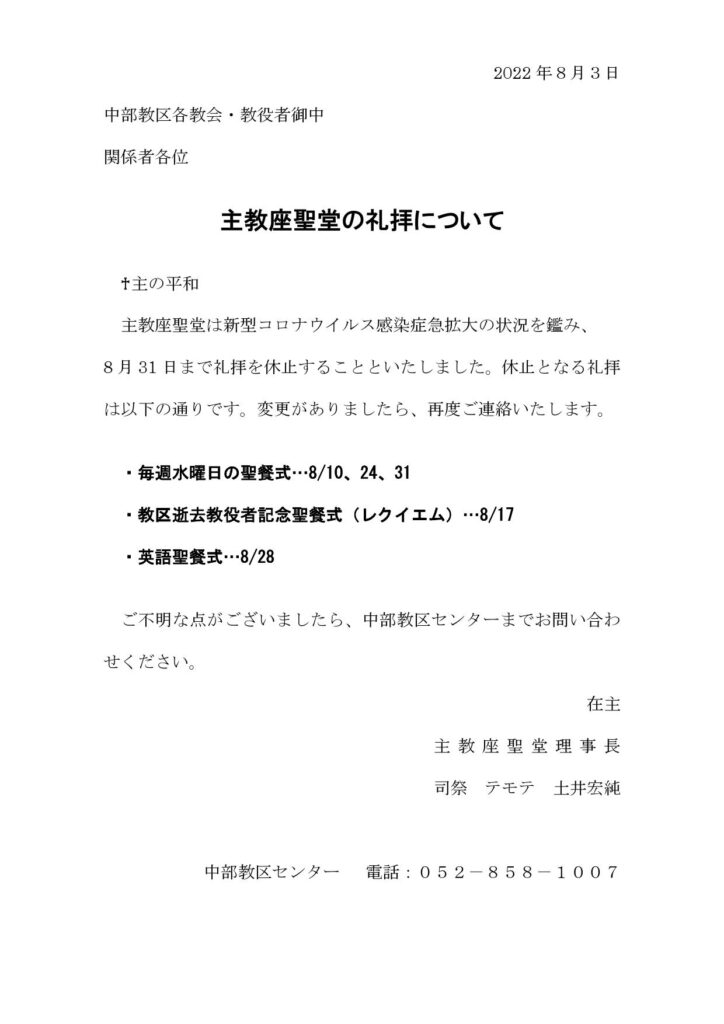戦乱や疫病によって荒廃した15世紀ロシアの村。一人の少年がいました。鐘造り職人の父を失った彼は、「鐘造りの秘訣を知っている」と人々に呼びかけ、新しい鐘の鋳造の指揮をとることになります。少年は皆に協力を求め、仲間と懸命に働きます。
困難を乗り越え、ついに鐘は完成します。多くの人々が見守る中、鐘は鳴り響きます。完成を見届けた少年は倒れこみ、涙を流し続けました。実は彼は、鐘造りの秘訣など、父から何も教わっていなかったのでした。
これは、私が20代のころ観た映画『アンドレイ・ルブリョフ』の中の一場面です。
当時私が通っていた大学院のゼミに、ロシアからの留学生の女性がいました。皆で昼食をとっているとき、私はその映画の話をしました。
その際、正教会の信徒であり、いつも穏やかな表情をしていた彼女が、急に真剣な顔をして私にたずねました。
「その少年は、なぜ鐘を造ることができたと思いますか」
当時まだ信仰を持っていなかった私は、そのまなざしに動揺しながら、「わかりません、どうしてだか」とだけ答えました。彼女はそれ以上何も聞きませんでした。少し眉をひそめて、眩しいような表情をしただけでした。
あれから20年経ち、病院チャプレンとして多くの患者さん達と出会い、看取り、別れてゆく経験を続けていく中で、彼女の問いかけの意味が、わかってきたように思います。
あの少年も、私もまた、ただ主のご恩によってのみ、仕事にとりかかり、取り組み、終えることができる。その方なしには、私たちは何一つできず、誰一人支えられない。私たちはただその方に、手で持ち運ばれ、用いられる器。
でもその方は、私たちをその場所に遣わされ、どんな苦しみのさなかにも、いつくしみをもって守られる。そして多くの人々と出会わせ、そのみ業をなしとげてくださる。
留学生の彼女は、信じて生きることと働くことの、不思議と喜びを、私に伝えたかったのだと思います。
病院の職員は、患者さんが亡くなり、お見送りの祈りをする際に、「いつくしみ深き」(聖歌第482番)を一緒に歌います。多くの人が知っているメロディですので、初めてのご家族でも、つぶやくように歌ってくださいます。
病床で出会い、ご一緒に日々を過ごした人と別れるのはつらいことです。時には、この歌をもうこれ以上歌いたくないとさえ思います。
でも、この不思議な歌をお見送りの部屋で歌うたびに、悲しみの底にいるご家族のそばに、そして立ち会う私自身のもとに、静かに、主のまなざしと優しさが満ちていくように思います。そして世を去ったその方と私たちは、いつか再び出会い、抱き合って喜び祝う時が与えられるのではないかと感じられるのです。
なぜ少年は、鐘を造ることができたのか。なぜ私は、この命と死の現場に立ち会わせていただいているのか。それはわかりません。主よ、わからないから私は、あなたのいつくしみにゆだねます。
私たちは、少年の造った鐘が鳴り響くのを、必ずいつか、愛するすべての人たちと一緒に、聴くことになるでしょう。「いつくしみ深き 友なるイエスは 変わらぬ愛もて 導きたもう」(同聖歌3節)。
ウクライナに、ロシアに、日本に、そしてこの地上に、平和がありますように。
司祭 洗礼者ヨハネ 大和孝明
(新生礼拝堂牧師)