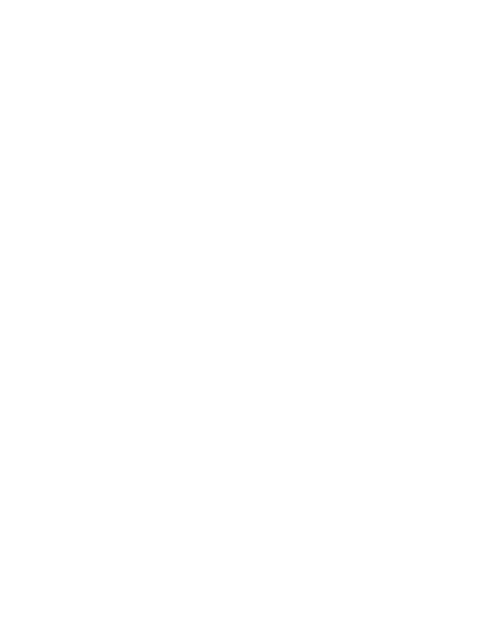この言葉は1960年代ころからことあるごとに言われてきた言葉です。 そのことが表している一つのことは、 世界全体が神の深い愛の対象であったということです。 神は神の子イエス・キリストを世界に遣わし、 人とし、 その地上の生涯、 十字架の死、 復活によって人間とすべてのものを救われました。 「神の子」 とは神とイエスの関わり方を、 有限である人間の言葉で最大限表現してみたものです。けれどもこれは「神」と「子」とは、まったく別であるような感じを与えます。しかし神と神の子とは一体です。イエスを表現するのに「神の子」と言う表現しか語りうる言葉がない。神の子の世界への登場とは実は神の大きな犠牲それも「世界」への大きな犠牲でした。つまり、イエスの生涯は、特に十字架の死は、神が別に関係ない人にそれを負わせ、なされた事柄ではなく、何と神がご自身を傷つけたことであり、痛みを負って、人間を始めとする全被造物を、すなわちこの世界を罪より救われたことなのです。イエスにその使命を与え、ご自身は離れて見ていたのではなく、神はご自分を傷つけてまで、私たち世界を愛されたのです。
教会は「キリストのからだ」であり、愛する世界に正義と平和が打ち立てられるまで、弱くされた人々のために働きます。このことの中にすべての人がいることは間違いがない。しかしそこには「弱い人々の優先」という考え方があることも長く言われてきたところです。世界が、実際は神の慈しみ深い「支配」(「神の国」の「国」を表す)の下にあるとするなら、また世界は広い意味で「教会」であるという洞察を受け入れるなら、現在の戦争、テロ、争い、人権侵害、いじめ、病気、貧困、ホームレス、環境破壊、政府の危ない政策その他否定的なことは、みな教会の中での出来事であることになり、私たちは黙視することはできません。私たち信徒に行動を促します。
教会は世界のためにあることのもう一つは、すべてが神によって「造られた」ことにあります。神は世界をその愛のゆえに、「良いもの」として創造されました。造られたものつまり被造物は造った方つまり神に賛美、感謝をつねにささげるようになっています。「主を賛美するために民は創造された」(詩編102:19)とあるとおりです。被造物が造物主なる神を賛美し感謝することは被造物の喜びの務めです。この世界全体は常に神に感謝をささげねばなりません。1世紀頃から「感謝」という名前の礼拝が教会によってささげられてきました。それはエウカリスティア(「感謝」の意。聖餐式のこと)と呼ばれました。つまり被造物の務めに気づいている教会は絶えずエウカリスティア、その他の感謝をささげてきたのです。教会は、「被造物の感謝」の務めに気づいていないこの世界のために、とりなしをし、世界を代表して、世界をその中に取り込んで、感謝をささげているのです。つまり、教会はこの世界のために存在するのです。教会のこの務めをすべての被造物が気づき、万物が「感謝」をささげる日を、神と教会とは待ち望んでいます。「み子が再び来られるまで」(日本聖公会祈祷書175ページ)。
主教 フランシス 森 紀旦