2020年12月13日付の主教書簡が公開されました。
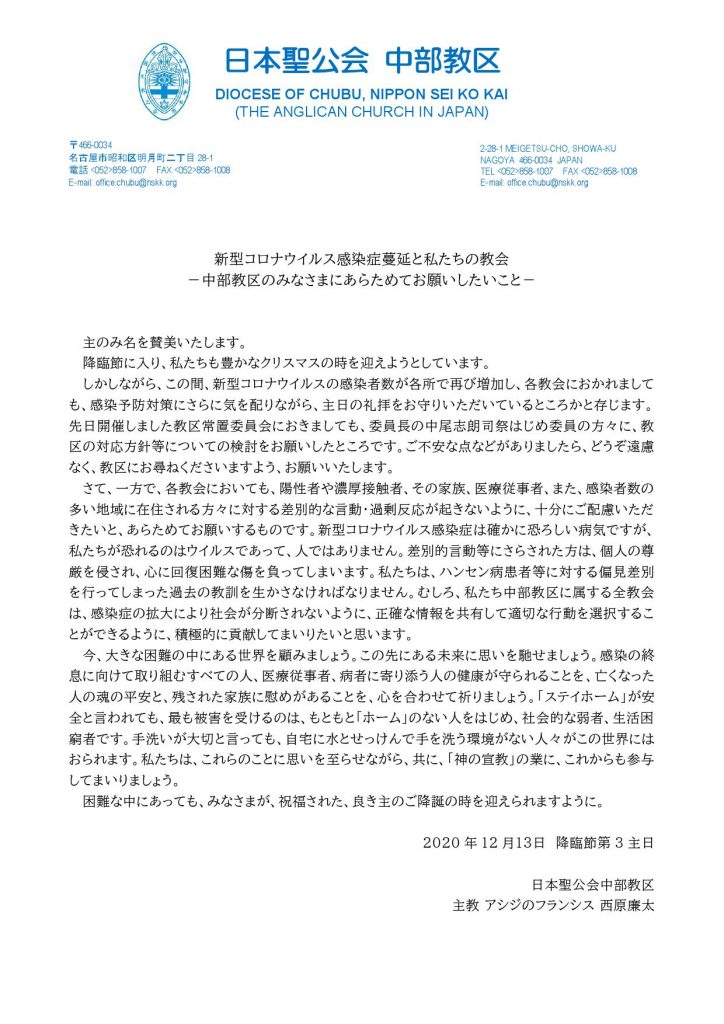
中部教区報「ともしび」に掲載された西原廉太主教による連載エッセイや巻頭メッセージ、関連するお知らせなどを掲載しています。バックナンバーもご覧いただけます。(肩書きは執筆当時のものです)
2020年12月13日付の主教書簡が公開されました。
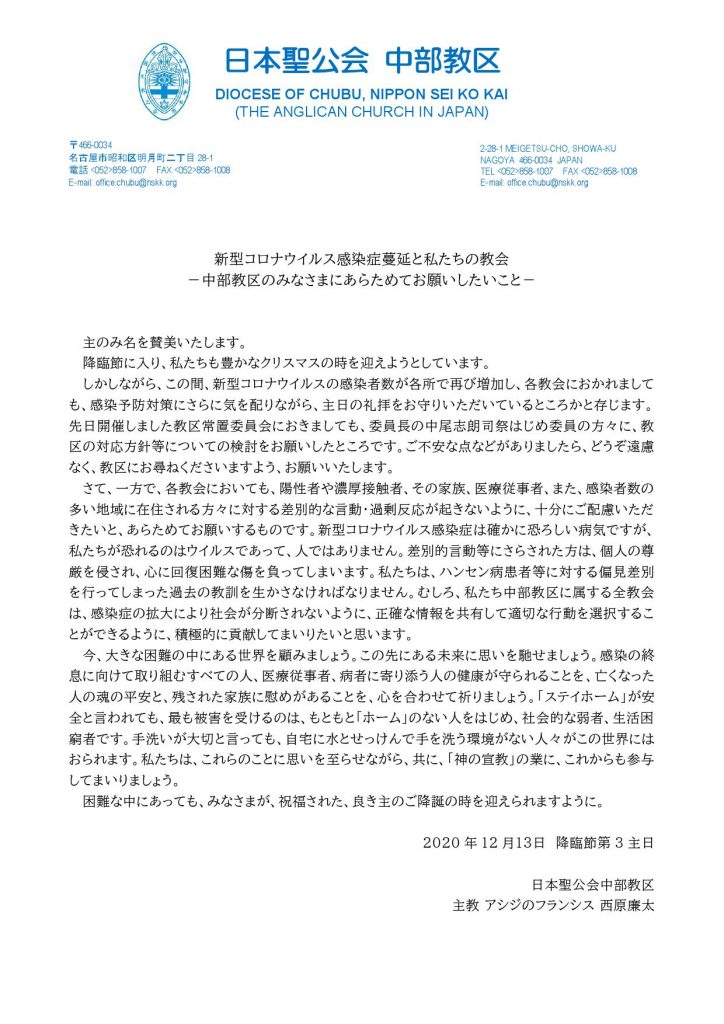
下記URLから番組アーカイブをお聞きいただけます。
NHKの連続テレビ小説『エール』でキリスト教考証を務める西原廉太司祭(主教被選者)の記事がプレジデント・オンラインに掲載されました。中部教区の豊橋昇天教会のことにも触れられています。是非、ご覧ください。
2020年5月31日
主教被選者 司祭 アシジのフランシス 西原廉太
[以下動画の内容をテキストで掲載]
おはようございます。私たちはペンテコステ、聖霊降臨日を迎えました。本日は、聖霊降臨日についてご一緒に黙想の時を過ごしたいと思います。
聖霊降臨日の礼拝の起源は大変古いものです。4世紀頃、エテリヤ(エゲリヤ)と呼ばれる女性が、聖地、エジプト、小アジア、コンスタチノープル一帯の巡礼の旅をしました。その記録、紀行文のようなものが現在でも残されております。それは、『エテリヤ(エゲリヤ)の巡礼記』と呼ばれていますが、11世紀以降、所在が分からなくなっていたのですが、1884年に、スペインのガムリーニという人によって再発見されました。その『エテリヤの巡礼記』には、4世紀当時のエルサレムでは、どのような礼拝が守られていたかが書かれています。それによりますと、聖地では、エピファニー(顕現日)、イースターと共に三大祝日として、今日のこのペンテコステ(聖霊降臨日)が守られていたようです。
西方教会でのペンテコステの礼拝は、当初は立ったまま行われていました。そして、礼拝の中ではアレルヤ唱が何度も唱えられ、また、少なくとも13世紀位までには、“Veni Sancte Spiritus”(「聖霊よ、おいでください」)という短い歌(セクエンティアと言いますが)が繰り返し歌われるようになりました。“Veni Sancte Spiritus”(「聖霊よ、おいでください」)と繰り返し歌いながら、人々は本当にキリストの息、神の息をその身に感じながら、ペンテコステの祭りを祝っていたのです。
本日の聖霊降臨日の福音書である、ヨハネによる福音書第20章19節以下には、イエスさまの弟子たちが最初にこの聖霊を受けた出来事が描かれています。イエスさまが十字架に架けられ、息を引き取られ、そして墓に葬られてからまだ三日しか経っていない時のことです。弟子たちは、一つの隠れ家に集まり息をひそめていました。彼らもまたイエスの「一味」として追われる身であったのです。彼らは身の危険を感じ、ぶるぶると震えていました。福音書にもこのように記されています。
「弟子たちは、ユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。」
彼らは、本当に恐ろしかったのです。不安と絶望に打ちのめされていたのです。ところがその時、驚くべきことが起こりました。イエスさまが、弟子たちの真ん中に立っておられるのです。そして、こう弟子たちに語られました。
「あなたがたに平和があるように。父が私をお遣わしになったように、私もあなたがたを遣わす。」
そのように語られてから、イエスさまは、「聖霊を受けなさい」と、弟子たちに息を吹きかけられた、と記されています。
「聖霊」とは、主イエスの「息」なのでありました。確かに、聖霊とは「息」であります。ヘブライ語で「聖霊」は、「ルアッハ」と言います。これは「息」あるいは「風」を意味します。聖霊とは神の息であり、神の風であります。何か体に受ける力、エネルギーのようなものです。
主イエスの息、聖霊を受けた弟子たちは、この瞬間から、生きる力を回復します。希望を取り戻します。あれほどまでにも、不安と絶望の内に震えていた彼らが、死んだようになっていた彼らが、命を回復したのです。そして、弟子たちは、大胆に主イエスをキリストとして証ししていきます。この力こそが聖霊です。キリストの息、神の息なのです。
イエスの十字架上での死によって絶えたはずの主イエスの福音は、こうしてよみがえりました。神の息を受け、聖霊を体に満たしたこの弟子たちは、再び福音を宣べ伝えていく勇気を取り戻しました。
聖霊は、打ちのめされた者、絶望の淵にある者、痛み、苦しみにある者、疲れた者に与えられる生きる力です。私たちが”Veni Sancte Spiritus”(「聖霊よ、おいでください」)と唱える時、私たちは、神の息に満たされ、苦しみや疲れは癒され、明日への希望と勇気が備えられるのです。
預言者エゼキエルがイスラエルの罪に満ちた現実に直面し、腰から砕け落ちた時、神はエゼキエルにこう言われました。「人の子よ、自分の足で立て。」すると、聖霊がエゼキエルの中に入り、エゼキエルを自分の足で立たせた、と書かれています。神の聖霊が息のように彼らの体に入り、自分の足で立たせた、のであります。
さて、実は本日の福音書には、もう一つ非常に大切なことが記されています。それは、20節にあります。イエスは、「そう言って、手とわき腹とをお見せになった」という箇所です。イエスさまは手とわき腹を見せられた。すなわち、十字架上で釘を打ち抜かれた手とわき腹の傷跡をお見せになったのです。
本日の福音書は23節までが読まれましたが、すぐあとの24節以降には、トマスがこのイエスのわき腹の傷に直接手を当てて、主を信じる物語が置かれています。イエスさまは、トマスにこう言われます。
「あなたの指をここに当てて、わたしの手を見なさい。あなたの手を伸ばし、わたしのわき腹に入れなさい。」
そして、トマスはうめくように、振り絞るように言葉を発します。
「わたしの主、わたしの神よ。」
トマスに声をかけられたイエスは、栄光のイエスではありませんでした。復活されたイエスとは、光輝く天の衣をまとい、金の王冠をかぶったイエスではなかったのであります。トマスと弟子たちの前によみがえられた主とは、手に傷を負い、わき腹から血を流し、荊の冠をかぶらされたままの姿であった、のであります。おそらくトマスは実際に、その主の傷に、自らの手で触れたのだと思います。
主イエス・キリストは、傷を負われたまま、よみがえられました。その傷とはいったい何であったのでしょうか。イエスさまは、その短い公生涯の間、虐げられた人々、病める人々、体の不自由な人々、捨て置かれた人々の痛みと傷を自ら負われ、ついには十字架に架かられました。そして、その無数の痛みと傷を担われたまま、主イエスはよみがえられました。まさに、この事実に、トマスはただ、「わたしの主、わたしの神よ」という、この世で、最も短く、同時に最も完全な信仰告白の言葉を発することができたのでありました。
また、イエスさまの手とわき腹の傷は、他ならない、私たちの傷でもあります。イザヤ書第53章には有名な「苦難の僕」の記述があり、よく、イエスの十字架はこの「苦難の僕」とのつながりの中で考えられます。このような記述です。
「見るべき面影はなく、輝かしい風格も、好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。」「彼が担ったのはわたしたちの病。彼が負ったのはわたしたちの痛みであったのに」。
イエスさまは、私たちの苦しみ、悲しみをこそ担われ、それゆえに十字架の上で「荊の冠」をかぶせられ、そして、私たちの痛みと傷を負われたまま、よみがえられます。私たちは、それゆえに生きていくことができるのです。
弟子たちは、主の息をその身に感じ、そして主の傷にその手で触れることによって、「わたしの主、わたしの神よ」と証しすることができました。主イエス・キリストの息と傷についての弟子たちの記憶が、その後弟子から弟子へと伝えられ、それがやがてキリストの体としての教会となっていきました。そういう意味では、「教会」とは「イエスの息と傷を記憶し続ける共同体」であると言うことができると思います。その記憶は、今や全世界に伝えられました。2000年の後の今、私たちが聖霊降臨を祝っているのも、主の息と傷についての、弟子たちの具体的な記憶が絶えることなく受け継がれてきたからに他なりません。
今、私たちは、新型コロナウィルス感染症の蔓延のために、今日の聖霊降臨日も、共に礼拝堂に集まることができません。私たちは、教会で、お互いの息も感じることもできず、「主の平和」を互いに手を触れ合いながら交わすこともできません。それは教会としては大変寂しいことです。
けれども、私たちは、そのような状況であるからこそ、2000年前の主の弟子たちを思い起したいのです。彼らも、イエスさまの息を感じ、その傷を手に触れることはできなくなりました。しかし、彼らは、そのあと、主イエス・キリストの息と傷を、「記憶」として、その後の者たちに受け継いでいったのでした。いつかまた、イエス・キリストが、私たちのもとに来られるその時まで、イエスさまの息と傷を記憶しながら、ひたすらに「待つ」ことに生きたのでした。私たちも、このような時であるからこそ、主イエス・キリストの息と傷についての弟子たちの「記憶」を、深いところで黙想したいのであります。

さて、ここに、私が大切にしている一冊の写真集があります。『家族の日記』と題された、小倉英三郎さんという方が撮られたものです。小倉さんのおつれあいである亮子さんが、27歳の若さでガンを宣告され、そして亡くなるまで、小倉さんは最愛の妻と二人の幼い子どもたちにカメラを向け、シャッターを切り続けられました。それが一冊にまとめられたのが、この写真集です(小倉英三郎『家族の日記』未来社、1995年)。
池袋の文芸座という名画座のアルバイトを通して出会われたお二人は、結ばれて鉄平くんという男の子を授かり、幸せな生活を送っておられました。ところが、二人目の子どもがお腹の中にいて、もう直に出産という時に、亮子さんは、第3期の乳ガンであることを宣告されます。出産が済むまでは抗ガン剤などの治療を受けられずに、病状は進行してしまいました。
小倉さんが写真集を作ろうとされた理由が後書きに書かれています。
「彼女が出産を控えた微妙な時期に、深刻な病気を宣告された、ということもあって、私たちには選択の余地も時間的な余裕もありませんでした。私たちは、お互い心の整理もつかぬまま、先行していく運命に追いつこうと必死でした。今まであったはずの日常生活はもうありませんでした。だから行き先のわからない運命にとまどいながらも懸命に生きている、亮子や子どもたちの日々を記録することで、家族の存在を確認したかったのだと思います。亮子にしてみれば、生まれてくる赤ちゃんのこと、1年と10ヶ月、片時も離れずに暮らしてきた鉄平のこと、自分の乳房を失うこと、そしてそんな代償をはらっても油断できない病気のことに、どれだけ心を痛めていたかわかりません。母として、妻として、そして女としてあった自分の居場所を見失って心細くしていたと思います。」
写真集は長男の鉄平くんと、生まれたばかりの青佳(はるか)ちゃんを抱きながら病気と闘う亮子さんの姿が残されています。結局、1994年10月4日のことですが、28歳の誕生日を10日後に控えたその日、早朝、亮子さんは亡くなられました。

たくさんの写真の中でも、私が最も心を揺り動かされるのが、この写真です。病院から一時帰宅を許された亮子さんが、電車の中で、鉄平くんをぐっと抱きしめて離さない写真です。今日、この写真集をご紹介しようと思いましたのは、私はこの1枚の写真からいろいろな黙想を促されたからです。
イエスさまが弟子たちに息を吹きかけられた時、きっとイエスさまはこんな風に弟子たちの一人一人をぐっと抱きしめられていたのではないか、と思うのです。息は、遠くからでは決して届かない。こんな風に、抱きしめられながら、鉄平くんが体の温もりの中、亮子さんの息遣いをその頬に受けたように、弟子たちもまた主イエスの息づかいを感じていたのではないか、と思うのです。
小倉さんは、あるエッセーの中でこう書かれています。
「妻の手術の傷を直接この手に触れ、そして直面する運命にひきずられるように写真を撮り続けた。そして今、私の手は妻の傷をはっきりと覚えている。一枚一枚の写真は、確かに亮子が生きていたことの大切な証しである。いや今そうやって、亮子は私たち家族の中に生きているのだ。」
写真評論家の飯沢耕太郎さんは、この写真集を、『終わらない家族』と評されました。
弟子たちも、もはやイエスさまとじかに触れあうことが許されなくなったけれども、しかしながら、主イエスの傷をその手にはっきりと覚え続けたはずです。そうやって、主は弟子たちの中に生き続けたのです。確かに、私たちの教会とは、主イエスの息と傷を記憶し続ける、『終わらない家族』であるのかも知れません。私たちも、主の息を頬に感じ、この手に主の傷を覚えて生きていきたい、と思うのです。♰
2020年4月12日
主教被選者 司祭 アシジのフランシス 西原廉太
[Youtubeで字幕機能をONにすると字幕が表示されます]
[以下動画の内容をテキストで掲載]
私たちは、主のご復活を祝う復活日、イースターを迎えました。しかしながら、今年、2020年のイースターは、後のキリスト教の歴史においても、異常な事態の中で迎えたと特別に記録されることでしょう。本来は、主のご復活を、日本聖公会、中部教区のすべての教会で、豊かにお祝いするはずでしたが、今般の、新型コロナウイルス感染症の急速な蔓延、世界的なパンデミックという状況の悪化に直面し、教区としても、大変残念なことに、聖週、イースターも含めて、5月24日までの主日及び週日の礼拝は、教役者・信徒が一堂に会して行うことを休止する、という苦渋の決断をすることとなりました。3月28日に予定していました中部教区主教按手式も一度は5月2日に延期したものの、10月24日へと再度延期せざるを得なくなりました。その間は、横浜教区の入江主教さまが、私たち中部教区の管理主教を担ってくださりますので、どうぞご安心ください。
 教会に集うことができず、共に聖餐式や祈りをおささげできないことは、私たち聖職たち、そして信徒の皆さんにとって、これ以上に辛いことはありません。しかし、大切なことは、だからと言って、私たちは教会を閉じているわけではない、ということです。世界の聖公会、アングリカン・コミュニオンの公式ホームページを開きますと、このような素敵なイラストが出てきます。そして、ここに重要なメッセージが記されています。
教会に集うことができず、共に聖餐式や祈りをおささげできないことは、私たち聖職たち、そして信徒の皆さんにとって、これ以上に辛いことはありません。しかし、大切なことは、だからと言って、私たちは教会を閉じているわけではない、ということです。世界の聖公会、アングリカン・コミュニオンの公式ホームページを開きますと、このような素敵なイラストが出てきます。そして、ここに重要なメッセージが記されています。
「教会は閉じているのではありません。ただ、建物だけを閉じているのです。なぜなら、私たちが教会だからです。私たちこそが、主イエス・キリストの生ける<からだ>だからです。そして、私たちはこの世界中、至るところに存在しているからです」
皆さんお一人おひとりが教会なのです。仮に聖堂という建物に集うことができなくても、皆さんお一人おひとりが、それぞれの場で、心を合わせて祈られる時に、そこに、主イエス・キリストの生ける<からだ>が実現しているのです。ですので、ぜひ、この異常な事態の中にあっても、私たちは、主にすべてを委ねて、主を信頼して、共に祈りを合わせたいのです。今、それぞれの場で祈っている教会の仲間たちを覚えて、また、新型コロナウイルス感染症のために苦しんでいる方々、そのご家族、困難の中、治療にあたられている医師や看護師の方々を覚えて、この世界中で、言い知れない不安の内に、心を痛めているすべての方々を覚えて、心を合わせて祈りましょう。
さて、そのような恐れと不安の内にある私たちにとって、本日の復活日の福音は、深い励ましを私たちに与えてくれます。イエスさまが十字架に架けられ、墓に葬られた。その週の初めの日の朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアが、墓に行った、とあります。なぜ葬られた直後ではなかったかというと、ちょうど安息日が重なり、彼女は何もできなかったからです。安息日が終わると、まだ夜も明けない暗い内に、彼女はすぐに、いてもたってもいられずに、イエスさまが葬られた墓に駆け出して行きました。
彼女は、少しでも早く、イエスさまの遺体に香油を塗ってあげたかった。イエスが十字架に架けられ絶命し、さらに槍でわき腹を突かれ、血を流されたその姿を、マグダラのマリアは目の当たりにしていました。ヨハネによる福音書第19章25節にはこう記録されています。「イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた」。マグダラのマリアはその場にいながら、ただただ茫然と立ち尽くすしかなかった。彼女は、おそらく言い知れない無力感に打ちのめされたに違いありません。あれほど愛して、つき従っていた主イエスが今、死に行こうとしているのに、何一つすることができないのです。彼女の中には、「なぜ」という言葉が渦巻いていたはずです。「なぜ」私たちの主が、この地上から、私たちのもとから取り去られなければならないのですか。神さまは「なぜ」、私たちの愛する主をお守りくださらないのですか。「なぜ」このような試練を私たちにお与えになるのですか、と。
そんな彼女が、最後に主イエスにして差し上げられる唯一のことが、イエスさまのお体に香油を塗ることでした。しかし、マグダラのマリアがイエスさまの葬られた墓に辿りついた時、そこには驚くべきことが起こっていました。墓から石が取りのけてあり、墓の中にあるはずのイエスさまの体がなかったのです。彼女は、急いでペトロのところに駆けつけてこう報告しています。「主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、私には分かりません」。それを聞いたペトロたちも墓に走って確認しに来ます。この時の様子を伝えるヨハネによる福音書の記述は実に興味深いものです。ペトロたちは、墓の中を検分し、「イエスの頭を包んでいた覆いは、亜麻布と同じ所には置いてなく、離れたところに丸めてあった」ことを確認し、それで、彼らは「信じた」、納得したというのです。きわめて冷静に墓の中を調べ、それで納得できてしまうものなのか、と正直思います。マグダラのマリアは違いました。20章11節にはこうあります。「マリアは墓の外に立って泣いていた」。彼女は、ペトロたちが納得して帰った後も、ずっと墓の外で泣き続けていたのです。彼女は言葉にもできない、悲しみと不安、恐れの中で、ただひたすらに、ぶるぶると震えながら、墓の外で泣き続けていた。彼女の中には、さらなる「なぜ」が溢れてたはずです。「なぜ」イエスさまのお体さえもが取り去られてしまうのですか。「なぜ」、主のからだに油を塗ることさえも許されないのですか。「なぜ」神さまは、こんな不安と悲しみ、恐れを私たちにお与えになるのですか、と。
そんな彼女のそばに、いつの間にかイエスさまが立たれていました。20章15節をもう一度お読みします。
イエスは言われた。「婦人よ、なぜ泣いているのか。だれを捜しているのか。」
主イエスは、マリアにこう語りかけられるのです。「なぜ泣いているのか」と。あなたはなぜ泣いているのか。ここできわめて大切なことは、実は、イエスさまは、マリアが泣いているその理由を尋ねておられるのではない、ということです。彼女が立ち尽くし、打ち震えながら泣いているその理由は、すでにイエスさまご自身が十分に知っておられるのです。イエスさまがマリアに、「なぜ」とこう語りかけられたのは、彼女の涙の理由を知りたいからなどではなく、「あなたは、なぜ泣いているのか、泣く必要など何もないのだ」ということを、彼女に気づかせたいからでありました。私があなたの傍に今もいるのだから、何も恐れることはない、あなたはもう泣かなくてもいい。主はそのことを、彼女に伝えようとされていたのです。
実はこの「なぜ」というのは、マグダラのマリアがずっと抱えていた問いに他なりませんでした。「なぜ」私たちの主が、この地上から、私たちのもとから居なくならなければならないのですか。神さまは「なぜ」、私たちの愛する主をお守りくださらないのですか。「なぜ」このような試練を私たちにお与えになるのですか。「なぜ」イエスさまのお体さえもが取り去られてしまうのですか。「なぜ」、主のからだに油を塗ることさえも許されないのですか。「なぜ」神さまは、こんな不安と悲しみ、恐れを私たちにお与えになるのですか、と。
この「なぜ」という問いは彼女の「無力さ」とも裏表です。私には、十字架に架けられたイエスさまを前にして何もできなかった。ただただ茫然と立ち尽くすのみであった。唯一の彼女ができる最後の主に対する奉仕のはずであった、遺体に香油を塗ることすらも許されなかった。何という無力さでしょうか。
この「なぜ」という問いと「無力さ」は、マリアだけのものではなく、私たち一人ひとりの「なぜ」であり、「無力さ」でもあります。私たちもそれぞれの日常の中で、いつも何かしら、この「なぜ」を神さまに問い、「無力さ」に打ちひしがれる存在です。神さまはなぜ、私に、こんな抱えきれないような重荷を背負わされるのですか。なぜ、あなたは、こんな悲しみや苦しみを私にお与えになるのですか。あるいは、あの時、なぜ、私は、こうしなかったのか。私はなぜ、あの時に、あの人の傍に居てあげられなかったのか。私たちにはそのような「なぜ」もあります。
今、私たちは、新型コロナウイルス感染症の急速な蔓延、多くの方々が治療のかいなく死にゆく事態に直面し、まさしく神さま「なぜ」と叫ばざるを得ません。目には見えない得体の知れないものに対する恐怖と不安の中で、私たちの心も蝕まれています。医療や看護に献身的に、犠牲的に携わる方々は、必要な措置も出来ぬまま、救えなかった命を前にして、絶望と無力さに苛まれておられると聞きます。そのような医療従事者の方々ご自身が、感染されてしまうという事例を耳にする時、私たちには祈る言葉すらも見つからなくなるのです。
イタリア政府は、4月6日の時点で、新型コロナウイルスに感染した方が13万2547人、亡くなった方が1万6523人に至ったと発表しました。そのイタリアで、北部ロンバルディア州ベルガモ県カスニーゴのローマ・カトリック教会司祭長のジュゼッペ・ベラルデッリ神父さまは、新型コロナウイルスに感染され、重篤となられました。しかしながら、報道でもご承知のように、イタリアでは人工呼吸器が圧倒的に足りません。ベラルデッリ神父さまは、ご自分が使用していた人工呼吸器を、若い感染者に譲って欲しいと医師たちに懇願し、人工呼吸器が外されて間もなく、3月15日に、ベルガモ県の病院で息を引き取られ、主のもとに召された、ということです。72歳でした。ベラルデッリ神父が司祭長を務める地域の住民たちは、神父の死を知ると、窓越しから「慈悲の殉教者」と拍手で称えた、と言います。
今、私たちも不安でいっぱいです。また、無力さに打ちのめされています。本当は、こうして人々が極限の苦難に遭っている時にこそ、皆で教会に集い、祈り、そして、苦しんでいる人々のもとに駆け付けて奉仕をしたいのです。しかし、それは叶いません。私たち自身のいのちを守るためだけではなく、私たちが移動することによって感染を拡大し、私たちが教会に集うことによって、いわゆる感染のクラスターを発生させるということがあってはならないからです。私たちキリスト者、教会にとって、本来クリスマス以上に大切な最大の聖日である「復活日」すらも教会に集わない、集えないという、誠に苦渋の決断を、私たちもせざるを得ませんでした。私たちは神さまに問いたいのです。「なぜ」と。なぜ、ご復活日にさえも、教会に集って共に祈ることさえ許されないのですか、と。しかし、この私たちの「なぜ」は、主イエスのお体に油を塗ることさえも許されなかった、マグダラのマリアの「なぜ」とまさしく同じものなのです。
そんなマリアに、イエスさまは、「あなたは、なぜ泣いているのか」と語りかけられるのです。そんな私たち、一人ひとりに、主は語りかけられるのです。「あなたは、なぜ泣いているのか」と。主は、私たちの尽きることのない「なぜ」を取り上げられるのです。そして逆に、私たちに「なぜ」と問いかけられる。主は、私たちがなぜ泣いているのかは、すでに十分に知っておられる。主は、「なぜ」なのかと悲しみ嘆くその私たちの「なぜ」をそのまま引き受けてくださる。そして、こう私たちに語りかけられるのです。「あなたは、なぜ、泣いているのか。あなたはもう、泣く必要はないのだ」と。
この時、私たちは気づかされるのです。本当は、この「なぜ」を問うことができるのは、唯、主のみであることを。私たちが「なぜ」と問う時に、私たち自身の人生の主人公はあくまでも「私」です。けれども、私たちが主から、「あなたは、なぜ、泣いているのか」と問われる時に、「なぜ」を語るのは主のみであり、私たちは、神さまによって、息を与えられ、私たちの人生は主のみによって導かれていることに、あらためて気づかされるのです。「あなたは、なぜ泣いているのか。私を信じ、すべてを私に委ねなさい。私は必ずあなたと共にいる。だから、あなたはもう泣かなくていい」。私たちは、その主の問いかけに、ただひたすらに、ただ一言、「アーメン」と応えて、主につき従うだけでいい。
マリアは、最初、「なぜ泣いているのか」と問われた方が、どなたかは分かりませんでした。聖書には、園丁だと思っていた、とあります。しかし、20章16節には、さらにこう記されています。
イエスが、「マリア」と言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語で、「ラボニ」と言った。「先生」という意味である。
まだ朝早く暗い中で、「マリア」と呼びかけられたその声は、彼女にとって忘れもしない、あの懐かしく、優しい主の声であったに違いありません。私たちは、それぞれの人生の中で、それぞれの日々を生きる中で、決して答えの出ない「なぜ」という問いに躓き、私たちの無力さに、涙を流します。しかし、「私はよみがえりであり、命である」と宣言されるご復活の主は、そんな私たちを無条件に抱きしめてくださる。迷える子羊を見つけ出して、その両手でしっかりと抱きかかえる羊飼いのように、ご復活の主はどこまでも皆さんお一人おひとりを愛し、包んでくださる。そして、あの優しく懐かしい声で語りかけてくださる。「あなたは、もう泣かなくても良い。私が必ずあなたと共にいるのだから」と。
私たちのあらゆる「なぜ」を引き受けてくださる主に、すべてを委ねましょう。そして、ただひたすらに「アーメン」と応えながら、主のご復活の道を共に歩みましょう。
お祈りいたします。いつくしみ深い神さま、新型コロナウイルスの感染拡大によって、今、大きな困難の中にある世界を顧みてください。病に苦しむ人に必要な医療が施され、感染の終息に向けて取り組むすべての人、医療従事者、病者に寄り添う人の健康が守られますように。亡くなった人が永遠のみ国に迎え入れられ、尽きることのない安らぎに満たされますように。不安と混乱に直面しているすべての人に、支援の手が差し伸べられますように。
希望の源である神さま、世界のすべての人々と共に手を携えて、助け合って、この危機を乗り越えることができるよう、お導きください。
ご復活の主なる神さま、あなたは、言い知れない不安と恐れの内にあるマリアに、「あなたは、なぜ泣いているのか」と語りかけられました。「私は必ずあなたと共にいる。だから、あなたはもう泣かなくていいのだ」と招かれる主に、私たちが、ただひたすらに「アーメン」と応え、主につき従うことができますように、どうぞ、強め、導いてください。
この祈りを、ご復活の主イエス・キリストのみ名を通して、み前におささげいたします。
アーメン
岡谷聖バルナバ教会は、昨年11月16日、国の「登録有形文化財」に登録された。「英国教会の伝統を受け継ぐ構造を有している一方で、かつて岡谷の蚕糸業を支えた「女工」の願いで設けた畳敷きの礼拝堂など、地域の歴史文化を伝える建築物」(文化庁文化審議会答申)としての評価を受け、すべての新聞、テレビ等でも報じられた。
90年前の1928年11月20日、岡谷聖バルナバ教会の聖堂は聖別された。当時、諏訪湖周辺を伝道していたカナダ聖公会の宣教師、ホリス・コーリー司祭は、諏訪地方のどこに教会を建てるのかという選択に迫られた。カナダ聖公会宣教協会は、より賑やかな温泉地で有名な上諏訪に教会を建てよと指示していたが、コーリー司祭は、諏訪の一帯で、最も重荷を背負わされている人々のために聖堂を建てたいと考えた。それは、岡谷の製糸工場で働く「女工」さんたちのためであった。それに対し宣教協会は、彼女たちは季節労働者で定着しないし、経済的な支えにはならず、教会を維持できるわけがないと反対した。しかしコーリー司祭は、「お金のことは神さまが何とかしてくださる」と応えた。
工場では一日16時間労働で、立ちっぱなしか、硬い木の椅子に座り続ける彼女たちが、教会に来たときには自分の実家に戻ったような思いになってもらいたいと、聖堂を畳敷きにした。当時からの信徒であった深澤小よ志さんは、かつてこう語ってくれた。「教会に駆けつけると、階段の下で青い目の司祭さんが待ちかまえていて、よく来たねと言って、私を抱きしめてくれた。お説教の意味はほとんどわからなかったけれども、司祭さんが抱きしめてくれた温かさに、私は涙が溢れた。教会は確かに天国だった。」
今年の2月2日、岡谷聖バルナバ教会の聖堂で、中国から働きに来ている王旭さんの洗礼堅信式が行われた。王さんは中国、山東省青洲市の出身で、岡谷市にあるピストンリングを製作する工場で、2016年から勤務されている。この工場には現在、60人ほどの中国からの女性たちが働いているという。ふと通りがかりに見つけたこの教会に、熱心に通い続けてくれた。彼女は3月で中国に帰国することが決まり、ご本人の願いもあって、洗礼式を行うことになった。中国には現在、聖公会の教会がないので、堅信式ができないのが気がかりであったが、急遽、渋澤一郎主教が岡谷に来てくださり、洗礼堅信式が実現した。日本語は十分にはお出来にならないため、市原信太郎司祭が作ってくださった日中対訳の洗礼堅信式文を用いた。私の問いに、王さんが中国語で応答する。洗礼名は、「馬利亜」。言い知れない感動に聖堂が包まれた。
取材に来ていた中日新聞の記者が、「あなたにとってこの教会はどのような場所であったのか」と尋ねた。彼女はこう答えた。「この教会は最高の場でした。親切で温かくて、いつも癒されました。」
岡谷はもう製糸女工の町ではない。しかし今は、中国などから来られた多くの外国人女性労働者たちが住んでおられる。歴史的文化財として認められた喜びと同時に、この聖堂が、決して過去の歴史遺産などではなく、90年前と通底するミッションのために、今も生き続けていることに感謝したいのである。
司祭 アシジのフランシス 西原廉太
(岡谷聖バルナバ教会管理牧師)
去る7月18日、聖路加国際病院名誉院長、日野原重明先生が主のもとに召された。実に105歳のご生涯であった。青山葬儀所で営まれた葬送・告別式には、約4千人の人々が、日野原先生との、この地上での別れを惜しんだ。日野原先生には、個人的にも、さまざまなことを教えていただいた。4年ほど前、聖路加の理事会終了後に懇親会があり、たまたまお隣の席が日野原先生だった。日野原先生は、私に、「ところで西原さんはおいくつですか」と尋ねられた。私は、「ちょうど50歳になりました」と答えたところ、日野原先生から、「ああそうですか。あと50年がんばってね」と返されたのも愉快な思い出である。
忘れもしないのは、2013年8月に、聖公会関係学校教職員研修会の主幹校を立教大学が務め、私は、副総長として、同研修会運営の実行委員長に任ぜられ、基調講演の講師を日野原先生にお願いしたことである。日野原先生には、「一人ひとりの存在と共にあること―聖公会学校の原点を確かめる―」という主題で、ご講演いただいた。日野原先生は、ご自身の立教大学との深い繋がりを話された後、このようなことを語ってくださった。
「世界で最初の近代的なホスピス、聖クリストファー・ホスピスが、ロンドンの郊外のシデナムというところにあります。その創立者シシリー・ソンダース先生に、ソンダース先生が長年やってきたホスピスのことを一言で言えば、どういうことかと聞きました。がんの患者で痛みがある患者にモルヒネを与えて、そうして苦しみをとり、死の不安をできるだけとってあげるという、命が制限された患者に何が必要であるかを一言で私に教えてくださいと言ったら、彼女が言ったことは、”Being with the patient”、『患者とともに』。患者がだんだん、だんだん亡くなる時に、
患者がいろいろなことを思い出して語ることを静かに聞いてあげ、ああそう、ああそうということをして、患者が語る言葉を静かに聞きながら、その腕を握ってあげて、そして患者と一緒に死ぬような態度。これがホスピスの中に必要であるということ。死ぬ人と治療する人ではなしに、一緒に死ぬのだ、ともに死ぬのだ。これが『寄り添う』という、”Being with the patient”の一番大切なことであるということだ、と。」
日野原先生のこの言葉は、これからの医学において重要な視点という文脈であったが、私たちの教会にとっての〈宣教・牧会〉の核心とは何かについても、大いに示唆されている。一人ひとりの教会につらなる者に、「寄り添う」こと。この社会、世界で、痛んでいる人々、泣いている者たち、重荷を背負って生きざるをえない一人ひとりに、ていねいに「寄り添う」こと。それは、確かに、主イエス・キリストが、この地上でなされた働きに、倣うことに他ならないのである。
(岡谷聖バルナバ教会牧師)
2016年1月11日(月)から16日(土)まで、英国・カンタベリー大聖堂において、アングリカン・コミュニオン38管区の首座主教が一同に会する「首座主教会議」が開催された。今回の「首座主教会議」は5年ぶり、ジャスティン・ウェルビー=カンタベリー大主教着座後、最初の開催であった。同性愛者の聖職按手、同性婚の祝福などをめぐって対立を内包したアングリカン・コミュニオンは首座主教会議を開くことができず、この間、カンタベリー大主教は全世界の管区を訪問し、各首座主教とも親交を温め、ようやく招集にこぎつけたのである。
今回の首座主教会議には急な事情等で参加できなかった首座主教を除き、すべての首座主教が出席した。結果として、首座主教たちは、分裂ではなく、コミュニオンとして共に在り続けることを選択した。しかしながら、それには同時に、大きな代償が払われたことが、すぐに明らかになった。首座主教会議は、米国聖公会を向こう3年間、アングリカン・コミュニオンの教理と教会行政をめぐるあらゆる意思決定から排除することを決定したのである。これは、米国聖公会が前回総会で、同性婚を可能とする教会法規改正を決議したことの「帰結」である、と首座主教会議は表明している。破れた交わりを、真に回復する再出発の時となると期待されていただけに、誠に残念な結果である。カナダ聖公会は、本年7月の総会で、米国聖公会と同様の決議を予定しているが、未だ総会決議には至っていないため排除を免れた。
そもそも、「首座主教会議」は、アングリカン・コミュニオンを支える4つの「器」(instruments)(他の3つは、カンタベリー大主教、ランベス会議、ACC)の一つでしかなく、決議機関でもない。私は、「世界改革派教会-世界聖公会国際委員会」の委員であるが、米国聖公会の神学者=エイミー・リクター司祭は、私たちの国際委員会の中核的存在である。彼女抜きにこの国際対話は成立しない。
アングリカニズム神学者で教会法の権威であるノーマン・ドー教授は、今般の首座主教会議の「決議」について、そもそも、首座主教会議にそのような教会法的権限などなく、まったくナンセンスであり、ただ、この間、アングリカン・コミュニオンが議論してきた「聖公会契約」のプロセスが破綻したことを証明した効果しかない、と明言する。植松誠日本聖公会首座主教もこのように語られた。「私は、今回の首座主教会議の結果に関しては大変複雑な、重く沈んだ気持ちでいる。世界の聖公会が分裂せずに、共に歩むことは確かに嬉しいことではあるが、その代償を見たときに、それがあまりに大きく、しかも正しいとは思えない。」
首座主教会議の「決議」の直前に、米国聖公会のマイケル・カリー総裁主教は、列席した大主教たちにこう語ったという。「私たちがすべての者を包む教会となるために献身するのは、社会理論や文化的手法への従属ゆえではありません。そうではなく、十字架の上でイエスさまが広げられた御腕こそが、私たちすべてに差し伸べられた神さまの至高の愛の〈しるし〉なのだという、私たちの信仰に基づくものに他ならないのです。」
このメッセージにこそ、私たちにとっての真の「希望」がある。
司祭 アシジのフランシス 西原廉太
(岡谷聖バルナバ教会管理牧師、立教大学教授)
岡谷聖バルナバ教会では、毎年、聖バルナバ日に近い主日を、「バルナバ祭」として特別な説教者や講師をお招きしている。今年は、東北教区、郡山の越山健蔵司祭に説教をいただいた。越山先生は、お話の中で、一冊の本を紹介くださった。福島県キリスト教連絡会が編集された、『フクシマのあの日・あの時を語る~石ころの叫び~』と題されたものだ。福島県の様々な教派の牧師さんたち16名が、一昨年の3月11日の大震災、こと、福島第一原発の爆発と、その後の放射能災害に直面して、どのような行動をとり、また何を体験したのか、という鬼気迫る証言である。
しかし、それらの多くは、あの未曾有の事態の中で、牧師たちがいかに勇敢に立ち向かったかという記録ではなく、あの時、牧師も、まずは自分や自分の家族の身を案じた一人の弱い人間であった、という悲痛なまでに赤裸々な懺悔の告白というべきものだ。もし、私が、あの場に立たされていたら、と思うと、言葉を失うばかりである。
この本の中で、ある牧師さんが記されていることは、このようなことだ。震災直後の主日礼拝を休みとし、信徒に伝えたところ、「こういう時にこそ礼拝しないんですか」と叱責され、赤面したこと。白河に避難した後に、安否を問う教団本部からの電話に対して、まだ福島にいると嘘をついたこと。避難できない教会の信徒を置いていってしまい、事実、信徒から「先生は、教会と教会員を見捨てて、自分の家族だけで逃げた」となじられたこと。
この牧師さんは、教団本部に嘘をついた時のことをこう書かれている。「電話を切った後、私はしばらくぼんやりしていましたが、心の中にペテロがイエスさまを裏切って、三度も拒んだ聖書箇所が浮かんできました。ペテロの気持ちが非常によく分かりました。あらためて自分は弱い人間だな、たいしたことないなあ、情けないなあと思いました。そして同時に、こんな私をイエスさまは、愛してくださり、救ってくださり、伝道者の末席に座すことを許してくださっていることに感謝しました。」
この福島の牧師さんたちが経験されたことは、この牧師さんたちにしか分からない、そして、今も私たちには到底分かりえない痛み、苦しみなのであろう。しかし、私たちもまた、私たちそれぞれの日常の中で、思わぬ出来事に直面し、戸惑い、茫然と立ち尽くしてしまうことがある。それぞれの十字架を背負わなければならない時が、必ずある。他者には決して理解できないような、それぞれの重荷を、それを「自分の十字架」として背負い、呻き、もがきながらも、なお、その十字架を担わなければならない時がある。
私たちもまた、それぞれの日々の十字架を背負う者だ。時には、途中で力尽き、十字架を下してしまうかもしれない。しかし、それでも、イエスさまは、私たちに、「日々、自分の十字架を背負って、わたしに従いなさい」と語り続けておられる。いや、そのように語り続けてくださっている。途中で力尽きてしまって、十字架を下さざるを得なかった者たちの無念さも、主イエスはしっかりと受けとめてくださる。そして、もう一度その十字架を担おうとする者に、主の深い慰めが注がれているのである。
司祭 アシジのフランシス 西原廉太
(岡谷聖バルナバ教会管理牧師)
3月11日、大震災が起きた。地震が起こった時、私は大学にいた。書類は倒れライトは大きく揺れ、テレビをつけるとそこには大きな津波が人々を飲み込もうとしていた。都内の交通機関も麻痺し立教のキャンパスを開放した。5千人近い人々と、私も大学で夜を明かした。翌朝には、すでに言語を絶する状況が明らかになりつつあった。詩篇詩人の、苦難を前にして、舌が上あごに張りついて、神に祈ることすらできないという嘆きそのものの経験であった。
ある女性の証言が耳から離れない。大津波から逃げようと高台に向かっている時、後ろを振り返ると、数人の小学生たちが泣き叫びながら必死に走っていた。しかし、次に振り返った時には、もうその子たちの姿は消えていた、という。ある男の子は、行方不明になった両親、兄妹の名前を段ボールに書いて避難所をまわっていた。この現実を前にして、私たちは茫然とするばかりである。
そして、地震と津波に加えて、さらなる恐怖が襲うことになる。福島第一原発の原子炉群の爆発、制御不能と高濃度放射能拡散である。学者たちは「人体に影響がないレベル」と言うが、私が工学部時代に学んだことは、それは急性障害が出るか否かだけで、人体にまったく影響がない放射能などないということだ。実は4年前に、福島原発は、チリ級津波が発生した際には冷却材喪失による過酷事故の可能性があると国会でも指摘されていた。そういう意味では、この原発事故はまったくの人災である。強烈な放射線が降り注ぐ中、身を挺して鎮圧作業に当たった人々を覚えたい。彼らの家族はどんな思いでこの作業を見守っていたであろうか。
私のもとにも、聖公会につらなる世界中の姉妹兄弟から祈りと励ましのメッセージが続々と送られてきた。カンタベリー大主教チャプレンのジョナサン・グッドオール司祭、アングリカン・コミュニオン・オフィス幹事のテリー・ロビンソン司祭によると、地震発生から30時間以内で、世界各地から数百通に及ぶ激励と祈りのメールが届けられたという。東北教区、北関東教区の信徒、教役者をはじめ、被災されたすべての人々は、今も極度の苦難と不安の内にある。被災者のみならず、私たちの誰しもが、言い知れぬ恐れを抱いている。けれども、私たちは独りではない。世界中の仲間たちがこの苦しみに共感して、自らの腸を痛め、叫びのような祈りで、私たちの手を握って離さないのだ。
今こそ、私たちの信仰が問われている。震えるマリアたちに、復活された主イエスは「恐れることはない」と力を与えられたではないか。絶望を永遠なる命へと変えられた復活の主イエス・キリストの、神から与えられた名は<インマヌエル>。この名は「主は私たちと共におられる」という意味だ。
被災地の瓦礫の中を、両手に水の入った大きな容器を持ちながら、歯を食いしばって歩く少年がいた。彼は、瓦礫の絶望の中を、それでも<いのち>という希望に向かって歩み出している。彼と共に、被災されたすべての人々と共に、そして、すべて私たち一人ひとりと共に、復活の主はあのエマオへと向かう道のように、私たちの隣を歩き、私たちの心を熱くしてくださる。
今年の復活日は特別な主日となる。それは、瓦礫の中に生え出でる小さな新芽のように、私たちが希望への新たな一歩を踏み出すための大切な時なのである。
司祭 アシジのフランシス 西原 廉太
(岡谷聖バルナバ教会 管理牧師・3月16日記)