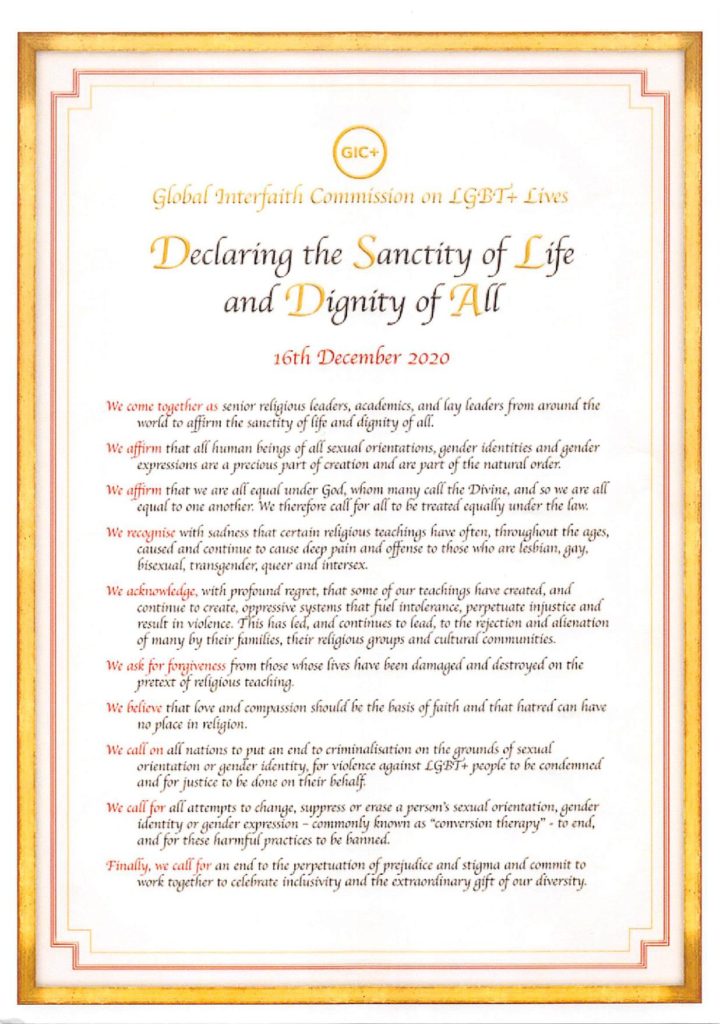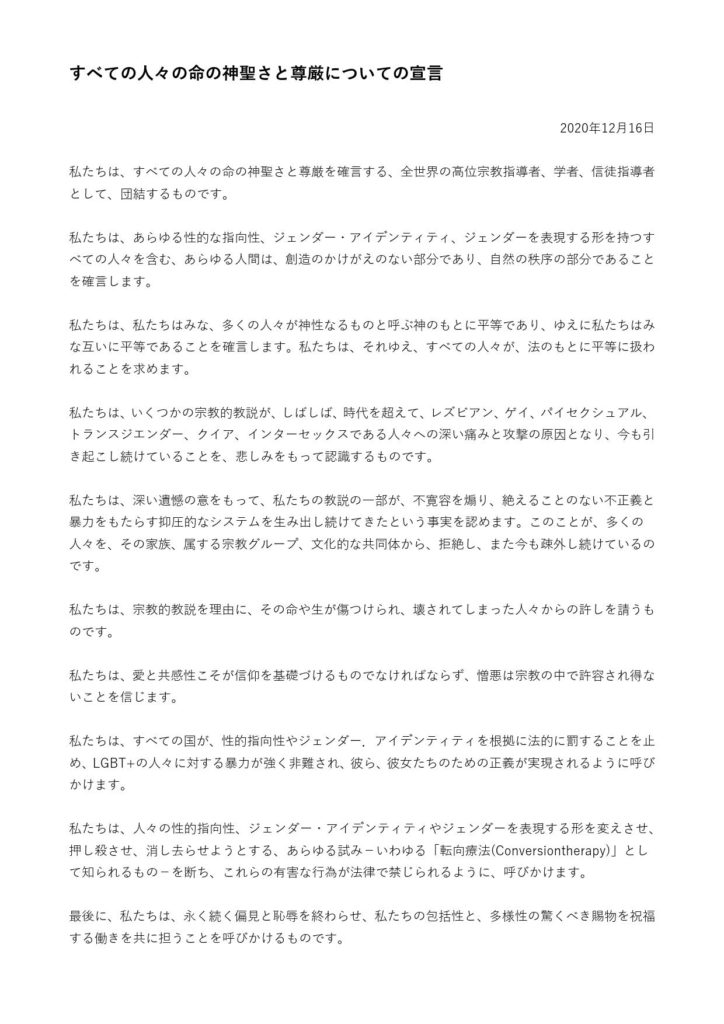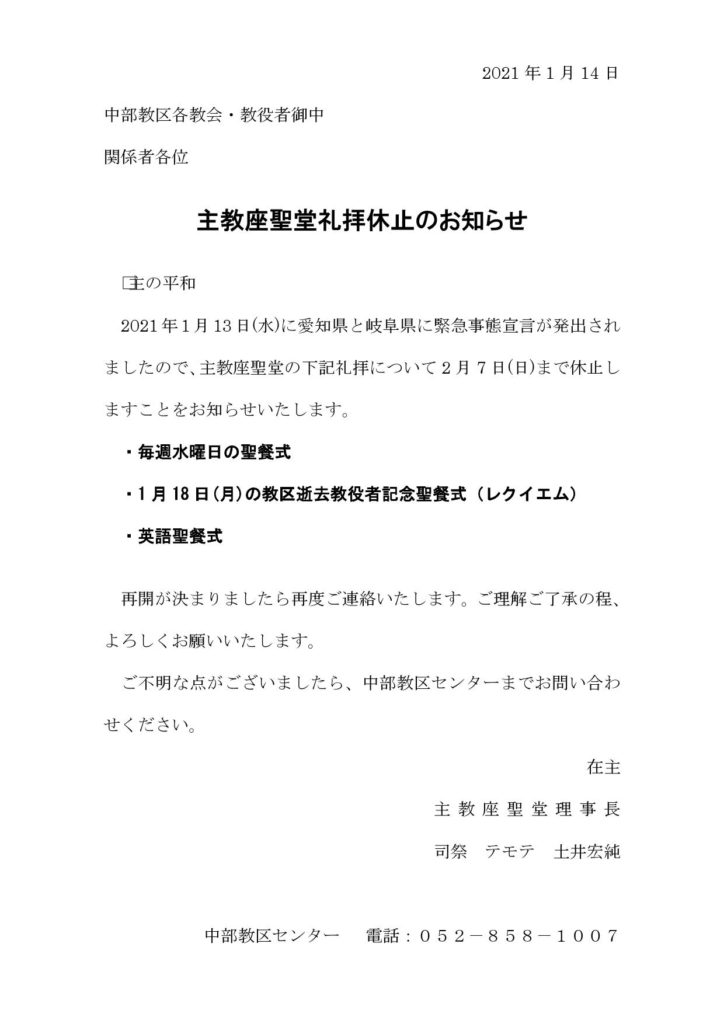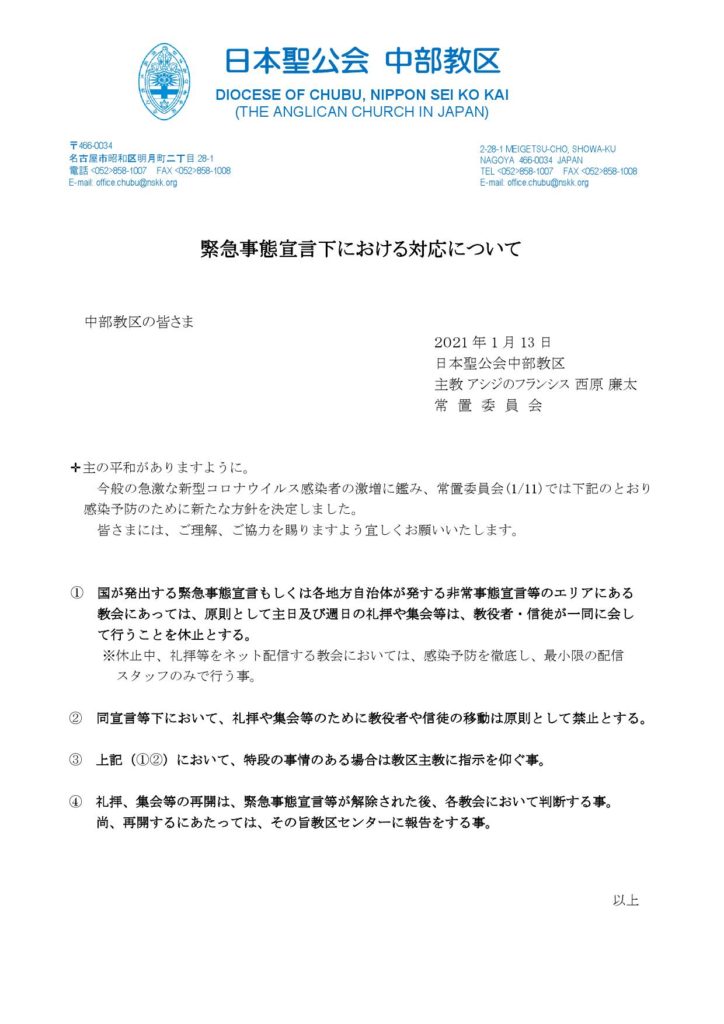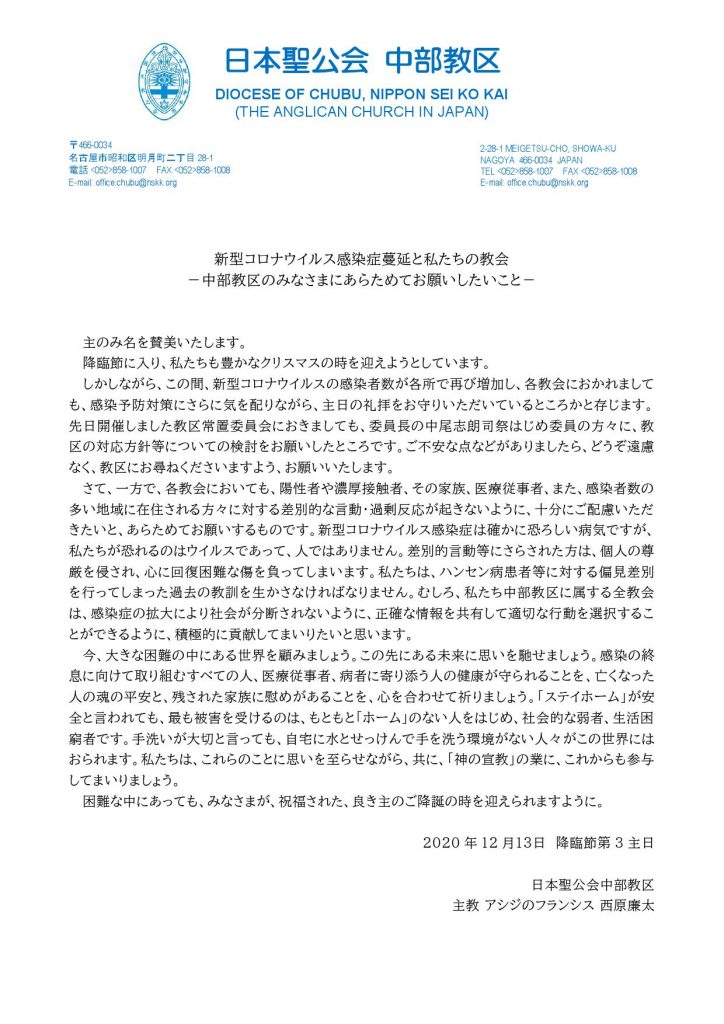カナダ聖公会ケベック教区のブルース・マイヤーズ主教は私の長年の親友でもあり、昨年の主教按手式にもZoomでご臨席くださいました。この度、マイヤーズ主教は、ケベック教区の大斎節プログラムとして、毎主日、マイヤーズ主教と親しい世界各地の主教とのビデオ・インタビューを収録し、教区の信徒・教役者に配信されています。毎回の構成は、その主教が属する教区や国の歴史、宣教課題や状況について、また、当日の聖書日課・福音書についての黙想の分かち合いとなっています。3月14日の大斎節第4主日は、日本聖公会中部教区主教の私がインタビューに招待され、楽しい時間を持つことができました。マイヤーズ主教のご許可を得て、中部教区のウエブサイトでも共有させていただきます。英語のみで、日本語字幕はつけていませんが、私の話の内容は、日本聖公会、中部教区のみなさんは良くご存知のことばかりです。日本におけるコロナ禍の状況、教会の対応、日本聖公会形成の歴史について、またカナダ聖公会の働き、岡谷聖バルナバ教会創立をめぐる、ホリス・ハミルトン・コーリー司祭(カナダ聖公会・ケベック教区ご出身)の物語、当日の聖書日課(日本聖公会の聖書日課と箇所は異なります)のヨハネによる福音書第3章14節~21節をめぐる黙想(リフレクション)などを語っています。カナダ聖公会ケベック教区とは今後もますます深いつながりを持つことができればと願っています。コロナ禍が落ち着き、海外にも再び自由に行けるようになりましたら、私たち日本聖公会中部教区のルーツでもあるカナダ聖公会、とりわけトロント教区やケベック教区を、信徒のみなさんとご一緒に訪問する「巡礼の旅」などが実現できればと考えています。
日本聖公会中部教区 主教 アシジのフランシス 西原廉太