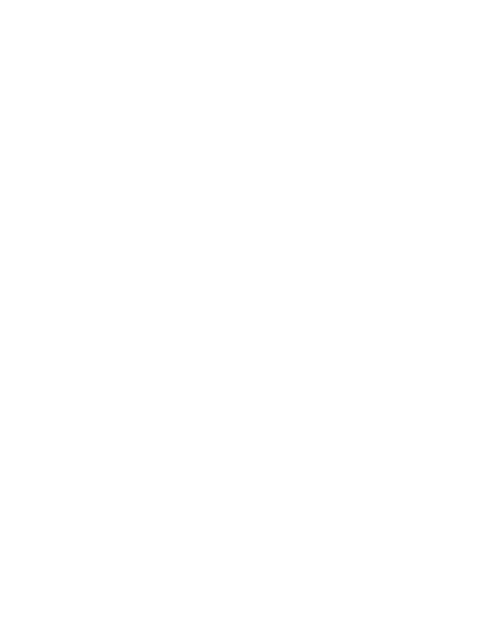新生病院のある小布施は、果物の季節を迎え、町のさまざまなお祭りや催し物が続きにぎやかです。でも一歩入った路地の木陰は静かな時間が流れています。病院の中庭も患者さんの散歩のコースになっています。ホスピスに入院された方も体の調子がいいとき静かな中庭の木々に招かれるように、緑の中に身をおいています。「(家族や病院スタッフ)皆さんに見せたくて」と庭で拾ってきた松ぼっくりや摘んできた花がホスピスのホールに飾られていることがあります。
生け花のボランティアに来て下さる方と同じようなことを患者さん自身がしてくださり、私たちのほうが慰められます。ホスピスで思うことはたくさんあります。
病という思わぬ出来事に自分も家族も悩み、やっとの思いでホスピスに来る方もいます。ホスピスは世間では「もう治らない病気のために死を迎えるところ」というイメージがあるようです。しかしそれは間違いです。
がん=ホスピス=死ではないのです。確かに病状が進み亡くなる方もいます。また治療に向けて退院する方もいます。その患者さんの生と死に意味を見い出していく時、それはただの死ではなくなるのです。残された家族や医療者を生かす力となるのです。毎年、ホスピスで亡くなった患者さんの家族に集まっていただき、入院中の思いや今の心境などを語り合う「思いを分かち合う会」というものがあります。今年の6月におこなわれた時には入院してわずか2日で亡くなった方の家族も来て下さいました。最後の時を共に過ごすことができたと感謝していましたが、同時に「もっと早く(ホスピスに)来ていればよかった」とも語っていました。すると他の遺族の方が「一所懸命お世話されたから…長さじゃないですよ」と言われていました。人は、時間が神様から与えられた限られたものであることを忘れがちです。誰でもいつかは死を迎えます。それは神様を信じていてもいなくても同じです。終末期にある患者さんに対して積極的な治療は意味がないばかりか、苦しさが増えるばかりで残された時間がつらいだけになってしまいます。
突然の病気は心に大きな波紋を起こし、やがてくる死はその重たさのために家族だけでなく、病院スタッフをも過去の時間へ引きずり込んでしまうことがあります。しかし大きな波紋の中にある生といつまでも引きずるようなつらい死に、患者さんに関わるあらゆる人たちがゆっくりと心を向けることによって不思議と「死の重たさ」が「感謝」に変えられていくのです。それは必死になって自分に引きとめようとしたものをだんだんと神様にゆだねていくような姿です。コリントの信徒への手紙Ⅰは「死のとげは罪である」と語ります。主イエスは人の存在に思いを向けた事によって「死のとげ」を取り払ったのです。私たちの間に十字架を建ててくださったのです。
ホスピスで思うことはたくさんあります。そして主イエスの出来事を思わざるをえないのです。
司祭 マタイ 箭野 直路
(新生病院チャプレン)