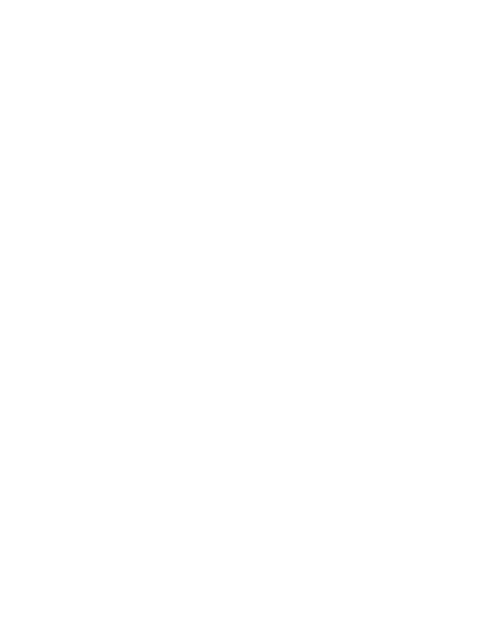2023年となりました。本年も中部教区聖職・信徒が祈りを合わせて、ていねいな〈宣教・牧会〉を誠実に担いあいたいと願います。
新年1月1日(日)は名古屋聖マタイ教会・主教座聖堂において、主イエス命名の日・主日聖餐式の司式・説教をさせていただきました。本来は、翌2日(月)、3日(火)は久しぶりの休日の予定でしたが、立教大学が実に55年ぶりに箱根駅伝本戦に出ることになったため、私も総長として、急遽、現地で応援することとなりました。
12月26日(月)には、立教学院聖パウロ礼拝堂で、「立教大学箱根駅伝出場感謝/ユニフォーム推戴式および壮行礼拝」が開催されました。礼拝の中で、立教大学の襷(たすき)と選手のユニフォームが祝福され、私から選手代表に襷を手渡しました。
そして、今回の箱根駅伝では、往路復路全10区間、この襷は見事に繋がり、ゴールを果たすことができました。実はこの襷には、10名の選手たちだけではなく、部員全63名がサインをした名前が記されていました。箱根路を走った選手たちは、部員全員の思いと、私たちすべての祈りを繋いでくれたのでした。
駅伝は、それぞれの区間は一人で走るという意味では、限りなく個人競技であると共に、襷を繋いで、チームとしてゴールを目指すという点で、完全な団体競技です。
教会もまた、個々人が信仰に生きると同時に、その信仰を先達たちから受け継ぎ、そして未来へと継承していくことによって成立する共同体です。そういう意味では、私たちは、イエスさまが〈語られ、為さったこと、命じられたこと〉、すなわち、主イエス・キリストの〈ミニストリー〉を「信仰の襷」として受け、誠実にそれぞれの人生という路を走り抜き、そして、次の世代に託していく者たちなのだろうと思います。
信仰の襷を繋ぐこと。それを「使徒継承」と言うのでしょう。
エッセイ
主教が教区報「ともしび」に連載しているエッセイです。
2022年ランベス会議に参加して
7月26日(火)から8月8日(月)にかけて英国・カンタベリーで開催された「ランベス会議」に出席させていただきました。正式な報告は、また別途の機会にさせていただきますが、ここでは特に印象に残ったことについてご紹介します。
私は1998年、2008年のランベス会議にもスタッフとして参加しましたが、今回、驚いたのは、出席した女性の主教の多さでした。1998年は「ランベス・イレブン」と呼ばれた11人の女性の主教が参加、前回は18人、そして今回のランベス会議には、笹森田鶴主教も含めて、実に98名もの女性の主教が参加されました。もはや世界聖公会は彼女たち、女性の主教たちの存在なしにはその働きを十全にはなしえないということです。
一方で、セクシュアリティをめぐっては依然として深刻な分断がコミュニオン内にあることが浮き彫りになりました。今回のランベス会議では決議ではなく「ランベス・コール」という文書を採択する方式が採られたのですが、起草段階ではなかった同性婚を否定する1998年ランベス会議決議を裏書きする文言が最終文案に挿入されたため、米国、カナダ、ウェールズなどの聖公会をはじめとして世界各地からこのプロセスに対する批判が集中し、カンタベリー大主教は急遽、この草案から当該箇所を削除することを発表しました。ランベス会議に参加したグローバルサウスの保守派主教たちは、今回出席している同性愛を公としている6名の主教たちと陪餐の列には並べないとして、カンタベリー大聖堂での開会聖餐式では席を立たず陪餐を拒否しました。
日本においても同性愛に対する無理解とそれがもたらす差別が、キリスト教の枠組みから語られることが後を絶ちません。それぞれのセクシュアリティはカラフルなものであり、その人の存在そのものと直結している。誰一人としてその人間としての尊厳が傷つけられてはいけないことを、私たちも粘り強く語り続けていかなければならないことを、あらためて確認する機会ともなりました。
全世界の主教がカンタベリーに集まります―第15回ランベス会議―
いよいよ7月26日(火)から8月8日(月)にかけて、第15回「ランベス会議」が英国・カンタベリーで開催されます。ランベス会議出席のために、教区のみなさまには温かいご献金をお献げいただきましたことに、心より感謝申し上げます。本来は2018年に開かれるべきでしたが、アングリカン・コミュニオン(世界の聖公会)内にある難題等で2年延期され、新型コロナウイルス感染症パンデミックのためにさらに2年延び、実に14年ぶりのランベス会議となります。8月23日(火)の”Bishop’s Room”や9月18日(日)・19日(月)の教区研修会などでもご報告させていただきます。
第1回ランベス会議は1867年9月24日から4日間、ロンドンのカンタベリー大主教公邸であった「ランベス・パレス」で開催されました。カナダ聖公会から、当時のカンタベリー大主教チャールズ・ロングリーに対して、世界に広がった聖公会が各地で直面する諸課題について協議するため、全世界の聖公会主教会議を招集するように要請されたことがきっかけでした。ロングリー大主教は、当時144名であった全主教に招待状を送りましたが、参加したのは約半数の76名のみでした。聖公会の重要案件は英国教会で法的に決定すべきであって、海外にいる伝道主教たちと協議する必要はないと反発したヨーク大主教はじめ多くの英国の主教たちが参加を拒否したのでした。以来、ランベス会議には法的拘束力はなく、道義的な指針を共有するものであるという性格自体は現在でも変わっていません。
その後、原則的に10年に一度、開かれることになったランベス会議は、回を重ねる毎に重みを増し、今ではアングリカン・コミュニオンにおける最重要の器の一つとなっています。前回、2008年のランベス会議には全世界の900名近い主教に招待状が送られました。私は、通訳等の補助者として、1998年、2008年のランベス会議に参加させていただきましたので、今回で3回目となります。世界聖公会の委員会等で旧知の主教さま方と再会できるのを楽しみにしています。この夏のランベス会議が無事に行われ、豊かな果実が与えられますように、どうぞお祈りください。
〝一人の生徒のための卒業式〟
私の娘が通ったあるキリスト教学校の高校卒業式のことです。娘の同級生に車いすで通学していたM君がいました。娘とは吹奏楽部の仲間でもあった彼は、高2の秋に、新たに白血病に冒されてしまったことが判明したのです。それ以来、M君は放射線治療や抗がん剤治療のため、学校にはほとんど来ることができなくなってしまいました。
そして卒業式の日を迎えました。クラスや吹部のみんなも、M君と一緒の卒業式を望んでいたのですが、体育館で彼の姿を見ることはできませんでした。ところが卒業式が終わった直後、娘の教室に、同級生や吹部の仲間たちが急遽集められたのです。そこにはストレッチャーの上に乗ったM君が、ご両親、お姉さんと一緒にいました。校長先生や他の先生たちも集まって、「M君のための卒業式」が行なわれたのです。そこにいた、同級生たちも、先生たちも、お父さん、お母さんも皆、号泣しました。
M君は、それから4ヶ月経った7月に天に召されました。翌年、私の一番下の息子が、姉と同じ中学に入学しました。息子がもらってきた、ある先生の自己紹介には、こんなことが書かれていました。
「昨年の高校卒業式、特に3Bの教室での一人の生徒のための卒業式は、一生忘れられない思い出であり、教員になって本当に良かったと思っています」
この学校が、「一人の生徒のために」という願いで満たされた学び舎であることに、感動を覚えました。一人ひとりの生徒や学生に、「あなたの存在こそが大切である」こと、そして、「あなたの存在が大切にされているように、あなたの隣人を大切にしなさい」という福音が伝えられれば、それで十分にミッション・スクールとしての使命は果たされているのだと思います。そしてまた、ここにこそ、私たち教会の〈宣教・牧会〉の本質があるのです。
〝この地上における〈正義・平和・いのち〉の実現のために〟
ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻と、いのちの蹂躙に心を痛めます。世界のキリスト者たちと共に、一日も早く平和が回復されることを祈り求めます。
今回の事態の背景には、14世紀以来のロシアとウクライナにおける正教会間の歴史的緊張関係があります。1991年にウクライナは国家として独立しましたが、従来の「ウクライナ正教会|モスクワ総主教庁」はロシア正教会の枝教会であり、モスクワ総主教の精神的な権威の下にあり続けていました。それは、多くのウクライナ人にとっては受け入れがたいものでした。そうした中、モスクワから独立したウクライナの真の国民教会の創立が試みられ、2019年1月、全世界の東方正教会の精神的首位者であるコンスタンティノープル総主教バルトロマイ1世は、ついに新しい教会である「ウクライナ正教会」を正式に承認しました。
この2つの正教会をめぐる対立は、ロシア人とウクライナ人の関係についての2つの異なる歴史的視点を反映しています。ロシア正教会にとって、ロシア人とウクライナ人はあくまでも1つの民族であり、単一の教会が彼らを統合しなければなりませんでした。プーチン大統領は、最近の論考の中でまさにこの主張を展開し、「ウクライナ正教会」をロシア人とウクライナ人の「精神的統一に対する攻撃」と激しく批判しました。
一方で、「ウクライナ正教会」の初代首座主教であるメトロポリタン・エピファニーは、「ロシア帝国の伝統」を断固として拒絶し、独自の文化を持つ独立した民として、ウクライナ人は独立した教会を必要としていると明言します。
同じイエス・キリストを主と告白する者たちの対立が、国家の軍事的暴力の一つの根拠とされることは大変悲しいことです。であるからこそ、この地上における〈正義・平和・いのち〉の実現を願い求める「エキュメニカル運動」は、きわめて重要な私たちのミッションなのです。
〝マリア・グレイスの主教按手を覚えて〟
昨年、11月3日(水)に行われた北海道教区主教選挙で、マリア・グレイス笹森田鶴司祭が選出されました。日本聖公会主教会の同意、被選者の受諾を経て、同月26日、笹森司祭は正式に主教被選者となられ、主教按手式が4月23日(土)に予定されています。按手が実現すれば日本聖公会、また東アジアで初の女性の主教が誕生することになり、私のもとにも世界中から祝福のメッセージが殺到しています。日本聖公会において最初の女性の執事、女性の司祭を誕生させたのは、いずれも中部教区(渋川良子師)であり、そういう意味でも、この度の主教按手は私たちにとっても大いなる祝福となります。
一方で、私にとっては、長年に亘って共に宣教の働きに参与してきた信頼すべき同僚が主教として召されることを喜ぶものであって、その方がたまたま女性であったということでもあります。『1995年日本聖公会宣教協議会・宣言』の草稿を、文字通り夜を徹して書き上げたのは、当時二人とも執事であった田鶴先生と私、そして私たちの畏友、故八幡明彦兄の30代同期青年でした。「宣言」の中で、私たちはこう記しました。
「私たちは、支配者の物語にではなく、民の物語に聴き続けます。そこから、私たちは、私たち自身の〈物語〉を語ります。自らの言葉で日本聖公会の歴史と現在、そして未来を語ります。こうした努力をして初めて、私たちは主イエス・キリストの福音を受肉化できると信じます」
これは同時に、私たち自身の「宣言」でもありました。私たちのこの盟約は、今に至るまで、いささかも揺らいではいないと確信しています。そのことを再確認するために、私は、一昨年の主教按手式において田鶴司祭にチャズブルを着せてもらいました。今度は、私が彼女の主教按手の証人となり、そして、主教団の同僚性(collegiality)の教理のもとに、彼女がこれから担う重荷を私も共に担います。
〝百年前の祈りと支え、そして宣教の苦闘〟
先日、高田降臨教会を訪問した時のことです。ベストリーに古い文書の入った小さな額縁が掛けられているのに気づきました。それには1910年12月4日の日付があり、「日本聖公会高田講義所」開設資金の3分の1は、カナダ・トロント聖ジョージ教会の篤信なる女性教役者の遺言による寄附であり、残りはトロント大学の「トリニチー學院」の神学生たちからの寄附であったことが記されていました。
1919年に来日し、後に岡谷聖バルナバ教会を創立したホリス・ハミルトン・コーリー司祭が、日本で最初に派遣されたのも、この高田の教会でした。私が、トロントにあるカナダ聖公会アーカイブスを調査した際に、コーリー司祭が当時のハミルトン主教に宛てた直筆の手紙を発見したのですが、そこにはこう書かれていました。
「高田、月曜日、2月6日、1922年。親愛なる私の主教さま。あなたの優しいお手紙に、心から感謝いたします。ハミルトン夫人が、素敵な本物のカナダのチーズを送ってくださったことにも、心からの感謝をお伝えしたく思います。懐かしい故郷の音が聴こえてきそうでした。私たちは、これまで、私たちの棒給で何とか生活できてきましたし、借金もありません。しかしながら、こちらに来て以来、常に、私たちの月給は、次のお給料をいただく10日も前には尽き果ててしまいます。例えば、私たちは、こちらに来てからというもの、服の一つも買えていないのです」
この一枚の書簡には、宣教師たちの、慣れない土地、決して豊かではない生活の中で、しかし、そのまさしくそれぞれに与えられた「ミッション」に、誠心誠意取り組む姿があります。今の私たちがあるのも、100年前のカナダ聖公会のみなさんの祈りと支え、そして、こうした宣教師たちの「苦闘」があったからこそであることを、心に刻みたいのです。
〝このことだけは徹底して親ばかでありたい〟
2018年2月11日(日)付『岐阜新聞』に、飛騨市長である都竹淳也さんは、このような文章を寄せておられます。
「私の次男は最重度の知的障がいのある自閉症児である。特別支援学校中学部の1年生。多くの方々のご支援をいただきながら暮らしている。次男の障がいが分かったのは2歳の頃だ。言葉の遅れなどが顕著で、不安に駆られ、医師の診察を受け、自閉症との診断を受けた。今も困難なことも多いが、我が子はかわいい」「次男のいいところはどこだろうと毎日見ているうちに、同じように職場の部下や同僚を見るようになり、強みを伸ばす組織運営をするようになった。弱い立場の人たちを意識するようになり、障がい児者だけでなく、病気や生活困窮、ひとり親家庭など、厳しい状況にいる人たちを助けたいと強く思うようになった。そうした頃、県職員だった私は、願い叶って障がい児者支援の仕事に就くことができ、重症心身障がい児者を医療面から支える仕事に打ち込んだ。
市長となった今も、弱い立場の方々の支援は市政の最重点だ。こうした分野に取り組むのは、誤解を恐れずに言えば、自分の子どものためである。公職にある自分が支援を充実させれば、多くの方々が救われる。それは次男が私をしてなさしめたことであり、この子が世の中のお役に立てたことになるからだ。このことだけは徹底して親ばかでありたいと思う」
確かに、主イエス・キリストがヨルダン川でヨハネから洗礼を受けた時に聴いた天からの言葉は、「あなたはわたしの愛する子、わたしの心に適う者」(ルカ3:22)でした。イエス・キリストも私たち一人ひとりを「愛する子」として徹底して大切にしてくださった。そのような愛をもって、私たちも、私たちの隣り人のために、まるで親ばかのように無条件で愛することが求められているのだと思うのです。
〝コロナ時代における新しい神学を〟
去る3月20日(土)に開催されたキリスト新聞社主催のオンライン配信イベント「コロナ時代に問う『神学+教育2.0』」に、いずれも畏友の同志社大学の小原克博教授、関西学院大学の中道基夫教授と共に、パネリストとして参加しました。各パネリストが奉仕する大学の現状や、オンラインかリアルかという二者択一の議論を超えて、「ポストコロナ」のキリスト教、学校、教会が生きる道について語り合いました。私も小原先生や中道先生からさまざまな気づきを与えられました。
中道先生は、「オンラインによって、教会に集まる意味や礼拝の本質が問われることになったと同時に、これまで多忙であった牧師が信徒と共に学ぶ時間が取れるようになり、普段は仕事などで主日に教会に行くことが困難な人々に対しての宣教のチャンスが生まれたのではないか」と指摘されました。小原先生は、「礼拝とは説教を聴いていれば良いというものではなく、教会はキリストの体であり、すべての者がキリストの体につながっていることを再確認する場である。そう考えるとき、本当にオンラインで十分なのか考える必要がある。私たちはあえて自由を放棄して、毎週教会に集っている。不自由で不便な教会には、世の中にはないものが教会にはあるのだということを示し続けなければならない」と問われます。
私は聖公会の立場から、北海道教区の植松誠主教さまの牧会実践を紹介しながら、一人ひとりへの丁寧な顔と顔を合わせた聖餐を通した具体的なつながりが、私たちにとっていかに重要なものであるかを強調させていただきました。
新型コロナウイルス感染症パンデミックという危機を経験した私たちが、社会に通用する言葉で、新しい神学をどのように語っていくのかが、教会の宣教的・社会的責任であるという点で、私たちは一致しました。
麦畑(「ともしび」3・4月号)
主教としての働きをはじめて、あらためて感謝なのは、教区の一つひとつの教会を訪問できることです。降臨節には、実に30年ぶりに一宮聖光教会を訪れる機会が与えられました。現在、聖堂の新築中ですが、旧聖堂での主教司式の最後の聖餐式を信徒のみなさまと共におささげすることができました。
礼拝前、聖堂前の植え込みに、少し錆びた恐竜のオブジェが置かれているのを発見しました。信徒さんに伺うと、それは長い間司牧された菊田謙司祭の娘さんで、かつて私が名古屋学生センターの主事をしていた頃からの青年仲間の片岡真実さんが作られた、大学の卒業制作だとのことでした。
真実さんは今や世界的なキュレーターとなられ、現在、東京・六本木にある森美術館の館長や国際美術館会議会長を務められています。先日も森美術館の特別展を、片岡館長直々のご案内で鑑賞させていただきました。1月5日付け朝日新聞夕刊にも一面を使って真実さんのインタビュー記事が掲載されていましたが、その中で印象深かったのは、「名前『真実』は新約聖書の一節に由来する」と記されていたことです。
昨年末、2022年に開催される国際芸術祭「あいち2022」(旧「あいちトリエンナーレ」)の芸術監督を、真実さんが担われることが発表されました。その記者会見の中で、未来のみならず過去の多様な人類の歴史にも光を当て、新型コロナウイルスや、人種、ジェンダー、民族的な差異に対する差別や不平等などの課題を、現代の問題としてとらえ対峙していくことの大切さを強調された上で、こう語られたのです。
「生きることは学び続けること。未知の世界、多様な価値観、圧倒的な美しさと出会うこと」
私は、これはまさに彼女の「祈り」なのではないかと思います。私たち教会が語るべきメッセージのひとつが、ここにあります。