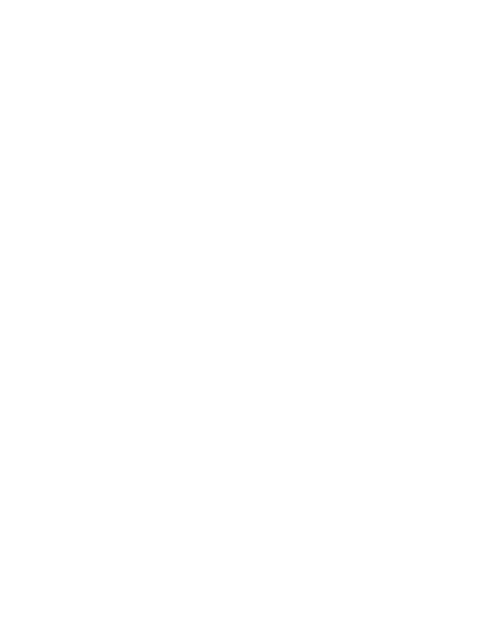「だから、あなたが祭壇に供え物を献げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰って来て、供え物を献げなさい。」(マタ5・23~24)
ぼくの故郷は日本海に面した町で、長く続く緑の松林と白い砂浜、青く広がる海があります。ぼくの子どもの頃にはなかった原子力発電所が岬の先端に蜃気楼のように見えています。
子どもの頃、よく家族そろって海水浴に出かけました。
松林の中でお弁当を広げていると、風にのって太鼓や鐘の音がにぎやかに聞こえてくることがありました。
その楽しそうな音につられて見に行くと、一団の輪の中で、女の人たちがくるくる踊っていました。
白く光る袖や裾がひらひらと舞うのを、ぼんやりと見ていたことを思い出します。
ずっと後になって、その着物がチマチョゴリという民族衣装だと知りました。
ぼくが小学5年生のときだったと思うのですが、同じ学級に金(キム)くんという生徒がいました。
ぼくは「きんちゃん」と呼んでいたようです。
きんちゃんはいつも同じ服を着ていて、その服の胸と袖のところがペカペカに光っていました。
からだからニンニクの匂いがするので、「くさい、くさい」と鼻をつまんではやされたり、大人たちをまねて、きんちゃんの国の人をさげすむ言葉でからかわれていました。
教会の日曜学校へ行っていたぼくは、イエスさまの光の子なのだから、かわいそうなきんちゃんの友だちになろうと思いました。
ぼくがきんちゃんと仲よくしようとしたのには、もう一つわけがありました。
ぼくは運動が大の苦手で、鉄棒も跳び箱もまるでだめ、かけっこもいつもビリで恥ずかしい思いをしていました。
それが何と、きんちゃんはぼくよりさらに走るのが遅いのです。
だから、きんちゃんと仲よくしていて同じ組で走れば、ビリにならなくてすむと考えたのです。
ある日、空き地の草むらに二人だけでいた時のことだったと思います。
突然、きんちゃんがぼくを押し倒し、馬のりになって、ぼくの頭を地面にゴリゴリ押しつけました。
ぼくはなぜそんなことをされるのか分からず、きんちゃんの顔を見上げると、きんちゃんが泣いていたのです。
ぼくはきんちゃんをはねのけることも、やり返すこともできませんでした。
ぼくの坊主頭には穴があき、血が出ていました。
家に帰ると母が怒って、
「誰にこんなことされたの」と聞きましたが、ぼくは決して、
「きんちゃんにやられた」とは言いませんでした。
それからしばらくして、きんちゃんは学校に来なくなりました。
これは1952年頃の私の忘れられない記憶です。
執事 ヨハネ 大和田康司
(名古屋聖ヨハネ教会牧師補)